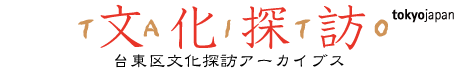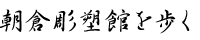一階住居部分
ここは朝倉文夫の書斎です。この通り天井まで本がぎっしりと入っていますが、見て分かりますのは、相当量の洋書があります。和書については朝倉の蔵書が主ですが、洋書は元は岩村透という東京美術学校の先生の蔵書でした。岩村透は近代日本の初期の美術評論家であり、それから美術ジャーナリスト、そして教育家として活躍した人物です。そして大正の早い時期に亡くなりましたが、朝倉の先生でした。これは今日では、現代美術史を研究していく上でも貴重な蔵書ですが、岩村透が亡くなった後に遺族の方がこの蔵書を手放して、その蔵書が本郷の古本屋さんにまとめて出ているという事を弟子から聞いて、それでは大切な先生の蔵書が散逸してしまうという事で朝倉はこれらを買い戻しました。当時、三千円という値段が付いて、立派な家が一軒建つような値段でした。朝倉は自分の家を抵当に入れて、銀行から五千円のお金を借りて、本屋さんは元値じゃ可哀想という事で千円上乗せして、岩村先生のご遺族に千円を渡して、私が預からせて下さいとい言って守りました。朝倉文夫は岩村透の胸像も作っていますが、大変尊敬していて、これを朝倉文夫が守った事は今日の私たちにとっても大変有り難い事だと思います。

Q: 高村光太郎の「手」を題材にした作品がありますね。
これは、購入したものです。これには色々なエピソードがあります。高村光太郎は朝倉と同年齢で、明治16年(1883)生まれでした。光太郎は高村光雲の息子で、そうした環境で生まれ育って、当時は飛び級というのがあり、非常に若くして東京美術学校に入り、しかも飛び級で卒業する。そしてヨーロッパにも留学した人でした。一方、朝倉文夫は田舎で中学校を落第して、上京しても美術学校にすぐには入れませんでした。同い年なのに、朝倉が美術学校に入った年に高村光太郎はすでに卒業しているわけです。朝倉は文展でデビューし、華々しい賞を獲得し、次々と作品を世に出て行くのですが、その時にヨーロッパから帰ってきた高村光太郎は、なにしろ筆が立ちますし、当時の美術批評家の中でもあれだけ美術について本質的な事が書ける人はそういなかったと思いますが、朝倉の作品についても非常に厳しい批評をしました。
朝倉の代表作のひとつに「吊るされた猫」がありますが、手で猫が捕まえられてだらんとしている姿を作っていますが、これを光太郎は比較的褒めているんですが、文展の作家というのはやたらと図体の大きいものばかり作って威張っているが、彫刻というのは指一本だっていいのだと言っています。(右段に続く)
そうした中で、猫一匹をこのように出品する事はかえって良いというように褒めています。ただ、その後返す刀でそれにしても腕のつくりがなっていないと光太郎は言うわけです。で、その後に、朝倉は珍しく「腕」っていう作品を作っていますが、この作品はどこの展覧会にも出品してません。

それで、その作品の裏に書かれた朝倉のサインを見て、おおよそどの時代を推測すると、ちょうど光太郎に厳しく言われた時期に、どうも腕を作る練習をしていたのじゃないかと推測できます。光太郎は二度目の留学をしようと考えていて、最初の留学は父がお金を出してくれたのですが、二度目はもう出さないというので、そのため光太郎はこのような作品を作って、作品頒布会を計画しました。朝倉と高村光太郎の共通の友人の小説家の田村松魚は、双方の家に出入りしていました。そこで、松魚が光太郎の話を朝倉に伝えた。それで、前から腕が良くないとか色々言われた事もあったのかどうか分かりませんが、朝倉からとは伝えないで光太郎に手をひとつ作ってくれと松魚を介して注文をしました。そのような経緯で作られた作品がこの「手」です。この「手」については、朝倉文夫は晩年弟子に話をしていて、そのお弟子さんから私は直接聞きましたが、見てご覧、光雲先生の息子さんは本当にロダンを勉強している。こんな立派な作品はないと言って、これをいつもこの書斎の棚において、君たちもこれを見て勉強しなさい。そういう話でも、朝倉からロダンというものを軽蔑しているどころか、非常に評価をしていた。それで、高村光太郎の仕事を非常に評価をしていたという事が浮かんできますね。高村光太郎は、この事を知らなかったと思います。彫刻は、原型があれば何本か作る事ができます。国際ルールでは、8点までという事になっていますが、状態の良い原型から抜いたほうが良いに決まっていて、この作品は版画でいうところのファーストエディションです。最も早い鋳造です。竹橋にある近代美術館に同じ時期に作られた作品がもうひとつありますが、おそらくこの二つが内容の良いものだと思われます。(次ページに続く)

それで、その作品の裏に書かれた朝倉のサインを見て、おおよそどの時代を推測すると、ちょうど光太郎に厳しく言われた時期に、どうも腕を作る練習をしていたのじゃないかと推測できます。光太郎は二度目の留学をしようと考えていて、最初の留学は父がお金を出してくれたのですが、二度目はもう出さないというので、そのため光太郎はこのような作品を作って、作品頒布会を計画しました。朝倉と高村光太郎の共通の友人の小説家の田村松魚は、双方の家に出入りしていました。そこで、松魚が光太郎の話を朝倉に伝えた。それで、前から腕が良くないとか色々言われた事もあったのかどうか分かりませんが、朝倉からとは伝えないで光太郎に手をひとつ作ってくれと松魚を介して注文をしました。そのような経緯で作られた作品がこの「手」です。この「手」については、朝倉文夫は晩年弟子に話をしていて、そのお弟子さんから私は直接聞きましたが、見てご覧、光雲先生の息子さんは本当にロダンを勉強している。こんな立派な作品はないと言って、これをいつもこの書斎の棚において、君たちもこれを見て勉強しなさい。そういう話でも、朝倉からロダンというものを軽蔑しているどころか、非常に評価をしていた。それで、高村光太郎の仕事を非常に評価をしていたという事が浮かんできますね。高村光太郎は、この事を知らなかったと思います。彫刻は、原型があれば何本か作る事ができます。国際ルールでは、8点までという事になっていますが、状態の良い原型から抜いたほうが良いに決まっていて、この作品は版画でいうところのファーストエディションです。最も早い鋳造です。竹橋にある近代美術館に同じ時期に作られた作品がもうひとつありますが、おそらくこの二つが内容の良いものだと思われます。(次ページに続く)