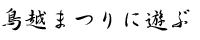鳥越神社
鳥越神社は日本武尊を祭神とし、その創立は今から1300年以上も昔の白雉二年(651年)と伝えられています。もともとこの地は周囲より一段高い丘で、神社はその上に祭られていました。徳川の入府にともない武家屋敷の用地を確保するため丘は取り崩され、更にその後の埋め立て工事などにより平地となり現在の姿となりました。(台東区鳥越2-4-1)

鳥越まつりは、地域の絆
鳥越まつりは「千貫神輿」とも呼ばれる大神輿の渡御(神輿をそれぞれの町会に引き継いで担ぐこと)が有名です。昔から6月9日に行われるのが習わしでしたが、交通事情等により現在では6月9日に近い日曜日に渡御が行われています。神社のまつりを支える睦会は明治45年(1912)に結成され、平成24年(2012)には100周年を迎えました。まつりの最終日は早朝6時30分に鳥越神社を出発した「千貫神輿」はそれぞれの町会へ受け渡されながら一日かけて氏子町会を巡ります。夕方、日が陰ると千貫神輿に下げられた提灯に灯が入れられ、まつりのクライマックスの宮入となり、睦会の手によって神社に戻ってきます。
二十三町会の21基の神輿が出揃い、それぞれの神輿には町会名の入った提灯が灯され、半被(はっぴ)の背の町会名が色鮮やかに映えます。多くの観客に見守られる中、闇夜の中をゆらゆらと揺れる提灯の明かりとともに移動する神輿の姿は圧巻で、下町の風物詩となっています。まつりは一般の氏子の他に、「氏子敬神会」や「鳥越神社十八ヶ町睦会」が中心となり、まつりの一切を取り仕切って、親子二代、三代と伝統を引き継がれて支えられています。

鳥越神社
鳥越神社は日本武尊を祭神とし、その創立は今から1300年以上も昔の白雉二年(651年)と伝えられています。もともとこの地は周囲より一段高い丘で、神社はその上に祭られていました。徳川の入府にともない武家屋敷の用地を確保するため丘は取り崩され、更にその後の埋め立て工事などにより平地となり現在の姿となりました。(台東区鳥越2-4-1)