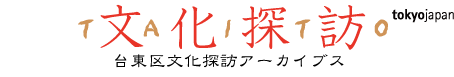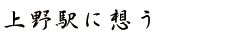上野駅は、平成12年(2000)から始められた新たな駅作りのプロジェクト「ステーションルネッサンス」の第1号です。



上野駅構内の台東区を初めとして様々な地域や地方の物産や製品を「旬のもの、地のもの、縁のもの」と題して販売し、地域の魅力を知らせる直販店「のもの」
JR東日本グループに、地域での活動について伺いました。
Q: 御社での地域活性化の取り組みについて、お話し頂けませんか。また、どのような体制で取り組まれていますか。
園田 : JR東日本グループ : JR東日本グループでは鉄道ネットワークを活かし、地域と一体となって「ヒト」と「モノ」の循環を創出する「地域再発見プロジェクト」を推進しています。具体的には、地域と連携した産直市の展開、伝統工芸品の発掘、農産加工商品の開発・販売などを通し、地域における新たな雇用創出や資源の活性化を行なっています。また、イベントや地域情報の発信を地元と都心の双方向で行い、人の移動を含めた交流の創出を目指しています。
Q: 上野駅で展開されている「のもの」のコンセプトや目的、そして将来について、伺えますか。
「のもの」は、作り手である生産者が商品と地域の魅力をお客さまに直接お伝えするショップです。店舗では、地元の方々が商品に対する思いや地域の魅力等を伝えます。これまでも産直市を通じて、地域の魅力を首都圏のお客さまに紹介する場を作ってきましたが、常設店舗の開設により、中小のメーカーや生産者の販路拡大へ貢献するなど、これまでの取り組みをより強化していくことを目的としています。現在、「のもの」の店舗のほか駅のコンビニ「ニューデイズ」9店舗でも販売を行ない、首都圏での更なる販路の拡大を行っています。
Q: 「のもの」で販売されている製品は、既成の製品ですか。あるいは、新たなブランド等の形成も予定されていますか。
現在は中小のメーカーや生産者のこだわりのものを紹介していますが、将来的には、実績を踏まえながら、より魅力的な商品の開発等も検討していきます。
Q: 今日の鉄道や駅のデザインは、コンプレックス施設(複合施設)等の新たなコンセプトにより、単に電車に乗る停車場等も変わりつつありますが、どのような展開がありますか。また、複合化等については、どのようにお考えですか。
当社では、駅の可能性を100%引き出すとともにお客さまの利便性の向上を目指した21世紀の新しい駅づくりとして平成12年(2000)より「ステーションルネッサンス」を推進しています。(右段に続く)
バリアフリー設備の整備やコンコースの拡幅、案内サインの改良等の駅設備改良工事にあわせ、既存設備を徹底的に見直し、新たな事業スペースを創出しつつ、地域に密着した駅づくりを行うなど、「駅を変える」ためのさまざまな取り組みを進めています。上野駅は、その第1号として、昭和7年(1932)に完成した駅舎をお客さまの視点で全面的に見直し、平成14年(2002)に「人にやさしい駅づくりと駅の魅力向上」等をテーマにリニューアルしました。
Q: 地域活性化についての課題や問題とは地域と鉄道やその駅の地域における有用性とは、どのような点でしょうか。
多くのお客さまにご利用いただく「駅」は、都市と地方、地域と地域を結ぶ鉄道ネットワークの基点、そして地域の中心的存在です。JR東日本では、お客さまの利便性向上、地域活性化および保有する資産価値の最大化をめざし、「駅を中心とした魅力あるまちづくり」を引き続き積極的に展開していきます。