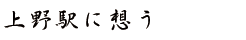中央改札口近くには、昔ながらの構造の通路が残っています。

JR上野駅長の園田恭久さん
JR上野駅長の園田恭久(やすひさ)さんに、お話しを伺いました。
Q: 現在の上野駅の駅舎についてお話し頂けますか。
園田 : 現在の駅舎は、明治16年(1883)の開業当時の駅舎ではありません。当時の駅舎は、大正12年(1923)の関東大震災の際に焼失し、その後の昭和7年(1932)に建設された駅舎が現在の駅の原型です。駅舎内は、その時々にリニューアルされていますが、広小路から正面口の建屋は、第二次大戦時の空襲でも被害をまぬがれたため、外観はそのまま残っています。
Q: 現在の駅舎の構造は、創建当時から変わらず、地下もあったのでしょうか。
昭和7年の駅舎の創建当時は地下2階であったと聞いています。駅の構造としては、現在でも物流関係は下から上がってくる仕組みになっています。現在は、地下鉄や京成線への通路は別として、地下は主に物流倉庫、荷捌きの場として使用しています。東北・上越新幹線は地下4階にあります。新幹線の地下化は国鉄時代から工事しており、17~20番線の下にホームを作っています。昭和7年当時にあった地下とは別の場所になります。地上部でも18~20番線を改修して新幹線の用地にして、その上に建屋を作り駅長室や貴賓室などがあります。中央改札口前の13、14番線のあたりは当時の雰囲気を残していますね。ちなみに昭和2年(1927)には、東京地下鉄道(現東京メトロ銀座線)の上野-浅草間が開通しています。
Q: 駅構内に置かれている美術作品やモニュメントの位置は、設立当時から変わっていますか。
朝倉文夫氏作の「翼の像」は変わっていませんが、同じく朝倉文夫氏作の「三相」は設立当時とは位置が変わっています。また「あゝ上野駅」の記念碑は、不忍口を出たところにあります。設立当時は中2階は浅草口に連絡していて出ることができました。現在では、途中から階段で降り中央口に出るようになっています。以前は、浅草口、不忍口、上野口とありましたが、昭和40年頃に名称が変わり、公園口ができました。その後、改めて東西大連絡橋が作られました。
昭和7年当時の駅舎から、外観の大きさは変わりませんが、通路は増えました。連絡通路は後に作られたものですが、新幹線の他は駅のホーム自体は大きくは変わっていません。明治16年頃の構内図では、今で言う高崎・宇都宮線のホームは一本のみでした。本屋と呼ぶ駅舎は創建当時のままです。商業スペースとして、アトレ、コンコース中にはエキュートが加わりましたが、駅自体が大きくなっているという訳ではありません。
Q: 上野駅の一日の乗降客は、どのくらいですか。先の東日本大震災時には影響はありましたか。
上野駅の一日の乗降客は、35万人程です。乗降する人の多くは、地下鉄への乗り継ぎや、通勤・通学のお客様、動物園、博物館等に行かれるお客様などですね。朝は、高崎線、宇都宮線経由で上野で山手線や京浜東北線に乗り継がれるお客様はかなり多いのですが、乗降がないのでその内にはカウントされていません。
災害に際しては、構内でも一時的に滞留場所として使って頂けるように、非常用品等の準備もしています。
Q: 上野駅の職員数は、どの程度おられますか。
上野駅だけで300名余です。切符の発売や改札口でのご案内、列車の運行に携わる信号、ホームの担当など、駅の仕事は、朝4時頃から始まり、深夜の1時半頃までありますから、常時80名程が駅に宿泊し、交代で勤務しています。(右上段に続く)

Q: 寝台特急カシオペアが停留する場所は、何というのですか。
カシオペアが停車する13番線は、カシオペアを初めとして北斗星、あけぼのなどの寝台列車の発着が多いため、「五ツ星広場」と呼ばれています。開設当時は広場でしたが、現在は縮小しています。寝台特急カシオペアは週3回運行で、一編成しかない列車で上野から札幌までを往復しています。片道1日掛かるので、隔日運行になってしまいますが、利用者は大変多いですね。
Q: 将来の鉄道は、寝台特急カシオペアやヨーロッパのオリエント急行のように高品質化すると予測していますが、いかがですか。
お客様のニーズという意味では、カシオペアでじっくり時間をかけて鉄道の旅情を楽しみながら行きたいという方もおられれば、飛行機で羽田から短時間で行きたいという方もおられます。
上野から発着する特急列車は、以前は今以上の本数がありましたが、新幹線開業などによりご利用のお客様が減ってしまいました。時間を有効に使いたいというニーズの方が多いのでしょう。鉄道の輸送サービスの品質を上げて行くには、両方のニーズについて、それぞれ満足をして頂ける輸送を提供していかなければいけないと思っています。また都心を走る山手線等のように、都内の輸送を担うものと、新幹線や特急列車のように都市間を結ぶものでは、それぞれ役割が異なっています。これからもニーズに沿った提供を心掛けて行きたいと思います。
Q: 近年、駅の複合化が進んでいますが、将来的な構想はどのようになっていますか。高架下の駐車場や倉庫から、御徒町-秋葉原間に開設された施設2K540等の多様な展開があるようですが。
近年では少子高齢化も進んで鉄道利用のお客様の減少も見込まれる中、アトレやエキュート等の施設のように、より便利に駅を使って頂けるよう、鉄道をご利用の際に合わせてお客様にもご利用頂ける施設を作っています。
通過点の駅ではなく、いつも利用して頂ける駅を目指しています。2k540を見て頂ければ、これまでの高架下のイメージが変わると思います。2k540のような試みはJR東日本都市開発が企画しています。また上野駅には、地産をテーマとした地域振興を目的とした直販店「のもの」があります。それぞれの地域まで行かないとと入手できない物産などの「旬のもの、地のもの、縁のもの」を販売する施設と催しでです。見て頂き、そして食べて頂いて、その地域にも行ってみたいという気持を喚起する事も目的としています。いわゆる「もの」と「人」を交流させるコンセプトからできた店舗です。対象とした地域や内容は一定期間ごとに変わります。(次ページに続く)
JR東日本のページから現在の上野駅の構造が分かります。JR東日本・上野駅構内図

東北本線の起点


2k540(ニーケーゴヨンマル)
御徒町駅-秋葉原間の高架下に開設された御徒町の「ものづくり」をテーマとした施設。施設名の2k540は、鉄道用語による東京駅を起点とした「キロ程」で2k540mに位置する事から名付けられています。秋葉原と御徒町の中間にあるため、「2k540 AKI-OKA ARTISAN」とも呼ばれています。

JR上野駅長の園田恭久さん

東北本線の起点


2k540(ニーケーゴヨンマル)
御徒町駅-秋葉原間の高架下に開設された御徒町の「ものづくり」をテーマとした施設。施設名の2k540は、鉄道用語による東京駅を起点とした「キロ程」で2k540mに位置する事から名付けられています。秋葉原と御徒町の中間にあるため、「2k540 AKI-OKA ARTISAN」とも呼ばれています。