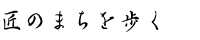べっ甲とは

べっ甲の魅力とは

江戸べっ甲師を志したきっかけとは
江戸べっ甲師になられたきっかけを教えて下さい。

べっ甲について
べっ甲製品は、どのような材料から作られるのですか。
タイマイというウミガメの一種だけしか使えません。甲羅が13枚ついていて、お腹や周囲に13枚ずつ、色んな形の甲羅が付いています。周りのギザギザは爪と言うんですけど、ここからはアメ色のものが作れて、価格的には最も高い部位なんですよ。一般には、ほぼ黒っぽいのがほとんどです。100頭いたら、80頭から90頭は黒くて、その中の1割ぐらいに白っぽい亀がいるんです。甲羅は、個体によって色や模様が全部違います。薄い製品には、5年ぐらいの小さいのも使いますが、大体は10年ぐらい育たないとべっ甲としては使えないですね。
タイマイ以外のものでも、べっ甲を作ることはできるのでしょうか。
べっ甲に使用するものは、タイマイじゃないかなあ。他の材料だと貼り合わせがうまく行かないようです、アオウミガメとタイマイを掛け合わせた細工もありますが、貼り合わせの付きが悪いので今は使わないですね。もっとも戦前は輸入禁止だったので、馬や牛の爪を使ってべっ甲職人は作っていたようですね。江戸時代から、べっ甲は禁制品だったので、昔のものでもほとんどべっ甲のものはないんですよ。色は似ているので、一般の方では判らないんですね。大名ぐらいの身分の高い人しか、べっ甲製品は持てなかったんです。また、べっ甲は虫が食って劣化してしまいますから、倉庫にしまっていてもなかなか残っていないんですね。
昔の技術や製品の違いはあるでしょうか?
昔は機械がなかったので、磨きには鹿の革を使って時間をかけて磨いたとか。貼り合わせも、卵の白身を使っていたらしいですね。火鉢みたいなものを鏝(こて)代わりにして熱さを調節しながら、くっつけていったらしいです。最近では、アクセサリーはブローチ、ペンダント・トップ、ネックレスなどの洋風の製品の方が受けますね。栞(しおり)やペーパーナイフの製品は、思いついて作ってみたものです。注文があれば、何でも作ります。今までにあった注文は、髭を整える櫛や香入れ、数珠などですね。
平成5年(1993)のワシントン条約でタイマイは輸入禁止になりましたが、どのように対応されているのでしょうか。また、今後べっ甲製品はどのようになって行くのでしょうか。
輸入禁止になってから15年以上が経ちまして、みんな在庫分で何とかやっていますが、今沖縄の石垣島で養殖を進めていて、事業化に向けて取り組んでいます。まだ言えませんが、何年か後には今後はこれを一緒に使って行くようにはなるでしょう。養殖と天然の材料の違いは、見た感じではほとんどないですね。
製造技術について
製造工程を教えて下さい。

最も難しい工程は何でしょうか。
最も難しいのは、貼り合わせですね。綺麗に平らにして貼り合わせないと、熟練した職人さんの製品ほど剥がれるようなことはないと言いますね。甲羅は、一年ごとに成長しながら年輪のようになっています。そのため、材料自体も自然に割れる可能性もあります。その年の気候などによっても自然に割れてしまう場合もあります。
作品について
色鮮やかなべっ甲眼鏡は、どのように作られているのでしょうか。

アクセサリーのモチーフはどのようなものが多いのですか。

(左:ペンダント、帯留め兼用─沈金を施したもの、右:ループタイ─べっ甲に蒔絵(まきえ)を施したもの)
昔のべっ甲製品をリフォームされる方もおられますか。
リフォームする人は、そう多くはないですが、 昔のデザインでも形見だから身に着けたいとなると、 我々のような職人を探されますね。デパートでは修理や磨きをやってくれないから、そう方が専門店を探される訳ですね。昔持っていた形見の眼鏡だとか、形見だから何かに加工してくれとか、そういう依頼があれば、イヤリングにするとか、ネックレスにするとか、眼鏡を磨いてレンズを変えるなどしますね。
べっ甲製品の取り扱い、保管方法について教えて下さい。
べっ甲の素材はタンパク質ですから、一年くらい使わないでしまっておくと、虫に食べられてしまいますね。桐箱にナフタリンを入れてしまって、半年に一度くらい空気に当てて下さい。なるべく油分を拭き取ってしまって頂いた方が良いですよ。眼鏡のように毎日使用するものは、就寝前に柔らかい布で拭いて頂くと長持ちします。
湯気に弱いので、お風呂や水分は良くないですね。すぐに拭けば問題はありませんが、そのままにしておくとひび割れて劣化してしまいます。磨くと、また新品のようになりますが、眼鏡でしたら、1年か2年に1回ほどは、磨きに出して頂くと長持ちします。
活動について
インターネットの動画サイトへの出演や、体験教室も開催されていらっしゃいますが、どのような活動をされていますか。
材料入手の問題からも、後継者もなかなかないということもありますが、今は若い方も本物のべっ甲に触れる機会はなかなかないと思います。べっ甲やその技術について若い方にぜひ知って頂きたいと思い、取材にはなるべく応えるようにしています。眼鏡を買って行かれる方は、価格も高価なので60歳代以上の方が多いですね。けれども、40代から50代の方にも掛けて頂きたい眼鏡もたくさん作っていますよ。材料も高いけど、機械を使わず全部手作りの工芸品なので、どうしても高くなってしまいますが、ぜひ手に取って頂ければと思います。一昨年頃からは、体験教室を開催しています。修学旅行や課外授業で、全国から学生さんが来られるようになりました。下ごしらえをしておいて、糸鋸で切ってもらったり磨いてもらったり、2時間程でできる簡単なストラップなどを作ってもらっています。

田中淳功さん

材料であるタイマイ(ウミガメの一種)の甲羅。

ハートをモチーフとしたペンダント。デザインさえあれば、どのような形でも作れるとのこと。
べっ甲とは

べっ甲は、ポルトガルから中国を通って香港辺りから長崎に伝わって来たそうです。日本のべっ甲はおおよそ長崎から来ていて、江戸べっ甲は伝統工芸として東京都に認定されてはいますけれど、長崎べっ甲との違いはなく、材料も同じで仕事自体もほとんど変わっていないんです。昔は大阪にも職人がいたんですけども、今は大分少なくなりましたね。べっ甲には、タイマイというウミガメの一種だけを使用しますが、べっ甲は漢字では鼈(すっぽん)甲と書きます。江戸時代には、べっ甲を使ってはいけなかったから、紛い(まがい)物のすっぽんという態でやっていたそうですよ。
べっ甲の魅力とは

べっ甲細工物というと、年配の方向けといったイメージが強いのですが、若い人にぜひ着けてもらいたいと思って作っています。べっ甲の縁の眼鏡は、掛け心地も違って良いですよ。1本買うと、必ず2本目、3本目となります。べっ甲の耳かきも、使っているうちに自分の形に馴染んできます。べっ甲は天然素材なので、暖かみがあるというのかなあ。模様も同じものはひとつもないですからね。手入れをしていれば長く保つので、ピン、帯留めなどデザインの流行廃りがないものは、ご自身が使って、後はお孫さんへという方も多いですよ。