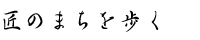看板彫刻とは

坂井さんが手掛けた浅草 鷲(おおとり)神社の扁額
看板彫刻の魅力とは

看板彫刻師として
職人になるきっかけをお聞かせ下さい。
なにしろ学校が嫌いで、15歳から中学を卒業して職人の道に入っちゃった方がいいと思ってさ。だけど親掛かりの時は、皆遊ぶじゃない。ズルをして見えるところだけ格好良く仕事をしていましたからね。親は分かっているんだろうけどね。だから19歳の時に父親(親方)が亡くなってしまった時には困ってしまってね。仕事できないんだもの。作業の仕方は分かっていても、そんなものできないじゃないですか。だから徹夜をして作業してましたよ。その頃は、忙しかったからね。
四代目になられる息子さんは、別の親方の元で修行されたとお聞きしまたが、それはなぜですか。

製作工程について その1
製作工程についてお聞かせ下さい。
看板を作る作業は、元々分業だったんですよ。文字書き師、彫り師、塗り師などとね。だけど今ではそれだけでは食べていけない上に、最近ではコンピュータを使って簡単に出来ちゃうじゃないですか。ウチでもお客さんが持ってくる原稿のほとんどがコンピュータで作成されたデータです。だから今では、本当にまれですが、自身で塗りまでの作業をすることもありますよ。今では看板屋で漆を専門として塗ってくれる職人の方は一人しかいないんでね。だからこの方がいなくなってしまったら、看板屋は、自身で塗りまでの作業をやらなくてはならないでしょうね。
元の原稿をデザインをされることもあるのですか。

製作工程について その2
今の作業はどのような工程ですか。

彫りの技法について
彫り方についてお聞かせ下さい。
墨文字が浮き出て立体的に見えように彫るのが『かまぼこ彫り(額彫り)』。その他に石屋さんが墓石に彫るような丸く文字を彫る『石屋彫り』、平らに彫る『地すき』、周りから彫って立体感を出す『篆刻(てんこく)』、溝をV字型になるように彫る『薬研(やげん)彫り』が主な彫り方です。篆刻などは素人さんでも彫れるんですが、彫り下げるという作業は、素人さんにはなかなかできないんだよね。
彫り方によって道具を使い分けるのですか。
作業の大半は、看板刀1本で彫り上げていますね。大きな看板から小さな招き札、ストラップ等の文字までは、基本的に1本の看板刀で作業しています。大変大きな看板では、三角刀という大きな鑿(のみ)を使って木槌で叩いて彫り上げています。
東京と関西では、どのような違いがあるんでしょうか。

形として後世に残るということ
製作されたものが後世まで残ることについては、いかがお考えですか。
形として後世に残ることは、うれしいことでね。例えば、お客さんに納品してから何十年か経って、何かの折にその場所に行って、私の息子や孫が私や先代の仕事を見た時に、あれは親父や祖父が彫った物だとか分かれば、それなりのもんじゃないですか。私の父親(親方)が残したもので思い出深いと言えば、岩手県の盛岡にある八幡様に東京の方が複数人で寄贈された額があるんですが、以前にそこにたまたま行った際に、親父が彫ったような仕事だなぁと思いながら見ていたら偶然にも親父の名前を発見したことがありました。年代を逆算してみると、独立してすぐに手掛けた仕事だったんですね。だから実際の物を見ると親父が頭の中で浮かんできて、今の自分の歳と比較しながらその仕事ぶりに思いを馳せることもありましたよ。このように父親の仕事ぶりが今でも形として存在し、後世にまで伝えられている看板って魅力的じゃないですか。自分が思いを込めて彫り上げた仕事が形として残り、使ってもらえている風景を見ることは、この仕事をしている上での楽しみでもあり、嬉しいことなんだよね。

坂井保之さん

左)坂井さんの屋号である『福善堂』の招木看板
右)題字 橘右之吉氏

純金で箔押した『鎮』の文字
看板彫刻とは

坂井さんが手掛けた浅草 鷲(おおとり)神社の扁額
看板は、扁額(へんがく)と呼ばれ、古代中国の宮廷や廟祠などにその名称を明記した木札を掛けたことに始まります。日本には飛鳥時代に宮殿仏寺に伝来したとされます。江戸時代になってからは、特に城下町などに店舗を構えた商人や職人が屋号や商品などを広告する手段として用いられ、様々な趣向が凝らされた看板が多く製作されてきました。
看板彫刻の魅力とは

我々の仕事は、形として後世に残るから良いんだよね。逆に残るから「怖い」という事もあるけど。最近では、出産祝いの『招木札』に誕生日や体重などの情報も入れて欲しいと注文されるお客さんが増えているんですが、3、40年も経てば、その子の成長と共に木札も歴史と思い出が詰まった物になっていくでしょう。それお客さんの喜ぶ姿を想像しながら手作業し納品し純粋に喜んでもらえることが好きで、この仕事を続けています