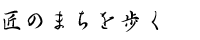錺(かざり)とは

錺師のやりがいとは
難しいものを頼まれた時の喜びね。どうやってやろうかって。半分苦しみかもしれませんけど、出来た時は嬉しいね。お客さんからヒントを貰って、私が考案して製法特許を取ろうとしたものは幾つもありますね。
仕事について

錺(かざり)師になるまで
錺師になられたきっかけを教えて下さい。
戦後すぐ(昭和26年)に中学校を卒業したでしょう。で、「学問より腕に職だ」という時代でしたからね。親父は「高校くらい行け」って言ってたんだけど。ちょうど岐阜県にある実家の田植えを手伝いに来た人が「東京で人を欲しがってるから行かないか」って。それで二つ返事で東京へ出てきたの。「職人になろう」と思って。修業は10年。それから2年くらいあちこちで修行して独立しました。それから、トントン拍子に忙しくてね。35、6から55才までは朝の7時から19時くらいまで仕事をやってました。四十肩も4回やった。寝られないの、痛くて。一番長い時は半年以上ありましたね。
現在、錺師の方はどの程度いらっしゃるのですか。
東京には5人か7人程度でしょうか。横の繋がりがないんだよ。関西では昔は50人くらいいたんだけど、今は半分くらいじゃないですか。見学に出掛けても、京都の町屋はうなぎの寝床でしょ。入口で話しして、それでストップ。技は見せてくれない。それに関西の場合は分業だから、截る(切る)人、模様を彫る人、組む人、皆違う。職人が、なかなか独立できないように考えてある。薬の調合は、秘伝で長男にしか教えないんだよね。
作品について
製作工程を教えて下さい。

材質について教えて下さい。
家紋は、財産家が金や銀で作ることはありますね。お寺さんや神社は、銅と真鍮が多いね。鍍金(めっき)を掛けて使う。銅の方が柔らかいから、模様彫るにしても曲げるにしても楽なの。真鍮は固いですね。神輿は真鍮(しんちゅう)しか使わないんですよ。銅を使うと出来上がった時に黒くなるから。煙管(きせる)も真鍮で出来ています。ロジウム(白金)で鍍金(めっき)をしています。艶があるでしょ。銀はもうちょっとくすんでますから。それにロジウムやクロムは剥げません。今はロジウムが主流になって来てるんじゃないですか。クロムはすごく高いんですよ、精製に使った水を捨てるにもお金が掛かり、金も溶かす時には煙が出るんですよ。だから鍍金屋も、最近は自分では溶かさなくなってきた。市販金っていう加工金しか使ってない。だから色も違ってきちゃいました。
文様について教えて下さい。

道具について
お使いの道具について教えて下さい。



川島利之さん


錺(かざり)とは

金属で作られたかんざし、金具などの細かな装飾品を「錺(かざり)」と言います。昔は提灯かざりや煙管(きせる)作りを手掛ける職人を「かざり師」と称しました。現在は神社やお寺の金物作りの職人には「錺師」という漢字を用いています。一方、三月人形や五月人形などのの金物作りを手掛けている職人には「飾師」という漢字が用いられます。
錺師のやりがいとは
難しいものを頼まれた時の喜びね。どうやってやろうかって。半分苦しみかもしれませんけど、出来た時は嬉しいね。お客さんからヒントを貰って、私が考案して製法特許を取ろうとしたものは幾つもありますね。
仕事について

最も多い仕事は、お寺の家紋ですね。神紋とか、本山の紋だとも言いますわね。末社やそのお寺の紋もあります。寺によっては2、3個違う紋がついているところもありますよ。篤志家が自身の紋を寄付する場合もあります。位牌や仏壇の金物も作ったりします。普通の位牌じゃなくて、少し上等の位牌を銀で作ったりしますね。菩提寺(檀那寺)が新築された時は、入口の金物を作って上げたりもしました。去年の暮れから灯篭30台の仕事を抱えて忙しかった。今、神田明神にずらっと並んでいる灯篭は平成16年から始めて、全部で55台を作りました。