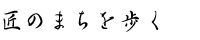江戸手描提灯とは

山田さんにとって江戸手描提灯とは

江戸手描提灯職人になるまで
江戸手描提灯職人になられたきっかけを教えてください。

修行はどのようにされていたのですか。
浅草の提灯屋さんに名人と言われている方がおられて、そこに通って勉強させて頂いたり、近所に櫻井さんという東京提灯業組合の方がいらっしゃいまして、そちらに習いに行ったりして修行をしました。私たちの組合の中にも提灯研究会という、いわゆる提灯の文字や描き方を学ぶ勉強会がありまして、私が始めたのが20歳頃だったのですけれども、先輩方の皆さんに大変良く指導してもらって、色々な事を教えて頂きました。
他は、私が江戸手描提灯を継ぐ上で、提灯以外の文字も勉強したいという思いがありましたので、歌舞伎の勘亭流(歌舞伎の看板、番付などで用いられる書体)という文字だったりとか、落語の寄席文字(落語の看板、めくり等で用いられる書体)などを勉強して、今もまだ通っています。書道教室などにも行った方が良いと言われて、そのような所でも勉強をしています。
独立されたのは何歳の頃でしょうか。
21歳の時ですね。とにかく平面の紙に描くのと、このような形に作られてる提灯に描くのは全然違いますから「慣れて覚えろ」「怖がらずに描け」というように初めの頃は教えられました。提灯の仕事というのは代々やっていましたから仕事はあったのですが、最初の頃は時間を掛けて自分のペースでやっていました。初めはやっぱりひとつひとつのものに相当な時間を掛けていましたね。
江戸手描提灯の仕事について
提灯への描画と製作は分業でやってらっしゃると聞きましたが。
昔は地張(じばり)と言って、私の所でも提灯の紙から貼って描いていました。ただそういう時代には提灯の種類も少なくて、また今のように時代の流れが早くもないので製作も可能だったんだと思いますが、今はもう完全に分業になりました。
提灯はどのような所に納めていらっしゃるのですか。
祭事を中心にしていますが、飲食店の看板代わりに使われる事も大変多くあります。提灯は縁起物として使われていましたから、今でも結婚式などのお祝い事や出産祝いのプレゼントとか、新築祝いに差し上げたりするお客さんがいます。また、個人的に自分の趣味としてインテリア代わりに飾られる方も多くおられます。
今でも居酒屋さんなどでも、赤提灯を見かけますね。
ええ、ありますね。これは昔の居酒屋さんでも、提灯はろうそくを用いた照明器具として使われていたのですが、その当時は白い提灯に黒い文字が描かれたのが一般的でした。そこで、あるお店があまり商売が上手くいかず、どうにか目立たせて繁盛させたいということで、提灯を赤く塗って出したところ、大変繁盛したようです。それで江戸時代に赤提灯が広まったと聞いています。そういうのもあって、日本人の心に赤提灯が残ってるんでしょうね。

山崎屋さんは初代から何年程続いておられるのでしょうか。
おおよそ300年程ですね。江戸時代から続いております。私の父もこの提灯の仕事をやっていましたが、合わずに辞めてしまいました。もう父は亡くなりましたが、元々このような提灯屋の息子として生まれましたので、サラリーマンで仕事もしてましたが、最後は提灯の問屋さんに勤めていました。父は多分提灯が好きだったんですね、字を描くのも絵を描くの好きでしたので。
江戸手描提灯について
文字の書体に決まり事はあるのでしょうか。
江戸手描提灯職人の間で、いわゆる何々流のような流派は無いのですが、私たちが描いている、このような文字は一般的には「江戸文字」と呼ばれています。提灯屋さんは家業で継がれる方がほとんどですから、その家であれば、お父さんから「こういうふうに描きなさい」というように教えられる事が多いのですね。そうすると、それぞれの提灯屋さんの雰囲気が出ます。ですから、街中に飾られている提灯を見ると、きっとあの提灯屋さんが描いたんだなと大体分かりますね。
江戸手描提灯の歴史についてお教えください。
提灯は、元は室町時代に中国から渡来したものです。日本では、江戸時代に照明器具として発達し広まりました。提灯は定義がありまして、基本的には小さく畳めてろうそくを立てられる、いわゆる照明器具を言います。今では、居酒屋さんや飲食店で使われるものは、ろうそくを立てないものも多くあるのですが、基本的には、ろうそくを立てて畳む事が出来るものを提灯と言います。昔も祭事で使われていましたが、次第に用途が広がって、大企業さんのイベントなどでも使って頂くようになってきましたし、個人でプレゼントなんかに買われるお客さんも多くなりました。ですので、昔ながらの提灯の描き方があるんですけど、英語で描いてくれという方もいらっしゃったりするので、そういうときは現代にあったデザインで描いたりしますね。
地域によってデザインは異なっているのでしょうか。
一般の方では分からないのですが、デザインや形、大きさも違いますね。特に文字に関しては、江戸文字という名称が残っているように、昔からその伝統があったと思いますし、今こうして受け継がれているのも、昔から私たちの先輩は文字に関してすごく勉強されてたと思うんですね。そのようにして江戸文字は大切にされてきたんだと思います。
例えば、「千社札」と言って、神社仏閣に貼ってある札がありますね、あれはいわゆる江戸時代の名刺交換や神社仏閣の参拝祈念などとして使われていて、そこに江戸文字と呼ばれる書体で自分の名前や屋号などを摺っていました。昔の人は何日も掛けて関西や東北の方に行っていましたので、その時代は遠くの神社仏閣に行くのは一生のうちに一度だったでしょうから、千社札を「ここまで無事に来れました」という証として貼ったのですね。地方の神社仏閣に貼られてる昔の千社札を見ると、あちらこちらに江戸から地方に参られた記録があります。でも逆に東京の神社仏閣に行っても、あまり地方の人の千社札は見掛けません。という事は、江戸時代には、江戸やその近郊で千社札や、江戸文字の文化が人気だった事が分かります。文字については、江戸はこのような事に大変こだわりがあったのではと思われますね。
また、やはり昔の先輩方の文字を見るとすごいですね。その時代は、私たちのように幼い頃から鉛筆、ボールペンを使ってという世界ではなく、生まれたときから筆を持っていたでしょうから、やはり違いますね。だから先輩方にはどんなにやっても一生敵わないと思います。
初期の提灯は比較的シンプルだったのでしょうか。

初期に用いられた懐提灯
製造工程について
江戸手描提灯の製造工程について教えて下さい。

その上に文字や絵を描いていくのですね。

このような文字ひとつにしても、職人さんの個性が出るのですね。
個性が出てきますね。江戸文字ひとつにしても、大変太く力強く描かれる方もおりますし、女性らしく細身で描かれる方もおりますし、まるで定規で描いたように縦も横も全部揃っている図形のような字を描く方もおられます。この漢字の「三」にしても、ただ横線を描くだけではつまらないので、少し曲線をつけたりします。例えば大きな筆でこの字を書いたとしたら、どんな形になるだろうかと考えながら描くことで、文字に個性が出るんですね。そして、提灯はろうそくを中に入れて使うので、基本的には提灯の文字は、かすれや透けたりする事を嫌います。けれども、わざとかすれを出す表現もあります。今製作している三社祭の提灯の文字の場合は、祭事なのでかすれを残す事で勢いを表現しています。
特に技巧を必要とするのは、どのような所でしょうか。
提灯は高い所に掛けますから、大体は下から見られます。職人さんによっても少し違いますが、縦書きの場合、提灯の下側の文字はすこし間が詰まります。上側が仮に4コマ空くのなら、下は3コマ空けたりします。そして一番難しいのが、提灯は地球儀のように紙が縦向きに貼られて作られているので、紙の継ぎ目に沿って文字を描いていくと、下の方の文字の幅が小さくなっちゃうんですね。つまり、もし仮に「雷門」の「門」の字を紙の継ぎ目を頼りにして描くと、門の字が下に狭まってしまうんです。ですので、提灯の下の方は継ぎ目に逆らって、幅が広がるように描きます。そうすることで、下から提灯を見上げた際に縦書きの文字が真っ直ぐに見えるようになります。
道具について
道具はどのようなものを使われているのでしょうか。

職人としてのこだわり
職人としての矜持とは何ですか。


山田記央さん



江戸手描提灯とは

日本における提灯の使用は室町時代に始まると言われており、江戸時代には照明器具として庶民に広く普及しています。それまで提灯製造業と一体化していた文字描き業が分業したのは明治時代であると言われています。明確に視認できるような江戸文字をきりりと描く表現が、江戸手描提灯の特徴です。
山田さんにとって江戸手描提灯とは

家紋でも何千種類もありますし、書体も20種類くらいあるんですね。この仕事というのは、勉強していったら一生あっても足りないくらいなんです。最初始める前までは、そんなに深く考えていませんでした。やってみて、これは大変だなと感じましたね。やってもやっても、本当に時間が足りない。だから、書法とか描き方とか江戸文字とか、昔の先輩方が多くのものを残してくれましたので、私たち世代も何か残さなきゃならない、新しいものも残したいなという気持ちはありますね。