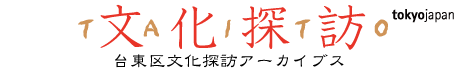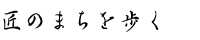江戸袋物とは

恩賜の煙草入れのエピソード
初代の頃に、満州事変(昭和6年(1931))の際に出征する兵隊さんのために、15万個の恩賜(おんし)の煙草入れを幾年か掛けて納めました。当時東京には15軒ほどの煙草入職人さんがいましたから、1軒あたり1万個を請け負ったわけですね。柳橋に昔マルエム松崎というバッグ屋さんがありましたが、そこを介して三越デパートから宮内庁に納めたという事です。

江戸袋物師になるまで、その仕事
江戸袋物師になられたきっかけをお話しください。

お仕事の内容について教えてください。
袋物の工程は、裁断、コバ漉き、縫製、仕上げですが、うちでは大量には作らないし、結構小さなものが多いですから、大体最初から最後まで一貫生産しています。リメイクもやっています。例えば使われていた半纏を用いて作ったり、手ぬぐいから作ったりというのもあります。形見の帯からお財布を作ってもらいたいとか、それを形見分けにしたいというような注文もありますね。
江戸袋物について
どのような製品を作られているのでしょうか。
江戸期に使われていた袋物を研究して製造しています。元々は私の所は煙草入れの職人だったのですが、巾着袋とか合切袋というような提げ袋などの、要は江戸のイメージが醸し出せるようなものを選んで作っています。
素材はどのようなものを使用されているのでしょうか。
主に牛革ですが、柄の入った鹿革なども使っています。柄が入ると、やはり江戸の雰囲気が出ます。裂地も使います。革以外でも、生地として加工できるものなら何でも使いますね。
昔ながらの袋物に加えて、新しいデザインの袋物も作られるのでしょうか。
袋物は中に入れるものが変わっていけば、それに対応して入れる袋物を作ろうっていう気になるわけですよ。今タブレットが出てるので、タブレットのケースを作ってみようかなと思っています。要は中身次第で袋物も変わっていくわけですよね。
製造技術について
詳しい作業工程を教えてください。
代表的な煙草入れですと、例えば革を裁断してから折り曲がるところは薄くしないと加工しにくいので、コバ漉きといって機械でヘリを薄く漉きます。それで折り曲げやすくなる。その作業の後に裏打ちをします。中にボール芯などの裏材料を入れるのですが、この工程の後に裁断して組み立てていきます。その後はミシン掛け、縫製の工程を経て、最後に木型に入れて仕上げます。
煙草入れの木型についてお話しください。

技が必要とされる工程はどこでしょうか。
やはりこの丸みですかね。革だと部分で伸びるので丸みが出易い。裂地だと丸みが出ても革ほどではありません。煙草入れは貼り合わせだけの部分があるので、よく付くように接着剤も選んで使っています。接着剤にも、サイビノール、ボンド、ゴムのりとありますが、作業上分けて使った方がどうしても便利です。一種類の糊だけではできません。
道具について
使われている道具についてお話しください。

例えば角をこう寄せるっていう、そういうために、袋物の職人さんは寄せねんを使っていますね。結構メインな道具ですね。他にはいつも使う革の裁ち包丁。革に型紙をあてて裁つための道具です。ローラーねんも仕上げるときに結構使いますけど、貼り付けたところをよく付ける時に使うと便利ですね。昔は主に金槌を使ってたんですが、ローラーねんの方が付ける場合に均等に力が行き渡りますから、重宝しています。
昔と今で道具の違いはあるでしょうか。
油圧の裁断機などは便利ですが、昔はありませんでした。そのため、火造(ひづくり)といって、焼き入れた刃物の型を使って木槌で叩いて抜いていました。またミシンは比較的早く入ってきましたが、私が子どもの頃には盛んに使っていました。ミシンは、比較的古い道具だと思います。
職人としてのこだわりについて
江戸袋物へのこだわりについてお聞かせください。

技術的なこだわりは、例えば縫製でもミシン目は絶対曲がらないように心掛けています。少しでも曲がると気分が悪くなっちゃいますからね。そのあたりに特にこだわっていますね。
職人としての矜持についてお聞かせください。

この前も、財布の裏地に正絹の生地があったのですが、普通に裁断して作ろうとすると、ぼろぼろと解(ほつ)れてしまう。それで、どうしようかと思った時に、生地屋さんにはほつれどめ加工という方法があるという記憶があったので、そうだったと思ってスプレー糊を試しにかけてみたら、ほつれが止まりました。ああ、これはしめたと思いました。このように様々なところから工夫が生まれて、しめたと思った時は面白いですね。

藤井直行さん

オーダーで製作した煙草入れ

合切袋。一切合切なんでも入れることから、その名が付いた。
江戸袋物とは

現代の財布やポーチ、バッグなどにあたり、物を入れるための袋状の入れ物を総称して袋物と呼んでいました。紙入れ、合切袋、胴乱など袋物の種類は多岐に渡りますが、江戸では特に煙草入れが町人の装飾品としてもてはやされ、通人はこぞって洒落た煙草入れを持ったと言われています。
恩賜の煙草入れのエピソード
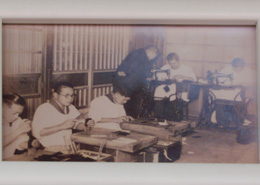
初代の頃の作業風景(藤井直行さん提供)
初代の頃に、満州事変(昭和6年(1931))の際に出征する兵隊さんのために、15万個の恩賜(おんし)の煙草入れを幾年か掛けて納めました。当時東京には15軒ほどの煙草入職人さんがいましたから、1軒あたり1万個を請け負ったわけですね。柳橋に昔マルエム松崎というバッグ屋さんがありましたが、そこを介して三越デパートから宮内庁に納めたという事です。