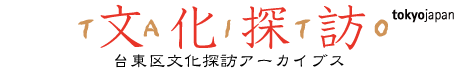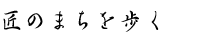東京銀器とは

伝統工芸一家として
うちは伝統工芸一家です。この道に入ったからにはということで一生懸命やっています。私の家系には、銀器製作では著名な平田禅之丞という人がいます。ここから系図を辿って、私で11代目になります。

銀師(しろがねし)として
職人の道に入られたきっかけをお聞かせください。
親父がやっていたからそのまま継いだという感じです。職人の家なのでこの仕事ばかりでしたから、小さい頃からずっと父が仕事している側で遊んでいました。本格的に修行を始めたのは、中学を卒業してからですね。子供の頃から大体のやり方は分かっていましたが、入ったらもうとにもかくにも下積みでした。まずは外注さんの所へのお使いから始めたわけです。昔は自動車などありませんから自転車で一日中走り回っていました。
この仕事ははどの程度の年数携わられていますか。
16歳からやっています。現在は68歳ですから、かれこれ52年程ですね。
昔と仕事の内容は変わっていますか。
時代によってずいぶん変わりました。私が修行していた当時は、やかんや急須などが主体でした。それから後には、日本では大ゴルフブームがありましたから、ゴルフの優勝カップが増えました。明けても暮れても365日、休みなしに作っていました。
やかんが駄目になった理由は、電気ポットやペットボトルなどが普及したからです。やかんでわざわざお湯を沸かす必要はありませんからね。けれども、やかんで沸かしたお湯の方がおいしいですね。鉄に比べて銀器は熱伝導が良いので早く沸きます。真鍮のやかんなど色々ありますけれども、銀器は特においしく飲めますね。
東京銀器について
銀器製造でもさらに新しい技法は生まれていますか。

江戸時代と今が違うところは、多少機械化されているところでしょうか。手で叩いて形作るのも良いのですが、機械を使ったへら絞りという技法もありますから、昔とはそのあたりが違いますね。
(へら絞り加工で使用するへら棒と木型)
東京銀器と他の地域との違いは何でしょうか。
東京は、地域としては最も華やかですね。台東区、文京区、荒川区の3つの地域に職人が集まりましたね。職人さんがいっぱい集まると、何が良いかと言うと、これを商う道具屋さんもここに来るわけです。色んな道具を買い集める時にここに来ればすぐに買えますから。この地域以外でも仕事はできますが、ここに住んだ方が良いじゃないかという訳です。
余談になりますが、金沢の金箔がありますね。江戸幕府は金を厳しく統制し、1グラムの金は大体1円玉程の重さですが、数平方メートル程の大きさまで伸びる。こんな技術は、金沢にしかありません。江戸ではすぐに地金が入手出来ますから、そのまま作ることが出来ます。そのように、産地の文化と歴史がちゃんと理に適ってるんですね。
銀器は、どの程度長持ちするのでしょうか。

昔のやかんを直してくれと来られますが、ちょっとこれは無理というのもあります。材質的な問題ではなくて、昔の品物で鏨(たがね)で模様が深く彫ってあるような場合は、厚みが大変薄くなっていて、使っているうちに切れてしまっているものがあります。これは直すことはできません。
銀器ならではの特長とは何でしょうか。
貴重な材料としての銀自体の価値とは別に、銀器が何で良いのかと言いますと、銀のコップでは味が変わります。まろやかになり、尖った感じが無くなって非常に口当たりが良くなります。酢などは、銀器で飲むと最高です。ガラスの器だと、そこまで味が出ない。本当に味が変わるのかと、保土ヶ谷にある味香り戦略研究所(現在は茅場町に移転)という所にお願いして、調べてもらいました。その結果は、間違いなく味が変わりますと数字にも出ました。そのお墨付きをもらいました。
製作工程について
製作工程についてお教えください。

伝統的な技法とは、どのようなものですか。




11代続く技を伝え継ぐということ
伝統工芸士としてのやりがいはどういう点でしょうか。

東京銀器とは

銀が硫化して色が変わる性質を活かし、中世ヨーロッパでは毒殺を防ぐために銀製の食器が重用されていました。このように銀器と人の生活は古くから密接な関係でしたが、日本でも江戸時代に現在の銀座である銀座役所において銀貨が鋳造されていたことや、経済発展し賑わった元禄文化では銀が装飾品として好まれたことなどから、東京が銀器の産地の中心として栄えることとなりました。
伝統工芸一家として

父である一男さんを師匠に、三男一女の一家で伝統工芸に取り組んでいる。
うちは伝統工芸一家です。この道に入ったからにはということで一生懸命やっています。私の家系には、銀器製作では著名な平田禅之丞という人がいます。ここから系図を辿って、私で11代目になります。