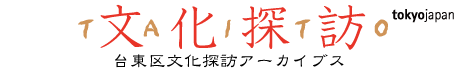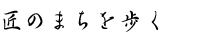江戸すだれとは

型抜きすだれについて

江戸すだれ職人として
職人の道を選ばれたきっかけをお聞かせください。
きっかけは特にありませんね。職人をするつもりはなかったんです。するつもりがないっていうより、やりたくなかったんですよ。朝から晩まで休みもなく作ってるじゃありませんか。ですから、大変そうに見える訳ですよ。大学を卒業して研究室に残って研究をしていましたが、その後に職人になりました。まぁ、小さい頃から手伝ったり、道具は触ったり、仕事の手伝いもしていましたが、専業になってからは25年程になりました。
田中製簾所さんの成り立ちについてお聞かせください。

江戸すだれについて
すだれはどのように発展したのでしょうか。
すだれの材料、例えば竹などの材料が採れる所には、竹を編む人たちが集まります。そういう所では竹を割って、それを使いすだれが作られました。他は、消費地にも集中します。例えば、今はもうありませんが、大阪や名古屋、そして京都が最も有名ですね。そういう所では作る人もいて、近在から材料を仕入れたりしていました。東京は竹があまり採れるような地域ではありませんから、郊外から仕入れています。江戸時代もそうだったと思います。
江戸すだれは、消費地として発展したケースでしょうか。
そうですね。昔は江戸では需要に応じて色んな所から物品を運びました。堀や川を利用して、物流を作ったんですね。その水路を使って舟で材料を運びました。ですから 神田など水路のすぐそばに職人が集中していました。すだれだけではなくて、他の職人さんにも言える話なのですが。飯田橋辺りには運んだ荷物を上げる河岸があって材木などを運んでいました。また市ヶ谷あたりも随分職人がいました。京橋には竹専用の河岸がありましたから、昔は竹河岸って地名だったそうです。最終的には隅田川が物流の中心になりましたから、台東区に最も多くの職人さんがいます。
(萬世御江戸絵図 : 国立国会図書館蔵)
すだれの種類にはどのようなものがあるのでしょうか。
基本的に、お客さんが求めるものは何でも作ります。大別して4つに分けています。まずは外掛すだれ、日よけや目隠し用に外に使うものです。次に内掛すだれ、神社仏閣に使う御簾(みす)もそうだし、座敷用のすだれもそうです。今では窓に掛けるようなものもあります。それから小物のすだれ、のり巻きを作るものとか、小さなものだと和菓子を載せる板重(ばんじゅう)などです。最近では食事マットやコースターも作成しています。最後は、これらを応用したものです。屏風の中にすだれを入れたものや、すだれを張った障子などがあります。それからお客さんが自分の仕事のここの部分に使いたいだとか求める場合があります。そういう特殊なすだれも結構あります。
どのような素材が使われているのでしょうか。
竹以外は、葦(よし)、御形(ごぎょう)、蒲(がま)、萩などです。向き不向きもありますから、これらを用途によって使い分けます。例えば、竹は割って竹ひごを作ります。竹だと削って形を整えることができます。海苔巻きだと、巻く方は平らにして、握る方はかまぼこ型にしたり、ナルトやちくわぶのギザギザしたものを作るには三角形の形の方が良いですね。他の素材では、姿形そのままの自然な状態で使うから、竹のような加工はしません。萩は色出ししたり、つや出ししたりできますが、細いものなので曲がってるんですね。それを火で矯(た)めてまっすぐにすると風合いが良くなる。ただ火で矯めたものですから雨が当たる所には駄目です。


製作工程について
すだれの製作工程は、形によって違うのですか。
すだれの製作工程には、2パターンあります。竹の場合は、必要な長さに切り、洗った後に乾かしたものを割って、目的に応じて加工します。他の素材の場合には、材料ごとに様々な加工の仕上げがあります。使える状態になっても、濃さや様々なくせがありますから、更に選別します。それでどんどん処分していきますが、最終段階になっても、まだ虫が食ってるものやシミがあるものがあります。また太さも一定ではないので選別して色味も分けたりします。これで材料の下ごしらえが出来ましたから、後は注文に合わせて編みます。
道具について教えて下さい。


糸の種類は、綿糸、絹糸、麻糸、化学繊維などがあります。糸によって特徴があり、例えば綿の糸は伸び縮みし、濡れると縮みます。化学繊維は摩擦に弱かったりします。ですから、糸も使い分けが必要です。
技術を活かして新しいものを
お客さんの変わった注文など、ありますか。
全く違った素材をすだれ状に編んでくれって頼まれたことがありましたね。金属やアクリルの板だったり、棒だったり、アルミのパイプだったり。真っ直ぐの状態の素材だったら編めますね。ただ工夫が必要で、素材が違うと重さが違ったり、従来使っている糸では編めないものもあります。


田中耕太朗さん

工房の2階はすだれを活用したショールームとなっています。

すだれは、古来より仕切り(しきり)や日よけとして親しまれてきました。
江戸すだれとは

すだれは古くは万葉集にも詠まれており、宮廷や寺社仏閣などで調度品として用いられてきました。江戸時代になり、地方から江戸に多くの人が集まるにつれて庶民の間にも広がり、必要にかられて多種多様な江戸すだれが生まれました。
型抜きすだれについて

一度普通に編んだすだれの、型抜きする部分に印をつけ、ほどいてから小刀で不要な部分を切り取ります。そして、また順序通りに編み直す事で、絵や文字の形が型抜きされます。紙に描いたものよりも丈夫で、多少の風雨でも壊れません。以前に駕籠(かご)につける家紋を抜いたすだれの修理依頼がありましたので、文字や家紋などを表現したものが古くから使われていたようです。