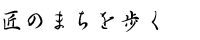木版画の持ち味

アトリエ店舗として

木版画彫刻師になるまで、そしてその仕事
木版画彫刻師になられたきっかけをお聞かせください。

長尾さんの仕事場では摺り師、彫り師と向かい合って作業を行っています。
ご家族内で彫りと摺りを分業されていますが、ご家族ならではの点はあるでしょうか。
やっぱり色々と言いやすいとは思いますね。ここをもう少し深くしてくれとか、細い所がうまく空かないので空けてくれとかあり、そういうのは家族でやってると便利ですね。
木版画について
主にどのようなものを彫られているのでしょうか。

木版画と印刷物の見分け方について教えてください。

浮世絵は古いものも現存していますが、版木も残っているのでしょうか。

版木はどのような種類の木材を使用されていますか。
桜材が一番多いですね。堅くて目が詰まっているので彫りやすいのです。そのため、このような細い線が彫れるんですね。たまに朴材(ホオノキ)も使いますが、朴材だと少し柔らかいため、細かい絵柄はなかなか彫れません。
版木は幾度も使えるものなのでしょうか。
結構使えますね。一度に1000枚とか摺ると潰れてしまいますが、200枚程度摺って、それが売り切れた頃にまた摺るようにやっていけば、使えますね。うちでも40年以上使ってる版もありますから。一度に1000枚摺ると、ふやけている所が刷毛でどんどん擦れて潰れてしまいますが、200枚程摺って、乾かしてしばらく置いて摺っていけば、そんなに潰れるもんじゃないですね。また洗うとそれで潰れたりするので、版木は色を変える時以外は洗わないですね。
一枚の浮世絵を彫るのにどの程度の工程や時間が掛かるのでしょうか。
色板も彫ると、色ごとに板を変えますから、全部の工程でやはり1ヶ月近くは掛かります。墨の輪郭線が、おおよそ1週間から10日程度掛かって、色板全部で同じくらいの日数が掛かりますから。

作品について
西洋画の模刻も和紙に摺るのですか。

かすれなどの技法は日本画でも使いますから、西洋画でも彫りの基本は同じです。摺りでは、ぼかしを何回も重ねることで、少し違った色になります。すべてこのようにして色を混ぜて使います。赤と青を混ぜて紫を作ったり、黄と藍を混ぜてグリーンを作ったりします。
木版画ならでの腕の見せどころとはどこでしょうか。

伝統工芸への想い
伝統工芸の実演会によく参加されていらっしゃいますね。


長尾 次朗さん

千社札の一種で名刺のように交換される色札には、粋なデザインも多い。

エドヴァルド・ムンク『叫び』、 西洋絵画の復刻も試みている。
木版画の持ち味

機械印刷では油性のインクを用いますが、手摺りの木版画は水性絵具なので、発色が大分違う気がしますね。発色が軽いというか透き通った感じが出ます。
アトリエ店舗として

台東区では、多くの工房がアトリエ店舗として一般公開をしています。(要問い合わせ) 私の工房も、配布している案内を見て訪れる方が多くいます。