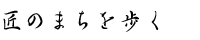銅器とは

煮色で仕上げられた急須
銅器は古来から日常的に用いられてきました。現在では、溶かした銅を型に流し込み成形する鋳金の手法を用いて仏像、梵鐘などを製造している高岡(富山県)と、金槌で叩いて成形する鍛金の手法を用いた鍋、やかんなどを製造している燕(新潟県)が産地として有名ですが、江戸銅器は後者の鎚起(ついき)銅器と呼ばれる部類に属しています。緑青を用いて赤錆色に染める煮色つけという独特の手法は、粋を好む江戸ならではの技と言えるでしょう。
屋号(銅銀銅器店)について

銅器職人として
職人になられたきっかけをお聞かせください。
きっかけは特にないんですけれども、小さい頃から祖父と父親の仕事を見ながら育ったものですから、仕事場が遊び場だったもので、もう自然にこの仕事に入りました。
18歳から修行をされて、一人前になられたのはいつ頃でしょうか。
一人前になったかどうかは分からないけれども、最近ですね。
先代と共にお仕事をされていた分、目標が高くなってしまうのでしょうか。

銅器について
現在は、どのようなものを作られていますか。

昔と作られるものが変わったでしょうか。
火鉢などに用いる炉の箱を「落とし」と言いますが、昔は火鉢の落としばかり作っていました。今も、たまに注文が来ますが、今はもう材料はベニヤばかりになりましたが、昔は桐の寸法での注文が来ていました。桐で作るから桐寸と言ったのですが、35cm角で角丸というように来ていました。手炙り(てあぶり)の火鉢というのは、昔はお料理屋さんに行くと一人に1つついたものでしたが、後にガスが出てきて無くなってしまいました。火鉢の箱は指物屋さんが作って、うちに注文を出してくれます。できるだけ応えていますが、こちらも手で作るからそうは数は出来ませんね。それは指物屋さんも心得ていますが、夜の12時になっても先方が待っていてもらえるものですから、こちらも一生懸命やらないと駄目だってうちの親父はいつも言っていました。
昔は、現在とは需要もずいぶん違ったのですね。
そうですね。まあガスが普及するまでは、鍋や落としなどが多くありました。一時期は、燗銅壺(かんどうこ)ばかりを作りました。酒の燗をつける銅で作ってニッケルメッキをした器です。鰻屋さんだったら鰻銅壺(うなぎどうこ)と言って、下に鰻焼く部分があるでしょ、その熱で横のタンクでお湯が沸くので酒の燗をつける。このような燗銅壺も機械製造のステンレス製に変わってしまいました。燗銅壺の製造を止めてからは、茶器や玉子焼き器などの細かな物の製造を始めたように思います。昔は夏場は燗銅壺の仕事も暇になりますから、そういう時期にこのような細かな物を手掛けていましたが、今ではこれが本格化したんじゃないかなと思います。
父の時代には、急須がずいぶん出ていました。それは漆器屋さんを介して新宿のデパートなどに納めていましたが、月に50個程は出ていました。建水(けんすい)と言う湯こぼし(茶道で茶碗を洗った湯を入れる容器)と急須のセットでした。ここにも急須ばかり作る職人さんは2人程いて、若い人たちはそればっかり年中叩いていました。これに漆を塗る職人さんが新潟から来ていました。もう高齢でしたが、年中漆ばかり塗っていました。

銅固有の特長について教えてください。
銅は、非常に熱の通りが早い金属です。ですから、お湯の沸きが非常に早く、熱が火の部分だけに集中しないで周囲にも行き渡ります。ステンレスなどでは、熱が広がらず火の部分だけ熱くなってしまいます。それで焦げてしまいます。銅は広く行き渡るので焦げません。玉子焼き器は銅ならではの商品ですね。ステンレスで作ってもこうはうまくは出来ませんから。他には、和菓子屋さんでは、小豆を煮るには必ず銅の鍋を使います。熱が均一に伝わって万遍なく煮上げることが出来るそうです。小豆の皮が弾けないと言うように、綺麗に煮上がるってことでしょうね。
台東区には、銅器職人さんは多くいらっしゃるのでしょうか。
昔はこのあたりにも3軒くらいはありましたが、今はいませんね。以前は、うちと同じように、火鉢に入れる銅壺を作っていた職人さんが何人かいました。一般に銅壺屋と呼ばれる商売ですよ。今、銅壺屋さんと呼ぶ人はもう80歳以上の方でしょうね。
このあたりは昔は鉄工所も多かったので、材料の調達が容易に出来たのでしょう。それから、芸者さんがいた待合茶屋が多くありましたから、需要もあったのでしょう。また、映画館通りでしたから、にぎやかでした。私が小学生の頃は、夜10時頃まで店を開けていました。それほどに人通りが多かった。映画と言えば浅草でしたが、今は1軒もありません。

製作工程について
製作工程についてお教えください。
製作する物によって違いますが、最初は、地金を寸法に合わせて裁断します。次に焠(な)まします。なますと言うのは、800度程で真っ赤に焼いて、地金を柔らかくします。この工程で、銀も銅もうっすら赤くなります。これを叩いて成形していきます。金槌で叩くと、柔らかかった地金が堅くなります。その後は、大抵の製品は槌目(つちめ)打ちだけで終わりますが、模様を入れる場合もあります。金槌で叩くことで、このような模様が付いていきます。

着色の工程についてお話しください。

硫化仕上げの小鍋
様々な色の仕上げ方があるのは、銅ならではですね。
最近では、光ってるものが銅だと思われますが、オレンジ色の製品は銅だと思わないみたいですね。作っている側としては困ってしまいます。何のために手間暇を掛けているのか分からなくなります。ですから、最近ではみんなピカピカにしてしまうのですね。ですが、座敷で使うのはね、ちょっと控えめ目のこういう色が落ち着いて良いと思います。
道具について
使用されている道具についてお話しください。
色々な大きさや形の金槌が数多くあります。打つ場所によって持ち替えます。これは鍋の底を打つ金槌です。鍋の中を打ちますから、長くなっています。

手仕事だからできること
手仕事の良さとはどこにあるのでしょうか。
機械では、趣がありませんよね。機械だと槌目打ちでも目が揃ってしまいます。やっぱり手でやったものの味わいは良いですね。このそれとない味わいが大事だと思います。
職人として、普段心掛けていることをお教えください。


星野 保さん

槌目打ちと呼ばれる技法は、手仕事の温かさを感じさせる。

二代目と二人掛かりで仕上げたやかん。
銅器とは

煮色で仕上げられた急須
銅器は古来から日常的に用いられてきました。現在では、溶かした銅を型に流し込み成形する鋳金の手法を用いて仏像、梵鐘などを製造している高岡(富山県)と、金槌で叩いて成形する鍛金の手法を用いた鍋、やかんなどを製造している燕(新潟県)が産地として有名ですが、江戸銅器は後者の鎚起(ついき)銅器と呼ばれる部類に属しています。緑青を用いて赤錆色に染める煮色つけという独特の手法は、粋を好む江戸ならではの技と言えるでしょう。
屋号(銅銀銅器店)について

銀器も一部は手掛けているのですが、銅銀の意味は祖父(初代)が銀次郎と言う名前だからです。銅壺屋(どうこや)の銀次郎ということで、銅銀と呼ばれました。それで銅銀を屋号にしていました。これだけでは、何だか分からないので、その下に銅器店と付けました。そしたら尚更分からなくなってしまいました。昔は、銀器も手掛けていると思ってくる方も結構いらっしゃいましたね。