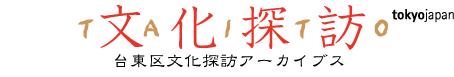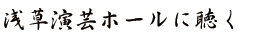浅草演芸ホール会長の松倉久幸さん
浅草演芸ホール会長の松倉久幸さんにお話しを伺いました。本インタビューは平成26年(2014)8月に取材したものです。
Q: 浅草六区と芸能の関連について、お話を伺えますか。
明治維新になって、浅草寺の寺領を七区に分けました。その際に浅草寺裏手の奥山にあった見世物小屋等が六区に移転しました。それから芝居小屋がここあそこと、にょきにょきと出てきたんですね。うちも明治時代に三友館という小屋を作りました。
Q: 当時は映画館というか、いわゆる活動写真(映画)が多かったのでしょうか。
明治時代にはまだまだ映画は少なくて、芝居小屋ばかりでしたね。その当時から浅草へお芝居をしたいと言って来る人が多くいました。今でも同じですが。全国でプロダクションと称する劇団が百幾つもあると言われるのですから、すごいですね。
Q: 浅草六区は、現在でも芝居が盛んなのでしょうか。
そうですね。台東区には演劇祭もあるし。そこを目指して応募に来る役者さん達も数多くいます。大正期に入って、無声映画が入ってきて、がらっと映画館になってしまいました。芝居をしていた所が全部映画館になってしまいました。それで弁士が誕生しましてね。当時は、この浅草六区だけで百何人と弁士がいました。
Q: 浅草寺境内に、徳川夢声さんの弁士塚がありますね。
弁士塚がありますね。徳川夢声さんとか、弁士は大勢いましたね。弁士にも売れる弁士と、売れない弁士がいましたからね。
Q: 徳川夢声さんもこちらに出演されていたのですか。
出てたんですよ。それから新東宝の大蔵貢さん(注)も、昔は弁士でしたから。その後に、昭和6年(1931)頃から映画が映像と音声が同期したトーキーになって、今度は弁士が失業してしまいましたね。その弁士の中から落語家や幇間になったり、浪曲師、講談師になったりと、変化していきました。ですから、弁士の力は大きかったですね。
注)大倉貢(おおくら みつぎ)
活動写真(映画)の弁士を経て、新東宝社長、大蔵映画社長を歴任する。浅草寺境内の弁士塚は、大蔵が日本映画5社に呼び掛けて昭和33年(1958)に建立しています。
Q: 会長さんはお若い時からこちらで勤められていたのですか。
そうですね、戦後間もなくからですが。まだ永井荷風さんが遊びに来ていた頃でしたから、古いですね。昭和26年(1951)に現在の小屋が完成しておりますので、その時からですね。まだ子供でしたが。私は昭和10年(1935)生まれですから、10代の頃ですね。いろんな弁士さん達が大勢浅草を目指して来ていましたね。
Q: 以前、永井荷風さんがお風呂に入ったエピソードを伺いましたが。
今でも当館の地下にお風呂はありますけどね。永井荷風さんは、踊り子さんと一緒にお風呂に入るんですよ。当時は、もう結構な歳ですからね、「俺は人畜無害だから、俺と入ったって平気だよ。」なんて言っていましたね。永井荷風さんは、また一風変わった人で、マスコミを一切受け付けなくてね。マスコミが「永井荷風先生が来ているという事ですが」と尋ねて来ても「俺、いねえって事にしておいてくれ」って。本人に会って留守だってんですからね、愉快な人でした。(右段に続く)
Q: 永井荷風さんはこの辺りをよく歩かれていたのでしょうか。
そうですね。この界隈をよく歩いていましたね。食事する所も、洋食はレストラン・アリゾナ、蕎麦は尾張屋と決まってましたからね。(下段に続く)

永井荷風が通っていた当時は、先代の松本さんのお父様の時代との事。

アメリカのアリゾナを模したウェスタンスタイルのレストラン。永井荷風が通っていた当時から大きく変わっていないとの事。
注)レストラン・アリゾナは、残念ながら先般閉店しました。
Q: 浅草演芸ホールの建物自体は、創建当時からどこか変わりましたか。
変わりないです。ただ変わったのは、増築して4階5階を造った事ですね。創建当時は3階建てでしたから。
Q: 現在の東洋館も、創建当時はなかったのでしょうか。
現在の東洋館も創建当時はありませんでした。昭和26年(1951)に浅草フランス座が開館した時にはなかったですね。それから上の階を増築して、それで寄席でもやろうじゃないかって、落語の定席を作ったんです。
Q: 当時の浅草フランス座の演し物は何でしたか。
最初は、ストリップショーですね。浅草フランス座というと、ストリップショーとお芝居の二本立てでした。その芝居から、渥美清さんや長門勇さん、そして萩本欽一さん等が育っていきました。(次ページに続く)

浅草演芸ホール会長の松倉久幸さん