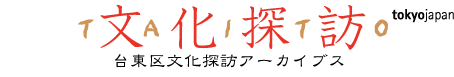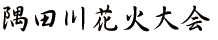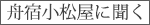隅田川花火大会
隅田川花火大会は、享保18年(1733)に飢饉やコレラにより亡くなった人々の鎮魂のために、将軍徳川吉宗が両国橋のたもとで水神祭を執り行い、花火を打ち上げた事に始まると言われています。明治維新や第二次大戦時には一時中断されたこともありましたが、「隅田川花火大会」と名称が改められた昭和53年(1978)から数えて、平成29年(2017)7月には40回目を迎えました。(隅田川、浅草、向島界隈)


町では、色とりどりの浴衣姿が艶やかさを競っています。
花火は江戸の華、今も夏の風物詩です。
かぎやー! たまやー!
享保17年(1732)、江戸は大飢饉とコレラの流行に見舞われました。時の八代将軍徳川吉宗は、大川(現隅田川)端で川施餓鬼(死者を供養する法会)を催しました。翌享保18年(1733)には、川施餓鬼と共に両国の川開きの日に水神祭を催して、花火を打ち上げました。しかし、この催しは、明治維新や第二次世界大戦時には一時途絶えました。また、昭和37年(1962)から昭和52年(1977)頃までの高度経済成長期には隅田川の水質汚染も甚だしく中断しましたが、水質改善や護岸整備により昭和53年(1978)には「隅田川花火大会」と改称され、今日まで続いています。
毎年7月末に開催される隅田川花火大会は、東京都内での花火大会の中でも、毎回100万人近くの人出の大会で、テレビ等の実況中継も行われています。隅田川に架かる桜橋から言問橋の間に設けられた第一会場と、駒形橋から厩橋の間に設けられた第二会場のふたつの会場で競って花火が打ち上げられ、花火コンクールが開催されます。昭和53年(1978)の再開から40回目を迎え、東京の夏の風物詩となっています。
ふたつの会場で打ち上げられる花火は競うように、艶やかな華を咲かせています。


遊覧船や屋形船も出て、ひと時の隅田川の涼風と共に花火を楽しんでいます。


隅田川花火大会
隅田川花火大会は、享保18年(1733)に飢饉やコレラにより亡くなった人々の鎮魂のために、将軍徳川吉宗が両国橋のたもとで水神祭を執り行い、花火を打ち上げた事に始まると言われています。明治維新や第二次大戦時には一時中断されたこともありましたが、「隅田川花火大会」と名称が改められた昭和53年(1978)から数えて、平成29年(2017)7月には40回目を迎えました。(隅田川、浅草、向島界隈)



町では、色とりどりの浴衣姿が艶やかさを競っています。