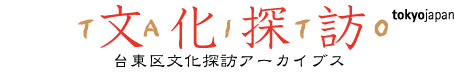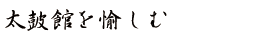宮本卯之助商店西浅草店
Q: 太鼓を浅草で作られるようになったきっかけについてお聞かせ下さい。
元は茨城県土浦の出身なんです。明治26年(1893)にここ浅草聖天町(現浅草6丁目)に店を開きました。この辺には、当時太鼓屋が6,7軒程ありました。
Q: 浅草猿若町が近いからでしょうか。
猿若三座ですね。それがあった事と、この辺には皮革産業が多かったためでしょう。当家の四代目の卯之助が、船で土浦から道具を積んで、ここに着きました。そして、その後に大正天皇の御大葬の儀のための雅楽器製造を拝命しました。浅草に店を開いて、程なくしての事でした。 (下段に続く)

Q: 後ろに展示してあるお店の写真に昭和5年頃とありますが、元々太鼓を中心に製作されていたのですか。
太鼓屋なので、太鼓ばかりでした。神輿製造は、昭和8年(1933)頃からです。その写真はここにはないのですが、昭和5年頃の写真に太鼓ばかりの山車のものがあります。この山車は、五代目が考えたらしいんです。それ以前の江戸の祭りというものは神輿が神社に一基だけ、ないしは三基ぐらいあって、あと各町は背の高い江戸型山車っていうのを曵いてたんですよ。それで例えば、神田祭とか山王祭とかは天下祭と言われていますが、江戸城に入城を許されたんです。要するに神田と日枝は江戸城の氏子範囲なんですよね。ですから四十ヶ町ずつが毎年のように江戸城の門を入って、山車がですよ、徳川の将軍に天覧というかな、上覧頂いたわけですね。
その時に城門の高さより山車が大きかったわけです。そのため、これを三層構造にして作り替えました。知恵ですね。入城すると、その上に人形が、例えば義経だとか天照大神等と色々ありますね、桃太郎だとか、そういうのを載せました。
それが明治の中頃になって、都内に電線が張り巡らされてしまいました。江戸時代はろうそくの時代ですが、電気の時代になったら背の高い江戸型山車が出せなくなってしまったため、止めましょうという発令が出たんです。それで、うちはこのような子供の曳太鼓を作り始めたんですね。それでやってたところが、神輿は日本中どこいっても神社だけにしかないんです。江戸というか東京の祭礼では、神輿は町会にはなかったのです、それが、大きな山車が出せなくなったので、氏子も神輿をという事で、町神輿が初めて出来ました。そのおかげで東京は町神輿だらけです。うちも最初は山車だけで、神輿は製造していませんでしたが、お客様から神輿も作ってくれないかという事で、神輿と太鼓、そして山車を製造するようになりました。
Q: 店頭に雅楽の楽器も並んでいますが、太鼓以外にも雅楽器も手がけているのですか。
雅楽は盛んに作っています。雅楽は、各神社さんが例大祭等の式典や結婚式の際に用いると、同じ式でも全然格式が違ってきます。普通の大太鼓でどんどんやるのと違ってこれをやると映えます。
Q: 電線の埋設化が進むと神輿も昔の様式を復活させるという話になるのでしょうか。
神輿が巨大化するという事はないですね。人力で担げる限界がありますから。神輿の場合は担げるのは四尺位まででしょうか。形はあまり変わってないです。むしろ担がれる方の体力の方が違ってきていますね。
現在の日本橋のコレド室町の裏に、福徳神社という神社が出来ました。元はビルの屋上にあった神社を降ろして、コレドの真後ろに祀られました。この神社の神輿もうちで作っています。その神社に合わせて、注文で特徴のある神輿を作っています。そういう町興しというのかな。神社が町興しというのも賛否あるでしょうが、ショッピングモールばかりで精神的な支柱がないような無機質な町になってしまいますから。 (右段に続く)
元は茨城県土浦の出身なんです。明治26年(1893)にここ浅草聖天町(現浅草6丁目)に店を開きました。この辺には、当時太鼓屋が6,7軒程ありました。
Q: 浅草猿若町が近いからでしょうか。
猿若三座ですね。それがあった事と、この辺には皮革産業が多かったためでしょう。当家の四代目の卯之助が、船で土浦から道具を積んで、ここに着きました。そして、その後に大正天皇の御大葬の儀のための雅楽器製造を拝命しました。浅草に店を開いて、程なくしての事でした。 (下段に続く)

Q: 後ろに展示してあるお店の写真に昭和5年頃とありますが、元々太鼓を中心に製作されていたのですか。
太鼓屋なので、太鼓ばかりでした。神輿製造は、昭和8年(1933)頃からです。その写真はここにはないのですが、昭和5年頃の写真に太鼓ばかりの山車のものがあります。この山車は、五代目が考えたらしいんです。それ以前の江戸の祭りというものは神輿が神社に一基だけ、ないしは三基ぐらいあって、あと各町は背の高い江戸型山車っていうのを曵いてたんですよ。それで例えば、神田祭とか山王祭とかは天下祭と言われていますが、江戸城に入城を許されたんです。要するに神田と日枝は江戸城の氏子範囲なんですよね。ですから四十ヶ町ずつが毎年のように江戸城の門を入って、山車がですよ、徳川の将軍に天覧というかな、上覧頂いたわけですね。
その時に城門の高さより山車が大きかったわけです。そのため、これを三層構造にして作り替えました。知恵ですね。入城すると、その上に人形が、例えば義経だとか天照大神等と色々ありますね、桃太郎だとか、そういうのを載せました。
それが明治の中頃になって、都内に電線が張り巡らされてしまいました。江戸時代はろうそくの時代ですが、電気の時代になったら背の高い江戸型山車が出せなくなってしまったため、止めましょうという発令が出たんです。それで、うちはこのような子供の曳太鼓を作り始めたんですね。それでやってたところが、神輿は日本中どこいっても神社だけにしかないんです。江戸というか東京の祭礼では、神輿は町会にはなかったのです、それが、大きな山車が出せなくなったので、氏子も神輿をという事で、町神輿が初めて出来ました。そのおかげで東京は町神輿だらけです。うちも最初は山車だけで、神輿は製造していませんでしたが、お客様から神輿も作ってくれないかという事で、神輿と太鼓、そして山車を製造するようになりました。
Q: 店頭に雅楽の楽器も並んでいますが、太鼓以外にも雅楽器も手がけているのですか。
雅楽は盛んに作っています。雅楽は、各神社さんが例大祭等の式典や結婚式の際に用いると、同じ式でも全然格式が違ってきます。普通の大太鼓でどんどんやるのと違ってこれをやると映えます。
Q: 電線の埋設化が進むと神輿も昔の様式を復活させるという話になるのでしょうか。
神輿が巨大化するという事はないですね。人力で担げる限界がありますから。神輿の場合は担げるのは四尺位まででしょうか。形はあまり変わってないです。むしろ担がれる方の体力の方が違ってきていますね。
現在の日本橋のコレド室町の裏に、福徳神社という神社が出来ました。元はビルの屋上にあった神社を降ろして、コレドの真後ろに祀られました。この神社の神輿もうちで作っています。その神社に合わせて、注文で特徴のある神輿を作っています。そういう町興しというのかな。神社が町興しというのも賛否あるでしょうが、ショッピングモールばかりで精神的な支柱がないような無機質な町になってしまいますから。 (右段に続く)
Q: 日本で製造される太鼓の需要はいかがでしょうか。
そうですね、今ちょうど50年程前から、組太鼓という表現が始まりました。それまでは要するに雅楽、能楽、歌舞伎、民俗芸能、里神楽等でも、太鼓は伴奏楽器だったのですが、太鼓だけを集めて演奏するという組太鼓というスタイルが起こりました。それがばっと拡がって今は日本のみならず、和太鼓として世界中に拡がっています。寿司等のブームと同じで、大変な勢いでアメリカでは、西海岸のサンフランシスコ、ロサンゼルス、サンノゼあたりの日本町を中心に2、300チームもあります。ヨーロッパもイギリスを中心にしてあります。そこを中心に、40年程前から盛んになってきたんですね。もちろん東海岸もボストン、ニューヨークあたりにもあるんですが、まあ西海岸が盛んですね。ヨーロッパでは、イギリスを中心にフランス等でも盛んになってきています。
Q: 演奏の形式やメソッドは日本と同じでしょうか。
同じです。要するに太鼓ってのは「ドン」という音と「カ」しかないですから。単純なんですね。それの組み合わせですから、そんなに突出した事は出来ないと思います。基本的にはその中でどういうふうに心地良いリズムを作っていくかという事ですから。そんなには変わらないですね。早いか遅いか、縁をどのくらい打つか、強さをどうするかという違いだけですね。
それでヨーロッパの方はどちらかというと、太鼓をアートとして捉えているところがあります。アメリカの方はホビーとして捉えているようです。
Q: 現在、太鼓人口というのでしょうか、どれ程なのでしょうか。
ちょっと計算出来ませんが、何万という数になるのではないですか。地域で活動する団体、趣味として楽しまれている方、プロの皆さん等、本当に沢山の方がおられます。日本の太鼓の特徴と言えば、一本のくりぬいた木に厚い革を貼ってるから、音がすごく良く出ます。ジャズドラムのセットよりも大きい音が出ます。それだけに太鼓の音を聞くと虜になってしまう人が多いですね。
Q: 海外から太鼓の発注はあるのですか。
バレルドラムと言われる樽を使っている所も多くあります。しかし、一昨年もスタンフォード大学さまに太鼓一式をお納めしたりと海外への発送も以前よりは増えました。
Q: 特注でユニークな形の太鼓を作られることはあるのでしょうか。
今ではメジャーになりましたが、担ぎ桶胴太鼓と言う肩から吊して打つ太鼓もあります。比較的、お求めやすいので、個人で購入されて練習される方が多いです。うちではスタジオも運営していますが、そのようなお客様をよくお見かけします。

そうですね、今ちょうど50年程前から、組太鼓という表現が始まりました。それまでは要するに雅楽、能楽、歌舞伎、民俗芸能、里神楽等でも、太鼓は伴奏楽器だったのですが、太鼓だけを集めて演奏するという組太鼓というスタイルが起こりました。それがばっと拡がって今は日本のみならず、和太鼓として世界中に拡がっています。寿司等のブームと同じで、大変な勢いでアメリカでは、西海岸のサンフランシスコ、ロサンゼルス、サンノゼあたりの日本町を中心に2、300チームもあります。ヨーロッパもイギリスを中心にしてあります。そこを中心に、40年程前から盛んになってきたんですね。もちろん東海岸もボストン、ニューヨークあたりにもあるんですが、まあ西海岸が盛んですね。ヨーロッパでは、イギリスを中心にフランス等でも盛んになってきています。
Q: 演奏の形式やメソッドは日本と同じでしょうか。
同じです。要するに太鼓ってのは「ドン」という音と「カ」しかないですから。単純なんですね。それの組み合わせですから、そんなに突出した事は出来ないと思います。基本的にはその中でどういうふうに心地良いリズムを作っていくかという事ですから。そんなには変わらないですね。早いか遅いか、縁をどのくらい打つか、強さをどうするかという違いだけですね。
それでヨーロッパの方はどちらかというと、太鼓をアートとして捉えているところがあります。アメリカの方はホビーとして捉えているようです。
Q: 現在、太鼓人口というのでしょうか、どれ程なのでしょうか。
ちょっと計算出来ませんが、何万という数になるのではないですか。地域で活動する団体、趣味として楽しまれている方、プロの皆さん等、本当に沢山の方がおられます。日本の太鼓の特徴と言えば、一本のくりぬいた木に厚い革を貼ってるから、音がすごく良く出ます。ジャズドラムのセットよりも大きい音が出ます。それだけに太鼓の音を聞くと虜になってしまう人が多いですね。
Q: 海外から太鼓の発注はあるのですか。
バレルドラムと言われる樽を使っている所も多くあります。しかし、一昨年もスタンフォード大学さまに太鼓一式をお納めしたりと海外への発送も以前よりは増えました。
Q: 特注でユニークな形の太鼓を作られることはあるのでしょうか。
今ではメジャーになりましたが、担ぎ桶胴太鼓と言う肩から吊して打つ太鼓もあります。比較的、お求めやすいので、個人で購入されて練習される方が多いです。うちではスタジオも運営していますが、そのようなお客様をよくお見かけします。


宮本卯之助商店西浅草店