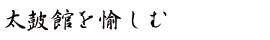宮本卯之助商店会長の宮本卯之助さんにお話しを伺いました。本インタビューは、平成26年(2014)9月に取材しました。
Q: 昭和39年(1964)開催の東京オリンピック開会式の大火焔太鼓について、お話しを伺えますか。
私はこの年の3月に大学を卒業して、一年間程修行というか、うちのお得意さんの所に住み込みで修行に行っていました。その年の秋の10月に東京オリンピックがありましたが、私は直接は携わっていなくて、六代目になる私の父が製作監修しました。父からはあまり詳しくは聞いていませんが、10月の開会式に間に合わせるために、相当徹夜してやったというふうに聞いています。ところが、これを作る前に、もう一回り小さい太鼓を製作していて、今でも一対あります。その知識というかノウハウがありましたので、これなら間に合うと思ったんじゃないですか。
Q: 当時作られた東京オリンピック開会式の太鼓はどちらにあるのでしょうか。相当大きなものですよね。
私どもの所にありますが、組み立てると高さは8m程もあります。この太鼓は、当時私どもが受注したのではなく、父が意気に燃えて作ってしまったんですね、それをオリンピックの組織委員会に提供したんです。それで使って頂いた後は、無用の長物に等しい状態で、10年程は倉庫に眠っていました。それで昭和60年(1985)頃かな、その間も雅楽団体は、宮内庁の楽部程度で、日本国内には数少なくて、NHKさん等が雅楽公演する際に一番使って頂きました。
最近では、英国のエディンバラ国際芸術祭、それとアムステルダムで開催されオランダ国際園芸博覧会フロリアード2012)と海外まで行きました。
それからサッカーの日韓ワールドカップの時にもこれを持って行ったように思います。ワールドカップをアジアで開催しようという事になって、韓国と共催という事になり、その際に何を催したら良いだろうかという事になって、雅楽が良いだろうという事で、ソウルと釜山にこれを持って行きました。日本では東京の国立劇場と大阪の文楽劇場(国立文楽劇場)と2ヶ所か、計4ヶ所で。楽師も韓国から来られて演奏されました。韓国の雅楽は日本とずいぶん違うのですが、互いに交代で演奏して交流したんですね。(右段に続く)
Q: 左右にそれぞれ太鼓が配置されていますが、どのように違うのですか。
舞楽には、左方舞と言って、中国系を源流とした赤系統の装束、飾りは龍、日照を頂いた仕様があり、一方は右方舞と言って朝鮮半島系を源流とした黄系統の装束、飾りは鳳凰、月照を頂いた仕様と異なっています。左方舞の時には2つ並んでいても、左方しか打ちません。右方舞の場合は、朝鮮、いわゆる高麗から伝わったと言われて右方を打ちます。
Q: 韓国や中国で雅楽に類するものはあるのでしょうか。
元々は中国から発祥したのでしょうが、現在は中国には一切ありません。韓国にはありますが、日本とは少し違います。ベトナムにも残っています。私も見に行きましたが、ベトナムは全く似て非なるものでした。けれども、ベトナムでは漢字で雅楽って書いています。
Q: ベトナムのどのあたりで演奏されていたのですか。国が運営しているのでしょうか。日本では、雅楽の演奏者は宮内庁以外にもいらっしゃいますか。
フエだったように思います。宮廷等ではなくて、何かのイベントでした。私も、わざわざ出掛けたのではなくて旅行の途中でたまたま遭遇しました。雅楽と書いてありましたから、ベトナムに雅楽があるというのは聞いてはいたんですが、見たら少し違っていました。演奏している方は地元の方でしたね。韓国は、国が運営していますが。日本では宮内庁が主に伝承していますが、奈良、平安時代からずっと続いています。現在では、民間団体もあります。東京にも日本雅楽会と小野雅楽会、東京楽所等がありますし、それから大阪には大阪楽所があります。楽という字に所と書いて「がくそう」と呼びます。それから京都には平安楽所、南都というのは奈良の事ですが南都楽所、九州にも筑紫楽所がありますね。

宮本卯之助商店西浅草店

宮本卯之助商店会長の宮本卯之助さん