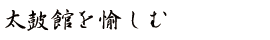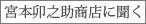宮本卯之助商店西浅草店4階にある太皷館は、会長の宮本卯之助さんが世界各地で収集した太鼓を身近に感じて頂きたいとの主旨から「実際に触れる・叩ける」博物館として昭和63年(1988)に開設されました。世界各国の約900点の太鼓、3000点を超える文献や視聴覚資料が収蔵され、世界においても貴重な博物館となっています。打つ楽しさや素晴らしさを伝える事を目的としています。
取材時には、展示室に200点から250点程の世界各地の太鼓が展示されていました。中央に日本の太鼓類、入り口より入って右手に中南米の太鼓、左手にアフリカの太鼓、正面奥に中東、ヨーロッパ、アジア圏の様々な表情を持った太鼓が展示されていました。展示品の解説にはシールが付されており、赤いシールの楽器には触れる事は出来ませんが、音譜マークが付されている楽器は実際に触れたり、叩いて演奏する事が出来ます。

太皷館(西浅草店4階)

世界の様々な太鼓や打楽器に触って、その音色を聞く事が出来ます。館内には、いつも楽しげな音が溢れています。海外からの来場者も数多く、浅草散策の合間に世界各国の様々な太鼓を楽しんでいます。

瓢箪太鼓(コートジボアール)
コートジボワールでは瓢箪を用いたり、カモシカの皮を張っています。演奏方法は、紐を首から前に下げて両手で打ちます。この太鼓も実際に叩く事が出来ます。

イプヘケ(アメリカ)
ハワイのフラダンスの伴奏に用いられるひょうたん太鼓
アンクルン(インドネシア)
竹筒を枠に組み込み、手で持ったり、腕にかけて振って鳴らす。
ガムラート(パプアニューギニア)
イアトルム族の割れ目太鼓
スリットドラムとも呼ばれていますが、木をくりぬいて作った割れ目を打って鳴らします。日本では、撥(ばち)を用いて叩く、いわゆる撥を振ると言いますが、ガラムートは突くようにして鳴らします。実際に使用する際は、下に板を置くため、もう少し響きがなめらかになります。装飾は、先祖の霊を模していると言われます。
ダホメの太鼓(ベナン)
婚礼に用いられる太鼓と言われています。現在のベナンの婚礼の儀式で使われている太鼓です。それぞれ男性器、女性器を施していて、夫婦和合や長命、子宝等の祈りが込められています。
セヌフォ族の太鼓(コートジボアール)
セヌフォ族の太鼓(コートジボアール)
太鼓によっては、性別や用途によって、形が異なるものがあります。例えば、セヌフォ族の太鼓では男性、女性の成人の儀礼に用いられるものですが、こちらは河馬(かば)の姿を模した太鼓(上)で、強い男性を意味しています。女性の方(下)は、頭上に荷物を抱え働いている姿になっています。
グンデル(インドネシア)
ガムラン音楽で用いられる青銅製の音盤を木撥(ばち)で打つ。
スタンピング・ドラム(パプアニューギニア)
エデ族の太鼓(ベトナム)
象の皮が用いられています。現地でも象の皮を用いたものは数少ないとの事ですが、その地域でも特別な権威のある家で作られたのではないかと言われています。日本では皮の毛を全て除去してしまいますが、海外では毛を残した太鼓もあります。
銅鼓(ミャンマー)
太鼓は、一般には胴に皮を張っていますが、中には例外もあり、皮の部分が金属でできたものもあります。これは「フロッグ・ドラム(銅鼓)」と呼ばれています。
建鼓・架鼓(中国)
左右の一対を建鼓(けんこ)、中央のものを架鼓(かこ)と言います。建鼓の鼓面に描かれた龍は5本の爪を持っています。この模様は中国、清王朝の皇帝と皇后にしか許されなかった模様なので、これもそのような場で実際に用いられていたのだろうと思われます。アジア圏では、皮の留めに鋲が多用されます。日本も含めて東アジアに共通する特徴です。