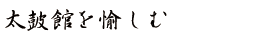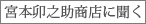宮本卯之助商店の企画広報室の郡山梢さん(左)と太皷館学芸員の飯田希美さん(右)に、案内頂きました。

長胴太鼓(ながどうたいこ、2尺、宮本卯之助商店西浅草店)
国産の欅(けやき)材の胴に牛皮が使われています。最もポピュラーな形で、神社仏閣、また組太鼓の演奏にも使われています。


愛媛県の祭りで使われる長胴太鼓です。太鼓の釻(かん)は一般的には2点ですが、愛媛県の祭りでは太い柱にくくり付けて使うため、4点付いています。


大平太鼓(鼓面:牛皮、胴:欅、宮本卯之助商店太皷館)
組太鼓としてグループで演奏する際などに使用される太鼓です。太鼓の胴の幅が短い所が特徴です。


締太鼓(宮本卯之助商店西浅草店)
お囃子などで用いられる太鼓。紐で締められている昔ながらの形の他、チューニングしやすいようにボルト締めのものもあります。

宮本卯之助商店西浅草店

様々な太鼓の数々(宮本卯之助商店西浅草店)

信州型桶胴太鼓(6.5寸、宮本卯之助商店西浅草店)
主に信州で使われています。刳り貫き(くりぬき)胴に皮を張り、紐で締められています。

屋根延神社型神輿(宮本卯之助商店西浅草店)

作人札
私どもで製作した神輿には「宮本重義作」と書した作人札が付いています。「重義」とは当社の社是で、義を重んずる、正しいことを行うという意味があります。
神輿は、神社や町によって形、意匠がそれぞれ異なります。デザインなど全てが決まってから1年程の製作期間を頂いています。小さな部材や金具のすべてを合わせると、約五千もの部品になります。二十職程の職人の手を経て製作されています。浅草神社の御本社神輿も手掛けさせて頂きました。

宮本卯之助商店の企画広報室の郡山梢さん(左)と太皷館学芸員の飯田希美さん(右)に、案内頂きました。

長胴太鼓(ながどうたいこ、2尺、宮本卯之助商店西浅草店)
国産の欅(けやき)材の胴に牛皮が使われています。最もポピュラーな形で、神社仏閣、また組太鼓の演奏にも使われています。


愛媛県の祭りで使われる長胴太鼓です。太鼓の釻(かん)は一般的には2点ですが、愛媛県の祭りでは太い柱にくくり付けて使うため、4点付いています。


大平太鼓(鼓面:牛皮、胴:欅、宮本卯之助商店太皷館)
組太鼓としてグループで演奏する際などに使用される太鼓です。太鼓の胴の幅が短い所が特徴です。


締太鼓(宮本卯之助商店西浅草店)
お囃子などで用いられる太鼓。紐で締められている昔ながらの形の他、チューニングしやすいようにボルト締めのものもあります。