
01. 川柳ゆかりの地(せんりゅうゆかりのち)
元浅草3-20-6 菊屋橋公園
柄井川柳(初代)は享保3年(1718)生まれ、通称を八右衛門、名を正通(まさみち)という。柄井家は祖父図書の代から浅草龍宝寺門前の名主を務めており、川柳も宝暦5年(1755)から龍宝寺門前の名主となった。その2年後、宝暦7年(1757)から前句付(まえくづけ)の点者(選者)として活躍している。寛政2年(1790)死去。墓は龍宝寺(天台宗、蔵前4丁目36番7号)にあり、都指定旧跡となっている。
前句付は出題された前句(七七の短句)に付句(五七五の長句)をつけるもので、川柳が点者を務める万句合(まんくあわせ)は広く人気を集めた。明和2年(1765)、川柳の選句集『誹風柳多留(はいふうやなぎだる)』初編の刊行を一つの契機として、付句が独立した文芸となっていった。この文芸は「川柳点」「狂句」などと呼ばれたが、明治中期から「川柳」の名称が用いられるようになった。個人の号名が文芸の呼称となるのは稀有のことである。
この地域で活躍した柄井川柳の偉業を記念するため、有志の運動により当公園には平成元年(1989)3月に柳が植樹され、平成4年(1992)4月には柄井川柳碑が建立された。

02. 孫三稲荷(まごぞういなり)
元浅草3-19-7
この付近は、『御府内備考』によると、慶安年中(1648~1652)、川村某が駿河国安倍川(現静岡県静岡市域を中心に流れる一級河川)の鎮守「孫三稲荷」とともに駿河から当地へ移したことにより阿部川町と称していた。
孫三稲荷は、当地に伝わっている由来によると、天正年間(1573~1592)、徳川家康が、「孫三」と名乗る者に馬の轡を取らせ安倍川を渡ったが、後にその孫三を探したところ該当者はなく、ただ安倍川の川辺に「孫三」の名を持つ祠があり、実はこの稲荷の化身であったという霊験から、天正18年(1590)関東入国の際、家康の命により稲荷の神体ごと川村其の手により江戸にもたらされ、慶安年中当地へ移したという。この伝承は、江戸へ招来した年も『御府内備考』と異なるが、『町方書上』に、慶安に安倍川より移安したことが記されており、江戸初期には地域の鎮守として信仰を集めていたことが知られる。
『町方書上』にはまた、当町に店借していた修験者の善明院という人物が「正一位孫三稲荷大明神」を司っており、神像は木造で長さ3寸(約10センチメートル)であったと記されている。
現在、静岡の孫三稲荷の所在は不明であり、当地も関東大震災、東京大空襲などによって、記録や社殿を失ったが、昭和26年(1951)、当町会(阿部川町・菊屋橋町会)によって社殿が再建され、毎年3月8日に例祭が行われている。

03. 小林清親墓(こばやしきよちかはか)
元浅草3-17-2 龍福(りゅうふく)院
小林清親は木版浮世絵師最後の人といえる。
江戸の末、弘化4年(1847)8月1日、浅草御蔵屋敷に武士の子として生まれ、上野戦争には幕府方として参加、明治維新後は、新聞、雑誌にさし絵を描き、生計を立てた。その前後、イギリス人ワーグマンに洋画を、河鍋暁斎、柴田是真からは日本画を修得、浮世絵師としての大成をはかった。
やがて清親の版画には、上野、浅草を中心に新しい東京の風俗・建物が光と影によって描きだされ、それらは、明けゆく明治の時代を先取したものとして、ひろく一般に迎えられた。それは、広重や国芳ともちがう、写実のなかに木版の刷りの美しさを生かしたものだが、浮世絵興亡の歴史からみれば、最後の光でもあった。巷説、わが家が焼けたとも知らず、両国の大火を写生していた男である。
大正4年(1915)11月28日死去。69歳。寺内には小林氏墓「真生院泰岳清親居士」と清親画伯碑がある。
※墓は非公開。写真は昭和6年(1931)に建てられた「清親画伯之碑」です。

04. 葛飾北斎墓(かつしかほくさいはか)
都指定旧跡
元浅草4-6-9 誓教(せんきょう)寺墓地
葛飾北斎(1760〜1849)は江戸後期の浮世絵師で、葛飾流の祖です。宝暦10年(1760)本所割下水に生まれ、鏡師中島伊勢の養子になり、はじめ中島氏を名乗ります。19歳の時に勝川春章の弟子になり、勝川春朗と改名します。役者絵や相撲絵を描きます。春章没後勝川を離れ、狩野派、漢画、土佐派、琳派、司馬江漢の洋風画・銅版画なども学びます。北斎は奇行に富んだ人で、居を九十三度、号を三十数度変えたとされます。肉筆画、版画などに手腕をふるい、特に風景画は賞賛されています。『富嶽三十六景』などが知られ、フランス印象派に影響を与えたとされます。

05. 銅鐘(どうしょう)
台東区有形文化財
元浅草2-5-13 妙経(みょうきょう)寺
妙経寺は山号を寿量山という、日蓮宗の寺院である。『御府内寺社備考』によると、当寺は天文4年(1535)に武蔵国芝崎村(現千代田区大手町)に建立され、慶長16年(1611)に現在地に移転した。
銅鐘の大きさは、総高151.5センチ、口径96センチ。宝暦13年(1763)。四代西村和泉守藤原政時によって鋳造された。
西村家は江戸時代中期から大正時代にかけて鋳物師を務めた家で、全国に多くの作品を残している。神田鍛冶町1丁目(現千代田区神田)に居を構え、代々「和泉守藤原政時」を名乗った。四代は享保5年(1720)に三代の実子として生まれ、市郎兵衛・伊右衛門を称し、江戸府内の代表的な鋳物師であった。
銅鐘の縦帯に「武陽浅草新寺町寿量山妙経寺十世日隆」の陽鋳銘があり、鋳造以来当寺に伝来したものである。
平成8年(1996)に台東区有形文化財として、台東区区民文化財台帳に登載された。

06. 下谷神社(したやじんじゃ)
東上野3-29-8
天平2年(730)、上野の忍ヶ岡(しのぶがおか)に創建されたと伝えられる。
寛永4年(1627)、寛永寺の建立のため山下に移された(現在の岩倉高校あたり)。しかし土地が狭く、延宝8年(1680)に広徳寺前通り(現在の浅草通り)の南側に移る(現在地の近く)。その周囲には武家の屋敷や長屋が建ち並んでいた。
本社は下谷の鎮守として広く信仰を集め、「下谷稲荷社」、「下谷惣社」などと呼ばれた。稲荷町という地名も、本社に由来する。江戸時代には開帳・人形芝居などがおこなわれ、祭礼の時には盛大な行列がみられた。
「下谷神社」と改称したのは明治5年(1872)である。関東大震災の後、昭和3年(1928)の区画整理により、東南に50メートルほどの現在地に移る。新築された拝殿には、池之端に住んでいた日本画の巨匠、横山大観により雲竜図の天井画が描かれた(平成12年、台東区有形文化財)。

07. 長瀧山本法寺御案内(ちょうりゅうざんほんぽうじごあんない)
寿2-9-7
一、長瀧山本法寺(日蓮宗)について
天正19年(1591)太田道灌の居城のあった江戸城紅葉山に、初代日先上人が開山したのが発祥の地である。
その後北条氏が滅亡し、徳川家康が新たに江戸城を築城するさいに、紅葉山から外壕にあたる八丁堀に移った。
さらに明暦3年(1657)江戸の振袖火事の大火で焼失し、幕府が用達町人高原平兵衛に賜与した浅草の拝領町屋敷のあった現在の地に移った。
住居表示で現在は寿町2丁目となっているが、その前の旧高原町という町名はその由来からとったものである。
一、熊谷稲荷の由来について
江戸中期の享保年間の頃、雷門の浅草寺境内にあった熊谷稲荷を、熊谷安左衛門の菩提寺である当本法寺に勧請した。
この熊谷稲荷は、江戸時代から霊験あらたかな稲荷として信者も多く江戸誌に参詣頗る多しと書かれているように、世に名高い稲荷である。
稲荷を祀った狐にもさまざまな種類があり、そのなかでも人間に福徳をわかつ福狐(ふっこ)として白狐だけが稲荷大明神の御眷属にえらばれる資格があると云われている。
白狐は財物に恵まれることと人生の幸福を授かると語りつがれているが、熊谷稲荷は白狐を祀った稲荷で、江戸浅草の本法寺と東北の弘前の津軽藩公が祀った2箇所だけしかないきわめて珍しい稲荷で、江戸時代から霊験があらたかなお守札をだしている稲荷として世に知られている。
一の守、伝教大師から伝授された身体加護・身にふりかかるすべての災難をとりのぞく熊谷稲荷の秘法とされているお守である。
除火難、除盗難のお札 浅草寺誌にもあるとおり、江戸時代からご利益のあるお札として世に名高い。
註、熊谷稲荷縁起の詳細な説明書については、当寺にお申し出あればさしあげます。
一、はなし塚について
境内に台東区教育委員会の文化財史蹟の掲示板があるのでお読みください。
一、その他
当本法寺境内には吉見稲荷、お伽丸柳一の碑、筆塚、山谷なかま塚、江川太郎左衛門の菩提所などがあるのでご自由に御高覧下さい。
本法寺

08. はなし塚(はなしづか)
寿2-9-7 本法(ほんぽう)寺
この塚が建立された昭和16年(1941)10月、当時国は太平洋戦争へと向かう戦時下にあり、各種芸能団体は、演題種目について自粛を強いられていた。落語界では、演題を甲乙丙丁の4種に分類し、丁種には時局にあわないものとして花柳界、酒、妾に関する噺、廓噺等53種を選び、禁演落語として発表、自粛の姿勢を示した。この中には江戸文芸の名作といわれた「明烏(あけがらす)」「五人廻(ごにんまわ)し」「木乃伊取(みいらとり)」等を含み、高座から聴けなくなった。
「はなし塚」は、これら名作と落語界先輩の霊を弔うため、当時の講談落語協会、小咄を作る会、落語講談家一同、落語定席席主が建立したもので、塚には禁演となった落語の台本等が納められた。
戦後の昭和21年(1946)9月、塚の前で禁演落語復活祭が行われ、それまで納められていたものに替えて、戦時中の台本などが納められた。

09. 荷田在満墓(かだのありまろはか)
都指定旧跡
寿2-10-2 金竜(きんりゅう)寺墓地
荷田在満(1706〜1751)は江戸中期の国学者で、京都伏見の稲荷神社の神官荷田信詮(のぶあき)の子高惟(たかのぶ)の子です。本姓は羽倉氏で、字は持之、通称は東之進、号を仁良斎などと称します。早くに伯父であった春満(あずままろ)の家学を継ぎます。享保13年(1728)、和学者として登用されることを求めて江戸に出て幕府に仕えます。その後、徳川吉宗の次男で有職故実の研究者として知られた田安宗武に仕え、有職故実の調査に従事し『本朝制度略考』などを著しました。
元文4年(1739)、『大嘗会便蒙(だいじょうえべんもう)』の無断刊行により幕府の忌憚にふれ、その後、宗武との意見の対立もあり田安家を退隠しました。有職故実の研究においては精緻な家風を打ち立て、歌論では芸術主義的な立場を貫いて、近世歌論の展開にひとつの時期を画しました。宝暦元年(1751)、46歳で没しました。
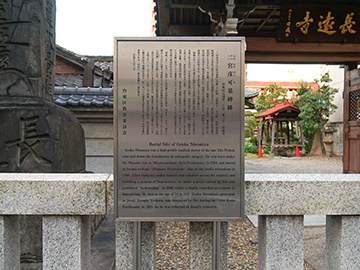
10. 二宮彦可墓碑跡(にのみやげんかぼひあと)
元浅草2-2-3 長遠(ちょうえん)寺
二宮彦可は江戸時代後期に活躍した医師。宝暦4年(1754)三河国(愛知県)岡崎藩主の侍医で国学者でもある小篠敏(おざさみぬ)の長男として、遠江国(静岡県)浜松近郊の叟楽(そうらく)村に生まれる。名は献。字を彦可・齢順といい、号を叟楽・擁鼻と称した。幼少時に乳母から梅毒が感染して、病弱のため廃嫡となるが、明和4年(1767)、同藩の口中科医である二宮元昌の養子となり家督を継いだ。
明和6年(1769)藩主の転封により石見国(島根県)浜田に移る。19歳の頃から各地で医学を学び、口中医を山県良班(広島)、内科を恵美三白(広島)、眼科を三井玄孺(大坂)、産科を賀川玄吾(京都)、内科を山脇東門(京都)に学んだ。また赤松滄洲(赤穂)、湯浅常山(岡山)、亀井南溟を歴訪している。天明8年(1788)には長崎に留学して吉雄耕牛にオランダ外科を学び、さらに吉原杏蔭斎のもとで整骨術の秘訣を伝えられた。
寛政3年(1791)帰国して浜田藩主の侍医を務め、同5年(1793)藩主に随行して江戸に赴き、木挽町5丁目(中央区銀座)に住居した。文化5年(1808)に『正骨範(せいこつはん)』二巻を出版したが、これは吉原杏蔭斎に学んだ整骨術に改良を加え、中国・西洋の諸書を参考としてまとめたもので、整骨術の古典として評価されている。
文政10年(1827)10月11日没。74歳。浅草長遠寺に葬る。法号は擣簁院了服日治居士。墓碑は大正12年(1923)の関東大震災などで焼失し、共同墓地に埋葬される。ほかに一族の墓碑の一部が残る。














