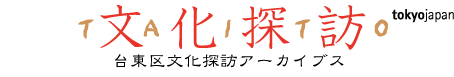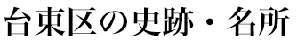01. 講道館柔道発祥の地(こうどうかんじゅうどうはっしょうのち)
東上野5-1-2 永昌(えいしょう)寺
明治15年(1882)、講道館柔道の創始者嘉納治五郎(1860~1938)が友人や門弟と共に稽古を始めたところが、当下谷永昌寺の書院であった。
これが今日、世界各国に普及し国際的な広がりを持つ講道館柔道の発祥とされている。道場となった書院の広さは12畳、初年の門弟は9人であった。
同年夏、当時の住職朝舜法(1837~1914)の協力を得て、玄関脇の空地に、12畳のバラック建て道場を新設したが、翌16年(1883)神田に移った。
永昌寺は、浄土宗で永禄元年(1558)下谷長者町に創建、寛永14年(1637)現在地に移転した。大正12年(1923)の大震災により当時の建物は焼失している。
境内の「講道館柔道発祥之地」と刻む自然石の記念碑は、昭和43年(1968)10月、嘉納治五郎没後30周年を記念し、講道館が建立した。

02. 斎藤長秋三代の墓(さいとうちょうしゅうさんだいのはか)
都指定旧跡
東上野6-17-3 法善(ほうぜん)寺
斎藤家は美濃国の出身といわれ、家康入府の時から江戸神田に住んで、雉子(きじ)町の草分け名主として六ヶ町を支配した。また、神田果物市場を監督して野菜上納のことを掌っていた。代々市左衛門と称した。
斎藤長秋(幸雄)とその子縣麿呂(あがたまろ・幸孝)その孫月岑(げっしん・幸成)は三代にわたって江戸の地誌を調べ、『江戸名所図会(えどめいしょずえ)』を完成させた。
『江戸名所図会』7巻20冊は、江戸の風俗・行事・名所等を絵入りで解説したもので、前編が天保5年(1834)に、後編が同7年(1836)に出版され、挿絵は長谷川雪旦・雪堤父子の手による。文・絵ともに実地踏査に基づいており、江戸の都市景観を知る上で貴重な史料である。
月岑は江戸年中行事を『東都歳時記(とうとさいじき)』、江戸関係事項を『武江年表(ぶこうねんぴょう)』と題し、出版した。いずれも江戸研究者必読の書である。

03. 伊能忠敬墓(いのうただたかはか)
国指定史跡
東上野6-18 源空(げんくう)寺墓地
墓石は角石で、正面に「東河(とうが)伊能先生之墓」と隷書で刻む。忠敬は延享2年(1745)神保貞恒の子として上総国(かずさのくに)に生まれる。名を三治郎という。のち下総国(しもうさのくに)佐原の酒造家・名主の伊能家を継ぐ。名を忠敬と改め、伊能家の家業興隆に精出すかたわら、数学・測量・天文などを研究。漢詩・狂句も良くし、子斉と字し、東河と号した。
50歳の時、家督を譲り江戸に出て、高橋至時(たかはしよしとき)の門に入り、西洋暦法・測図法を学ぶ。寛改12年(1800)幕府に願い出て、蝦夷地(現北海道)東南海岸の測量に着手。以来17年間、全国各地を測量して歩いた。しかし地図未完のうちに文政元年(1818)5月17日没す。享年74歳。
地図作製は、幕府天文方が引き継ぎ、没後3年の文政4年(1821)に完成。その地図は「大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず)」という。また「日本輿地全図」「実測輿地全図」ともいい、俗に「伊能図」と呼ぶ。わが国最初の実測精密地図である。

04. 高橋至時墓(たかはしよしときはか)
国指定史跡
東上野6-18 源空(げんくう)寺墓地
角石の墓碑正面に、「東岡高橋君之墓(とうこうたかはしくんのはか)」と隷書で刻み、三面には、尾藤二州(びとうにしゅう)の撰文を刻む。東岡は至時の号である。
至時は江戸時代中期の暦学者。明和元年(1764)11月、大坂御蔵番同心、高橋元亮の子として生まれる。名を至時、字を子春、通称を作左衛門といい、東岡または梅軒と号した。15歳で父の職を継ぐ。性来、数学・暦学を好み、公務のかたわら、それらの研究に励む。ついで、当時の天文学界の第一人者、麻田剛流(あさだごうりゅう)の門に入って学ぶ。
寛政7年(1795)、改暦の議が幕府で起きると、師剛立の推挙で、同門の間重富(はざましげとみ)とともに天文方に抜擢され、同9年(1797)「寛政暦」をつくる。一方、伊能忠敬が幕命により実測地図を作成する際には、測量を指導し、完成させた。その関係で、二人は後世「日本地図の父母」といわれている。文化元年(1804)1月5日、41歳で肺患のため没した。著書に『赤道日食法』等がある。

05. 谷文晁墓(たにぶんちょうはか)
都指定旧跡
東上野6-18 源空(げんくう)寺墓地
江戸後期文人画家。田安家の家臣で漢詩人谷麓谷(ろうこく)の子である。
名は正安、字は文晁のほかに子方、文五郎、号は画学斎、写山楼、文阿弥などといった。元・明・清画や狩野派、土佐派、文人画、西洋画など各派の手法を研究し画風を工夫し、関西文人画に対して江戸文人画壇の重鎮となった。門人は渡辺華山(わたなべかざん)、立原杏所(たちはらきょうしょ)、高久靄外(たかくあいがい)らと多い。文晁の妻や娘も画家である。
文晁は松平定信に従って諸国を巡歴し、『集古十種』の挿絵を描いた。このほか『名山図会』『本朝画纂』「公余探勝図(重要文化財)」などがあり、人物、山水、花鳥、虫魚を得意とし、特に水墨山水に妙を得ていた。天保11年(1840)12月14日没。年78。
昭和2年(1927)4月、東京都旧跡に指定された。
※谷文晁の説明板は、東上野6丁目19番2号の源空寺門前に建っています。

06. 幡随院長兵衛墓(ばんずいいんちょうべえはか)
都指定旧跡
東上野6-18 源空(げんくう)寺墓地
江戸初期の町奴。本名は塚本伊太郎。肥前唐津の士族で、幡随院の住職向導に私淑(一説には向導の実弟、または幡随院の門守の子ともいう)し、浅草花川戸に住み、奉公人を周旋する口入れ業に従事していたといわれる。
当時町奴と呼ばれる仁侠の徒が横行し、また、大小神祇組という旗本奴も市街を乱していた。やがて長兵衛は町奴の頭領となり、旗本奴の頭領水野十郎左衛門と張り合ったという。この辺は多くの伝説と潤色で後世の人々にもてはやされているため、つまびらかにはできない。
慶安3年(1650)4月13日、水野十郎左衛門のだまし討ちにあって没した。年36。
昭和2年(1927)4月 東京都旧跡に指定された。
※幡随院長兵衛墓の説明板は、東上野6丁目19番2号の源空寺門前に建っています。

07. 銅鐘(どうしょう)
台東区有形文化財
東上野6-19-2 源空(げんくう)寺
源空寺は浄土宗増上寺の末寺。寺伝によれば、円誉道阿(えんよどうあ)が天正18年(1590)湯島(現文京区)に草庵を結び、多くの信者を集めたことに始まり、徳川家康も道阿に深く帰依したという。慶長9年(1604)草庵の地に寺院を開き、開祖法然坊源空(ほうねんぼうげんくう)の名に因み「源空寺」と称した。二世専誉直爾(せんよちょくじ)の時、明暦3年(1657)の大火に遭って類焼し、当地に移転した。
源空寺の銅鐘は総高2メートル22センチで、江戸時代の銅鐘としては大型である。胴周りの銘文によれば、寛永13年(1636)三代将軍徳川家光の勧めを請け、開山道阿が願主となり鋳造されたもので、徳川家康の法号「大相国一品徳蓮社崇誉道和大居士」、同秀忠の法号「台徳院殿一品大相国公」、家光の官職・姓名「淳和奨学両院別当氏長者正二位内大臣征夷大将軍源家光公」を刻んでいる。
作者は「椎名勝十郎藤原義定」。鋳物師椎名家は、初代伊予守吉次より代々徳川将軍家御用鋳物師を務め、本銅鐘の作者義定もその一族と思われる。
本銅鐘は、昭和19年(1944)に旧重要美術品の認定を受け、平成9年(1997)には、台東区有形文化財として台東区区民文化財台帳に登載された。

08. 銅鐘(どうしょう)
台東区有形文化財
東上野6-13-13 報恩(ほうおん)寺
坂東報恩寺の通称で知られる当寺は、建保2年(1214)親鸞の高弟性信(しょうしん)によって開かれた浄土真宗大谷派の寺院で、初め下総国横曾根(現茨城県常総市)にあったが、慶長7年(1602)江戸に移転、その後市中を三転し、文化7年(1810)現在地に至る。
本鐘が鋳造されたのは、慶安元年(1648)で、当時報恩寺は八丁堀にあった。銘文によると、報恩寺十四世住持宣了および檀信徒の講中の発願で作られた。銘文の末尾に記されている鋳造者の「堀山城守藤原清光」は、江戸幕府の命で京都から江戸に下った御用釜師堀浄栄の息子浄甫(じょうほ)を指す。父子とも当代一流の鋳物師で、浄甫の作品にはこの銅鐘のほか、渋谷区祥雲寺の銅鐘・日光東照宮の銅灯籠・上野東照宮の銅灯籠などが現存している。
本鐘は、昭和18年(1943)、重要美術品の認定を受け、平成8年(1996)、台東区有形文化財として、区民文化財台帳に登載され、当寺境内鐘楼(平成2年竣工)に安置される。