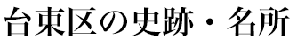01. 石川雅望墓(いしかわまさもちはか)
都指定旧跡
蔵前3-22-9 榧(かや)寺(正覚寺)墓地
石川雅望(1753〜1830)は江戸時代後期の国学者、狂歌師です。旅館糠屋七兵衛こと浮世絵師石川豊信の子として生まれ、六樹園、五老斎などと号しました。国学を津村淙庵(そうあん)、狂歌を大田南畝らに学び、狂名を宿屋飯盛(やどやのめしもり)といいました。
天明年間に狂歌壇に台頭し、狂歌四天王に数えられます。寛政3年(1791)、宿屋経営に関連して江戸を一時離れますが、このころ、国学に務め『源注余滴』『雅言集覧』を著します。文化期には狂歌壇に復帰し、文化文政時代の狂歌界を鹿津部真顔(しかつべのまがお)と二分する勢力となります。真顔の俳諧歌体に対して俗情俗語の狂歌の軽妙さを主張しました。
『(百人一首)古今狂歌袋』などの狂歌絵本や、『万代狂歌集』などの狂歌撰集の他『草まくら』などの紀行文もあります。

02. 初代柄井川柳句碑(しょだいからいせんりゅうくひ)
蔵前4-36-7 龍宝(りゅうほう)寺墓地
柄井川柳(1718〜1790)は、江戸時代中期の前句付点者(まえくづけてんじゃ)です。名は正道、通称を八右衛門といいます。俳号を緑亭、無名庵、川柳などと号します。俳暦は不詳ですが、最初雑林派の宗匠であったが後に前句付の点者になったとされます。宝暦4年(1757)、万句号を興行し、万句号付点者として力量をあらわしました。
やがて、その選句を川柳点といい、後に付句が独立して川柳と称されるようになりました。寛政2年(1790)、73歳で死去し、柄井家は3代で絶えますが、4代以降は子弟相承して13代まで受け継がれます。

03. 初代柄井川柳墓(しょだいからいせんりゅうはか)
都指定旧跡
蔵前4-36-7 龍宝(りゅうほう)寺墓地
川柳文芸の始祖、柄井八右衛門は享保3年(1718)に生まれる。名主を勤めるかたわら、宝暦7年(1757)前句付点者(まえくづけてんじゃ)となり、33年間にわたり名声を得た。寛政2年(1790)没。行年73歳。明治以降、俳号である「川柳」が文芸名として定着し、今日に受け継がれている。
2基の墓石のうち、左側の石塔が初代の墓で、表面右から初代川柳夫婦、三代川柳夫婦の戒名を刻す。
契壽院川柳勇縁信士 寛政二庚戌九月廿三日
微妙院浄心法性信女 天明六丙午二月十七日
但受院浄刹快樂信士 文政十丁亥六月二日
無量院長遠妙壽信女
右側の墓石には、次のように、二代川柳夫妻の戒名を刻してあったが、現在は風化して判読できない。
圓鏡院智月寂照信士 文政元戊寅十月十七日
心鏡院常照妙光信女 文政七甲申四月七日
墓域の後方、初代柄井川柳墓の右側に明治22年(1889)建立の元祖川柳翁一百回紀念標がある。

04. 不動板碑(ふどういたび)
台東区有形文化財
蔵前4-36-7 龍宝(りゅうほう)寺
板碑は石造の塔婆で、板石塔婆(いたいしとうば)ともいう。鎌倉時代から室町時代にかけて、追善供養などの目的で造られた。
この板碑は高さ155.8センチメートル、上端の幅39センチメートル、下端の幅44.5センチメートル、厚さ約5センチメートル。中央に不動明王の種子(しゅし・仏体を表した梵字)を刻むため、「不動板碑」と呼ばれ、区内現存の板碑を代表するもののひとつである。
碑の表面は、最上部三角状の下に二条線という横線の深い切り込みがあり、大きな蓮華座の上に不動の種子(カーンマンと読む)を大書し、その下方には、蓮台に乗せた「父」の字、「正応六季八月日孝子敬白」の銘を刻み、その両側には
六大無碍常瑜伽 四種曼荼各不離
三密加持速疾顕 重々帝網名即身
と「即身成仏義(そくしんじょうぶつぎ)」という経典の一節を刻む。銘文によって、この板碑は鎌倉時代後期の正応6年(1293)に造立者の父を供養する目的で建てられたことが理解できる。
平成2年(1990)に、台東区有形文化財として文化財台帳に登載された。

05. 三島政行墓(みしままさゆきはか)
都指定旧跡
蔵前4-18-11 浄念(じょうねん)寺墓地
三島政行(1780〜1856)は江戸後期の幕臣です。三島政春の六男として生まれ、三島政世の養子となります。通称を政蔵といい、知遇翁、凸凹斎(でこぼこさい)などと号します。文政元年(1818)御所院番になり、その後清水殿物頭となります。文政9年(1826)に命により江戸府内の地誌『御府内風土記』の編纂を手掛けます。この地誌は明治5年(1872)に焼失しましたが、残った資料集が『御府内備考』となります。このほか、『新編武蔵風土記稿』などの編纂にも参画しています。安政3年(1856)77歳で没します。

06. 高嵩谷墓(こうすうこくはか)
蔵前4-15-2 法林(ほうりん)寺
高嵩谷は、享保15年(1730)江戸に生まれる。江戸中期の画家で、名を一雄、号を屠竜翁(とりゅうおう)、翠雲堂(すいうんどう)などと称した。画を英一蝶(はなぶさいっちょう)の門人佐脇嵩之(さわきすうし)に学んだ。
英一蝶は、市井の風俗を軽妙に描写し、英派という一派を開いた元禄期を代表する画家の一人である。
嵩谷は、一蝶風の風俗画を得意としたが、後には、武者絵に新境地を開いた。浅草寺に現存する大絵馬「源三位頼政鵺退治図(げんざんみよりまさぬえたいじず)」は、天明7年(1787)の制作で、嵩谷の代表作のひとつ。『平家物語』に記されている、源頼政が紫宸殿で猪ノ早太と共に怪獣鵺(ぬえ)を射止めた武勇伝を描いたものである。また、根岸3丁目の永称寺には、墨画竹虎図の屏風がある。
文化元年(1804)8月、75歳で没し、当寺に葬られた。なお、墓所は非公開である。

07. 育英小学校発祥の地(いくえいしょうがっこうはっしょうのち)
蔵前4-16-16 西福(さいふく)寺
明治2年(1869)3月、明治新政府は、幕府・藩による政治体制にかわる新しい日本の構築にあたって、国民全体の教育の推進をはかるため、小学校の設置を定め、明治3年(1870)3月、東京に6つの小学校を設立した。
その一つが、本寺境内に設立された「仮小学 第四校」で、育英小学校の前身である。開校日は同年6月23日で、現蔵前・鳥越・浅草橋・柳橋・三筋付近に居住していた旧大名・旗本及びその家臣の子弟たちが入学したといわれる。したがって当地は、同5年(1872)8月の学制発布に先だつ、東京で最も早い公立小学校発祥の地である。
当校は、同7年(1874)4月中旬に医学館跡地(現浅草橋4丁目17番付近)へ移転、明治10年(1877)8月、育英小学校と改称し、同18年(1885)10月に浅草橋2丁目26番8号に移った。
※育英小学校は、平成13年(2001)柳北小学校と統合し、現在は台東育英小学校となっている。

08. 勝川春章墓(かつかわしゅんしょうはか)
都指定旧跡
蔵前4-16-16 西福(さいふく)寺
勝川春章(1726〜1792)は江戸時代中期の浮世絵師で勝川派の祖です。姓は藤原、諱は正輝、縦画生、旭朗井、李林などとも号します。無名時代に寄寓していた人形町の地本問屋林屋七右衛門方の壺形の仕切判を画印とし、「壺屋」「壺春章」と称されます。画風は個性的描写とは異なり、写実的な役者絵などを描きます。寛政4年(1792)67歳で没します。勝川派は、門下にも春英や春好、のちに葛飾北斎となる春朗など俊英を輩出し、明和から寛政期の役者絵を独占します。

09. 天文台跡(てんもんだいあと)
浅草橋3
この地点から西側、通りを一本隔てた区画(浅草橋3丁目21・22・23・24番地の全域及び19・25・26番地の一部)には、江戸時代後期に幕府の天文・暦術・測量・地誌編纂・洋書翻訳などを行う施設として、天文台がおかれていた。
天文台は、司天台(してんだい)、浅草天文台などと呼ばれ、天明2年(1782)、牛込藁店(現新宿区袋町)から移転、新築された。正式の名を「頒暦所御用屋敷」という。その名の通り、本来は暦を作る役所「天文方(てんもんがた)」の施設であり、正確な暦を作るためには観測を行う天文台が必要であった。
その規模は、『司天台の記』という史料によると、周囲約93.6メートル、高さ約9.3メートルの築山の上に、約5.5メートル四方の天文台が築かれ、43段の石段があった。また、別の史料『寛政暦書』では、石段は2箇所に設けられ、各50段あり、築山の高さは9メートルだったという。
幕末に活躍した浮世絵師、葛飾北斎の『富嶽百景』の内、「鳥越の不二」には背景に富士山を、手前に天体の位置を測定する器具「渾天儀(こんてんぎ)」を据えた浅草天文台が描かれている。
ここ浅草の天文台は、天文方高橋至時(よしとき)らが寛政の改暦に際して観測した場所であり、至時の弟子には伊能忠敬がいる。忠敬は、全国の測量を開始する以前に、深川の自宅からこの天文台までの方位と距離を測り、緯度一分の長さを求めようとした。また、至時の死後、父の跡を継いだ景保の進言により、文化8年(1811)天文方内に「蕃書和解御用(ばんしょわげごよう)」という外国語の翻訳局が設置された。これは後に、洋学所、蕃書調所、洋書調所、開成所、開成学校、大学南校と変遷を経て、現在の東京大学へ移っていった機関である。
天文台は、天保13年(1842)、九段坂上(現千代田区九段北)にも建てられたが、両方とも、明治2年(1869)に新政府によって廃止された。

10. 鳥越神社(とりこえじんじゃ)
鳥越2-4-1
当神社は、白雉2年(651)の創建。日本武尊(やまとたけるのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、徳川家康を合祀している。
社伝によると、日本武尊が、東国平定の道すがら、当時白鳥村といったこの地に滞在したが、その威徳を偲び、村民が白鳥明神として奉祀したことを起源とする。後、永承年間(1046~1052)、奥州の安倍貞任らの乱(前九年の役)鎮定のため、この地を通った源頼義、義家父子は、名も知らぬ鳥が越えるのを見て浅瀬を知り、大川(隅田川)を渡ったということから鳥越大明神と名付けた。以後、神社名には鳥越の名を用いるようになり、この辺りは鳥越の里と呼ばれるようになった。天児屋根命は、武蔵の国司になった藤原氏がその祖神として祀ったものとされる。また、徳川家康を祀っていた松平神社(現蔵前4丁目16番付近)は、関東大震災で焼失したため大正14年(1925)に当社に合祀された。
例大祭は、毎年6月9日前後の日曜。千貫神輿といわれる大神輿の渡御する「鳥越の夜祭」は盛大に賑い、また正月8日に正月の片付け物を燃やす行事「とんど焼き」も有名である。

11. 浅草御蔵跡碑(あさくさおくらあとひ)
蔵前2-1
浅草御蔵は、江戸幕府が全国に散在する直轄地すなわち天領から運んだ年貢米や買い上げ米などを収納、保管した倉庫である。大坂、京都二条の御蔵とあわせて三御蔵といわれ、特に重要なものであった。浅草御蔵は、また浅草御米蔵ともいい、ここの米は主として旗本、御家人の給米用に供され、勘定奉行の支配下に置かれた。
元和6年(1620)浅草鳥越神社の丘を切り崩し、隅田川西岸の奥州街道沿い、現在の柳橋2丁目、蔵前1・2丁目にかけての地域を埋め立てて造営した。このため、それ以前に江戸にあった北の丸、代官町、矢の蔵などの米蔵は、享保頃(1716~1736)までに浅草御蔵に吸収された。
江戸中期から幕末まで、浅草御蔵の前側を「御蔵前」といい、蔵米を取り扱う米問屋や札差の店が立ち並んでいた。現在も使われている「蔵前」という町名が生まれたのは、昭和9年(1934)のことである。
碑は、昭和31年(1956)6月1日、浅草南部商工観光協会が建立したものである。

12. 首尾の松(しゅびのまつ)
蔵前1-3
この碑から約100メートル川下に当たる、浅草御蔵の四番堀と五番堀のあいだの隅田川岸に、枝が川面にさしかかるように枝垂れていた「首尾の松」があった。
その由来については次のような諸説がある。
一、寛永年間(1624~1643)に隅田川が氾檻したとき、三代将軍家光の面前で謹慎中の阿部豊後守忠秋が、列中に伍している中から進み出て、人馬もろとも勇躍して川中に飛び入り見事対岸に渡りつき、家光がこれを賞して勘気を解いたので、かたわらにあった松を「首尾の松」と称したという。
二、吉原に遊びに行く通人たちは、隅田川をさかのぼり山谷堀から入り込んだものだが、上り下りの舟が、途中この松陰によって「首尾」を求め語ったところからの説。
三、首尾は「ひび」の訛りから転じたとする説。江戸時代、このあたりで海苔をとるために「ひび」を水中に立てたが訛って首尾となり、近くにあった松を「首尾の松」と称したという。
初代「首尾の松」は、安永年間(1772~1780)風災に倒れ、更に植え継いだ松も安政年間(1854~1859)に枯れ、三度植え継いだ松も明治の末頃枯れてしまい、その後「河畔の蒼松」に改名したが、これも関東大震災、第二次大戦の戦災で全焼してしまった。昭和37年(1962)12月、これを惜しんだ浅草南部商工観光協会が、地元関係者とともに、この橋際に碑を建設した。現在の松は7代目といわれている。

13. 浅草文庫跡碑(あさくさぶんこあとひ)
蔵前1-4-3 榊(さかき)神社
浅草文庫は、明治7年(1874)7月に創設された官立の図書館である。翌8年に開館し、公私の閲覧に供した。当時の和・漢・洋の蔵書数は11万余冊とも13万余冊ともいわれている。現在その蔵書は、国立公文書館内閣文庫や国立国会図書館、東京国立博物館などに所蔵され、太政大臣三条実美(さんじょうさねとみ)の筆蹟と伝える「浅草文庫」の朱印が押されている。
明治14年(1881)5月に閉鎖。跡地は翌15年に設立の東京職工学校(旧東京高等工業学校、現東京工業大学)の敷地の一部となった。関東大震災後の大正13年(1924)、当時の東京高等工業学校は目黒区大岡山に移転。
昭和3年(1928)に現在地に移ってきた榊神社のあたりは、かつて浅草文庫が位置していたところである。高さ約4メートルの碑は、この文教の旧地を記念して、昭和15年(1940)11月建立された。

14. 蔵前工業学園の蹟(くらまえこうぎょうがくえんのせき)
蔵前1-4-3 榊(さかき)神社
本石碑は、当地にあった東京高等工業学校(現東京工業大学)を記念し、工業教育発祥の地として同窓会の蔵前工業会が建立したものである。当校は、工業指導者の養成を目的として、明治14年(1881)5月東京職工学校として創設され、明治23年(1890)3月東京工業学校、明治34年(1901)東京高等工業学校と改称された。
当校は、常に日本の工業教育の指導的地位にあり、また、多くの留学生を教育するなど、科学技術の発展に貢献し、当校の出身者は「蔵前の出身」という愛称で重用された。
しかし、大正12年(1923)9月の関東大震災により、校舎、工場等が灰燼に帰したため、学校当局は、当地での再建を断念、目黒区大岡山に移転した。当地の敷地は、正門の位置に建てられている本石碑を中心に、隅田川に沿って面積43,000平方メートルに及んでいた。
側面に「昭和十八年三月吉日 社団法人蔵前工業会建之」裏面に「永田秀次郎撰」の碑文が刻されている。

15. 蔵前工業学園の蹟 碑文(くらまえこうぎょうがくえんせき ひぶん)
蔵前1-4-3 榊(さかき)神社
裏面
浅草蔵前ノ地二東京職工学校ヲ創設セラレタルハ実二明治十四年ノ事二属ス。爾来歳ヲ閲スルコトヲスルコト六十二星霜、技術者ヲ輩出スルコト万ヲ超エ、此間時勢ノ進運二伴ヒ校名ヲ明治二十三年東京工業学校ニ、同三十四年東京高等工業学校二改メラレタルガ、偶々大正十二年大震二遭ヒ、其復興ヲ企図スルニ当り、寧ロ都心ヲ離レテ郊外ノ地ヲトスルニ若カズトナシ、翌十三年大岡山ノ地ニ移リ、昭和四年昇格シテ東京工業大学卜呼称セラルルニ至ル。其校門ヲ出ヅル者、何レモ質実剛健ノ校風ヲ継承シテ、今ヤ所謂蔵前出身ノ技術者ハ、全東亜二亘リテ建設ノ重要部分ヲ担ヒ、各其特色ヲ発揮シテ産業報国ノ実ヲ昂揚シツツアルハ、世ノ等シク認ムル所ナリ。然ルニ此工業発祥ノ地トモ謂フべキ蔵前学園ノ蹟ニ至リテハ、既ニ全ク変貌シテ其面影ヲ偲ブニ由ナク、今ニシテ之レヲ表示スルニ非ラザレバ、此由緒深キ学園ノ地モ、遂二湮滅セラレンコトヲ惧ル。恰モ好シ、往年其正門所在地附近一帯ハ榊神社ノ境内トナリ、之レヲ標識スルニ便アリ。是ニ於テ本会ハ神社関係者卜相図リ、石二刻シテ其地蹟ヲ表シ以テ蔵前工業学園ノ蹟ヲ永ク後世二伝ヘントス。
昭和十七年一月吉日
社団法人 蔵前工業会
帝国教育会長 永田秀次郎撰
側面
昭和十八年三月吉日
社団法人 蔵前工業会建之
昭和六十一年一月吉日
社団法人 蔵前工業会

16. 速水御舟生誕地(はやみぎょしゅうせいたんち)
柳橋1-19
当地と想定される、浅草区浅草茅町(かやちょう)2丁目16番地で、速水御舟は明治27年(1894)8月2日に生まれた。良三郎、いとの次男として出生し、本名を蒔田栄一といった。
御舟は早くから絵に志し、明治41年(1908)14歳の時、松本楓湖(ふうこ)の安雅堂画塾に入門。同画塾は浅草茅町2丁目31番地にあった。入門の翌年、師から禾湖(かこ)の号を授かる。そして母方祖母の速水キクの養子となる。大正3年(1914)号を御舟と改め、このころから速水姓を称するようになったという。
明治43年(1910)、16歳で作品を初めて展覧会に出品。翌年出品の「室寿(むろほぎ)の宴」は一等褒状を受け、宮内省買上げとなる。大正6年(1917)第4回院展に「洛外六題」を出品し、横山大観・下村観山に激賞された。
昭和10年(1935)将来を嘱望されながら40歳で没した。作品には、昭和52年(1977)国の重要文化財指定の「炎舞」「名樹散椿」などがある。

17. 柳橋(やなぎばし)
柳橋1-1-1
この橋は、元禄11年(1698)に神田川が隅田川に注ぐところに架けられ、最初は「川口出口の橋」と呼ばれた。近くに幕府の矢の倉があったのに因み、矢の倉橋・矢之城橋と呼んだともいう。柳橋は享保頃からの呼称らしい。橋の名の由来には、「柳原堤の末にある」「矢之城を柳の字に書きかえた」「橋畔の柳に因む」など諸説ある。鉄橋に架け替えられたのは明治20年(1887)で、現在の橋は昭和4年(1929)に完成した。江戸時代、橋畔は船宿が並んで賑わった。幕末・明治以降、柳橋は花柳界として名を知られ、多くの文人・墨客が題材に取り上げている。また、柳橋は落語にもよく登場し、「船徳」等はこの地を舞台にした噺である。
柳橋ゆかりの人々
成島柳北 蔵前生まれ。『柳橋新誌』を著した。
小林清親 「元柳橋両国遠景」で、往時の柳橋周辺の情景を描いた。
正岡子規 句集『寒山落木』の中で「春の夜や 女見返る 柳橋」と詠んだ。
島崎藤村 今の柳橋1丁目に住み、柳橋を題材にした随筆『新片町にて』を発表し、小説『沈黙』の中では大正期の柳橋界隈を情緒豊かに書いている。また、代表作の『春』『家』などの作品も柳橋在住のときに発表した。
池波正太郎 『剣客商売』などの作品で柳橋界隈を取り上げている。