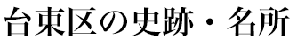01. 佐竹家上屋敷・佐竹っ原跡(さたけけかみやしき・さたけっぱらあと)
台東2・3・4丁目付近
江戸時代、この付近一帯は、出羽国久保田(秋田)藩の上屋敷があった地である。藩主は佐竹氏で、20万余石を領有した、東北地方屈指の外様大名であった。佐竹家上屋敷の当地開設年代は、『武鑑(ぶかん)』からみて、元禄2年(1689)もしくは翌3年と考えられる。屋敷地は広大で、現在の台東3・4丁目東半分にわたっていた。
佐竹家八代藩主佐竹義敦(よしあつ・号曙山[しょざん])は、日本初の本格的西洋医学書の翻訳書『解体新書(かいたいしんしょ)』(安永3年[1774]刊)付図を描いた藩士小田野直武(おだのなおたけ)らとともに、洋風画の一派「秋田蘭画(あきたらんが)」の基礎を築いた。また天明年間(1781~1789)の狂歌師手柄岡持(てがらのおかもち)も藩士であり、当時の文化人がここを中心に活躍していたことがうかがわれる。
明治になって佐竹家上屋敷や近隣の武家屋敷が撤去され、当地は野原となり、俗に佐竹っ原と呼ばれた。ここは見世物小屋が集中して賑わったが、明治時代半ばから民家が立ち並び、商店街として発展した。現在、「佐竹」の名は、「佐竹商店街」として継承されている。

02. 三味線堀跡(しゃみせんぼりあと)
小島1-5
現在の清洲橋通りに面して、小島1丁目の西端に南北に広がっていた。寛永7年(1630)に鳥越川を掘り広げて造られ、その形状から三味線掘とよばれた。一説に、浅草猿屋町(現在の浅草橋3丁目あたり)の小島屋という人物が、この土砂で沼地を埋め立て、それが小島町となったという。
不忍池から忍川を流れた水が、この三味線堀を経由して、鳥越川から隅田川へと通じていた。堀には船着揚があり、下肥・木材・野菜・砂利などを輸送する船が隅田川方面から往来していた。
なお天明3年(1783)には堀の西側に隣接していた秋田藩佐竹家の上屋敷に三階建ての高殿が建設された。大田南畝(おおたなんぽ)が、これに因んだ狂歌を残している。
三階に三味線堀を三下り二上り見れどあきたらぬ景
江戸・明治時代を通して、三味線掘は物資の集散所として機能していた。しかし明治末期から大正時代にかけて、市街地の整備や陸上交通の発達にともない次第に埋め立てられていき、その姿を消したのである。

03. 甚内神社(じんないじんじゃ)
浅草橋3-11-5
当社は「甚内霊神(じんないれいじん)」の名で、江戸時代初期に創建された。伝承によれば、甚内は武田家の家臣高坂弾正(こうさかだんじょう)の子で、主家滅亡後、祖父に伴われ諸国を行脚するうち宮本武蔵に見出されて剣を学び奥義を極めた。武田家再興をはかり、開府早々の江戸市中の治安を乱したため、瘧(おこり・マラリア)に苦しんでいたところを幕府に捕えられた。
鳥越の刑場で処刑されるとき「我瘧病にあらずば何を召し捕れん。我ながく魂魄(こんぱく)を留、瘧に悩む人もし我を念ぜば平癒なさしめん」といったことから、病の治癒を祈る人々の信仰を集めたという。8月12日の命日は、今も多くの人で賑わっている。
かつて鳥越川に架かる橋の一つ「甚内橋」の名も、付近に甚内神社があったからだといわれる。鳥越川は、今は暗渠となり橋もなくなったが、その名は「甚内橋遺跡(浅草橋3丁目13番4号)」の小碑に残されている。
関東大震災まで浅草消防署の付近にあったが焼失。その後移転。昭和5年(1930)、現在地に移った。

04. 蓬莱園跡(ほうらいえんあと)
浅草橋5-1-20
現在、都立忍岡高等学校・柳北公園・柳北小学校のある一帯に、江戸時代、肥前国(現佐賀県、長崎県の一部)平戸藩主松浦(まつら)氏の屋敷があった。寛永9年(1632)、松浦氏は幕府からこの地を与えられ、別邸を造営し、庭園を築造した。庭園は後に蓬莱園と命名された。
明治40年(1907)刊行の『東京案内』には「文化文政の頃の築造に係り、東都名園中現存するものの一也」と記されている。園内の模様は大正3年(1914)刊行の『浅草区誌』に詳しい。同書によると、大池を中心に、岡を築き、樹木を植え、東屋(あずまや)を建て、13基余の燈籠を配し、園内各所に雅趣ある名称を付した。面積は約2,600坪に及び、池水は鳥越川から取り入れていた。
この名園も関東大震災のために荒廃し、消滅した。現在は忍岡高等学校グラウンド東北隅に、池の一部と、都天然記念物指定の大イチョウを残すだけである。
※柳北小学校(旧浅草橋5丁目1番35号)は平成13年(2001)育英小学校と統合し、現在は台東育英小学校(浅草橋2丁目26番8号)となっています。

05. 旧蓬莱園のイチョウ(きゅうほうらいえんのいちょう)
都指定天然記念物
浅草橋5-1-20 忍岡高等学校
蓬莱園は、寛永9年(1632)に肥前平戸藩主松浦侯のために、小堀遠州が造営した名園です。池泉は校庭として埋め立てられ、わずかに北東の隅にその面影が残っています。このイチョウはその当初からあったもので、高さ約21.3メートル、幹囲約4.8メートルあります。

06. 市村座跡(いちむらざあと)
台東1-5
明治25年(1892)11月、下谷二長町1番地といったこの地に、市村座が開場した。市村座は歌舞伎劇場。寛永11年(1634)日本橋葺屋町に創始し、中村・森田(のち守田)座とともに、江戸三座と呼ばれた。天保13年(1842)浅草猿若町2丁目に移り、ついで当地に再転。
二長町時代の市村座は、明治26年(1893)2月焼失。同27年(1894)7月再建して東京市村座と呼称。大正12年(1923)9月の関東大震災で焼けたが再興、昭和7年(1932)5月に自火焼失し消滅という変遷を経た。明治27年(1894)再建の劇場は煉瓦造り三階建で、その舞台では、六世尾上菊五郎・初代中村吉右衛門らの人気役者が上演した。いわゆる菊五郎・吉右衛門の二長町時代を現出し、満都の人気を集めた。しかし、その面影を伝えるものはほとんどなく、この裏手に菊五郎・吉右衛門が信仰したという千代田稲荷社が現存する程度である。

07. 伊東玄朴居宅跡(種痘所跡)(いとうげんぼくきょたくあと・しゅとうじょあと)
台東1-30付近
この辺りに、蘭方医伊東玄朴の居宅兼家塾「象先堂(しょうせんどう)」があった。伊東玄朴は、寛政12年(1800)肥前国仁比山村(にいやま・現佐賀県神埼郡神埼町)で農民の子として生まれた。後佐賀藩医の養子となり、長崎でドイツ人医師フランツ・フォン・シーボルトらに蘭学を学び、その後江戸に出て、天保4年(1833)に当地に居を構えた。安政5年(1858)には、将軍家定の侍医も務め、その名声は高まり門人が列をなした。
玄朴はまた、江戸においてはじめて種痘法を開始した人物である。種痘とは、1980年に世界保健機構(WHO)より撲滅宣言された天然痘に対する予防法。1796年、イギリス人エドワード・ジェンナーが発明し、天然痘によって多くの人間が命を落としていたため、種痘法は西洋医学をわが国で受け入れる決定的な要因となった。嘉永2年(1849)、長崎でドイツ人のオランダ商館医オットー・モーニケが、佐賀藩医楢林宗建(ならばしそうけん)の子供に接種したのが、わが国における種痘成功の最初である。
江戸では、安政4年(1857)、神田お玉が池(現千代田区岩本町)に玄朴ら八十余名が金銭を供出して種痘所設立を図り、翌年竣工した。種痘所は、この翌年火災により焼失してしまったため、下谷和泉橋通の仮施設に移り、翌万延元年(1860)再建された。同年には幕府直轄の公認機関となり、この後「西洋医学所」「医学所」「医学校」「大学東校」という変遷をたどり、現在の東京大学医学部の前身となった。
幕府の機関となった種痘所の位置は、伊東玄朴宅のすぐ南側、現在の台東1丁目30番地の南側半分、同28番地の全域に相当する。
なお、谷中4丁目4番地の天龍院門前には伊東玄朴の墓(都指定旧跡)についての説明板が建っています。