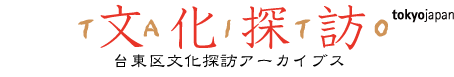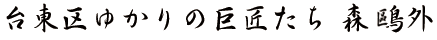台東区立下町風俗資料館(台東区上野公園2-1)
台東区立下町風俗資料館学芸員の本田弘子さんに話を伺いました。2019 年3 月29 日取材
明治期の上野
Q:鴎外が『舞姫』を執筆した当時の上野界隈は、どのような場所だったのでしょうか。
本田 : 鴎外が鴎外荘(現水月ホテル鴎外荘)で『舞姫』を書かれていた明治22年(1889)頃の上野界隈という事ですが、まずそこから遡ること明治6年(1873)に、当時の新政府が寛永寺の寺領であった上野界隈を上野公園として制定しました。それに合わせて、上野公園内にはその後博物館や動物園ができ、不忍池(しのばすのいけ)などもありましたので、上野界隈は文化的なひろがりが目立つ地域だったのではないかと思います。
特に鴎外が池之端の鴎外荘に住んでいた頃は、不忍池の周囲では競馬が開催されていました。競馬と言っても今のようなギャンブル性が強いものでなく、軍馬を養成するための馬匹(ばひつ、馬の事)奨励を目的とした競馬が開かれていたという 事もありまして、この地が多くの人が集まる場所になったかと思います。内国勧業博覧会も上野公園で開催されましたが、日本がどんどん西洋化していく中で、殖産興業を人々に知らしめ日本が進んでいく道を一般の人に示す場所だったかと思います。
Q.:競馬はどの辺りで開催されていたのですか。
不忍池の周囲です。今は上野動物園の敷地になっているのですが、そちらから、この資料館の前あたりまでがコースになっていたようです。

楊洲周延「上野不忍競馬会之図」(国立国会図書館蔵)

競馬の風景(明治39年(1906)、台東区立下町風俗資料館蔵)
不忍池今昔
Q:貴資料館で平成30年(2018)に開催された「不忍池─水面にうつる江戸から東京」展では、不忍池の歴史等についても紹介されていますが、不忍池界隈はどのように形成されたのでしょうか。鴎外の代表作『雁』には、無縁坂の南側の岩崎邸、上野広小路の情景が書かれていますが、この界隈は今日でも変わっていないのでしょうか。
まず不忍池ですが、元々は上野付近までが東京湾の入り江の名残だとされています。一万年前から六千年前には現在の上野公園のある上野台の麓(ふもと)まで東京湾が入り込んでいて、その後に海面が下がった際に、上野台と本郷台の間に取り残された水場が、不忍池の原型となりました。おおまかな池の形となったのは紀元前頃の事と言われています。
江戸時代の寛永年間の地図によると、池の形は大きく異なっていて、北西の根岸方面から水が流れ込んでおり、その大きさも現在の3倍近い面積がありました。天海僧正によって東叡山寛永寺が建立され、不忍池もその寺領に含まれると、池の中央に中之島(弁天島)が築かれ、池の周りは整備されていきました。現在の3倍近くあった池は徐々に埋め立てられて、『雁』の書かれた明治時代には、ほぼ現在と同じ面積になっていたようです。その後、明治8年(1875)に上野公園に編入された不忍池は、競馬や博覧会の会場として整備され、また昭和4年(1929)には築堤工事が行われて池は分割されました。不忍池は、昭和26年(1951)までは現在の形とは異なり4分割されていました。
『雁』の舞台としての不忍池は現在とも変化はあまりありません。明治17年(1884)に池の周囲が競馬場として、また明治40年(1907)からは博覧会会場として利用され、また北西から流れ込んんでいた藍染川(あいぞめがわ)、そして南東から流れ出て広小路を横切って、その先の三味線掘(しゃみせんぼり)に流れ込んでいた忍川(しのぶかわ)は暗渠(あんきょ)となり、その後埋め立てられてしまいました。

「不忍池─水面にうつる江戸から東京」展の資料
Q:鴎外の代表作『雁』では、不忍池で雁を捕える情景が印象的に描かれていますが、今日不忍池にはどのような鳥が飛来しているのでしょうか。不忍池界隈の四季についてお話し頂けますか。
不忍池では秋から春にかけて色々な水鳥を見ることができます。今日では一番目立つのはユリカモメでしょうか。ユリカモメは秋頃より不忍池の周囲を飛び始めます。池の柵にずらりと並んで休む様は冬ならではの光景です。また、現在上野動物園内にある不忍池北側、鵜(う)の池で飼育されているカワウですが、南側の蓮池(蓮が群生する地域)でも見られます。ユリカモメやカモが飛び始めると不忍池の秋の訪れを感じます。( ただしカワウは、1年を通して池にいる鳥です)
その他にも、冬の時期にはマガモ、キンクロハジロなどの水鳥が姿を現します。不忍池ではこれらの鳥を含めて14種類の鳥が観察できまると言われています。平成31年(2019)3月の資料館前の蓮池では、ユリカモメ、ダイサギ、アオサギ、オオバン、マガモ、カワウが確認できました。また開花した桜の木にはヒバリやメジロも飛来しています。
森鴎外の『雁(がん)』を読まれて「不忍池に雁は飛来したのですか」と質問される方もいらっしゃいますが、元は雁は日本全域で確認されていた鳥でした。明治時代に猟が解禁されて以来乱獲されたため、その数を大きく減らし、保護の対象となりました。『雁』が書かれた明治時代にはまだ数多く飛来していたと思われます。現在では、北海道と宮城県にのみになったようです。
明治期の装い
Q:江戸時代から明治時代になり、装いや生活の変化はあったのでしょうか。
まず服装については、洋服は入ってきてはいるものの、一部の特権階級の人たちのみのものでした。当時の学生や警察官などの制服に洋服は取りいれられてはいたのですが、庶民は昭和時代前半頃まで和装が中心だったと思います。化粧について、一番大きな変化は、お歯黒(おはぐろ)が無くなった事でしょう。(右段に続く)
江戸時代のお歯黒の化粧は既婚女性の印でしたが、明治時代になると、あまりよろしくない慣習という事になり、無くなっていったようです。
日本髪については、昭憲皇太后(明治天皇の皇后)が日本髪は洋装に合わないという事で、自ら率先して髪を結う事をやめられた話は一般的に知られているのではないでしょうか。また、日本髪は一度結うと長時間髪をほどかないので洗えないため、細い櫛目の櫛で髪を梳いて汚れを落としていました。そのため、庶民も徐々に簡易な結い方をするようになったようです。束髪(そくはつ)ですとか庇髪(ひさしがみ)ですね。

解かし櫛(とかしくし)や結櫛(ゆいくし、髷(まげ)を結うために用いた櫛)等が、日本髪に用いられました。(台東区立下町風俗資料館蔵)

束髪に結った女性。小説『青年』では、娘から夫人まで束髪に結った姿が描写されています。(明治38年(1905)頃、『台東区立下町風俗資料館 図録』から)
Q:洋装にも合うような髪型になったのですね。
そうですね。女学生などはお下げにしたり、そうした所からどんどん変わっていったと思います。
Q:最近では、大学の卒業式等で袴を着用する女性が多いですが、当時の女学生と同じ装いなのでしょうか。
女学生だけなく、当時の女性の先生も着物に袴姿でした。もう少し時代が下がると、宝塚や松竹でも制服として着物に袴を履いていますが、そうした影響があったかと思われますね。
Q:小説『青年』では、主人公の小泉が「薩摩絣(さつまがすり)の袷(あわせ)に小倉(こくら)の袴を穿いて、同じ絣の袷羽織を着ている。被物は柔らかい茶褐(ちゃかつ)の帽子で、足には紺足袋(たび)に薩摩下駄を引っ掛けている」というような書生風の装いを描写していますが、男性の装いはどのように変化したのでしょうか。
当時の書生の年齢からすると、10代後半から20代前半という一番周囲から影響を受けやすい年代だと思いますが、おそらく動きやすいというのもあるでしょうし、服装を自由に考えられるようになったため、このような装いが定着していったのではないかと思います。袖口からシャツが見えている絵がありますが、上は普通の着物ですがその下にシャツを着ていたりなど、和洋折衷になっているように思います。

丈の長い書生羽織を着た学生たち(明治30年頃、『台東区立下町風俗資料館 図録』から)
明治期の交通
Q:当時の街の交通事情はどうだったのでしょう。
上野界隈には鉄道馬車が走っていまして、この鉄道馬車が新橋から上野を通り浅草に回って、また新橋に戻るというコースだったのですが、そうした事もあって比較的交通の便が良く、いろいろな所に行く事ができたようです。今のような四輪の自動車等はまだまだ数少ない時代だったので、公道は人力車や荷車が走っていました。
Q:鉄道馬車とはどのような構造なのでしょうか。
馬車がレールの軌道を走って、それを馬が引きます。要するに現在の路面電車みたいなものですね。鉄道馬車の廃止後に路面電車が走るようになりますが、ほぼ鉄道馬車の線路の上をなぞるような形でした。そこからどんどんと東京のいろいな方向に広がっていきますが、上野と浅草間を走る電車が最も古く、明治時代は交通の要所でした。浅草寺があるという事や、博物館等がある事に加えて、最も大きな要因は鉄道の上野駅が開業して東北や常磐方面に行く事ができるようになったからです。たとえば西から電車に乗って新橋に来て、そこから鉄道馬車に乗って上野で乗り換えて東北に行く、あるいは上野や浅草で降りて観光するというような時代だったかと思います。

明治38年(1905)の上野駅南口。上野駅は明治16年(1883)の開業以来、東京の交通の要所として重要な役割を果たしてきました。(『台東区立下町風俗資料館 図録』から)
Q:鴎外の作品にも、人力車がよく出てきますが。
人力車は色々な所に行く事ができますから、近場の移動には多かったのではと思います。樋口一葉(ひぐち いちよう)の作品にも人力車は出てきますね。『十三夜』という作品では、主人公のお関が人力車に乗って自分の家に帰るのですが、その車夫がお関の昔の思い人だったという、読んでいると泣いてしまうような話があります。人力車は明治時代の、今で言うところのタクシーという感じでしょうか。人力車は浅草発祥なんですよ。今、本資料館一階の展示室前にも人力車を展示していますが、明治初期に日本で発明されたものです。

明治期の近代化には、その多くが欧米から輸入されましたが、人力車は国内で誕生しています。小説『ヰタ・セクスアリス』では、主人公が料亭からの帰りに人力車を遣う情景が描かれ、物語の展開に大きく関わる事になります。(『台東区立下町風俗資料館 図録』から)

台東区立下町風俗資料館学芸員の本田弘子さん

台東区立下町風俗資料館(台東区上野公園2-1)