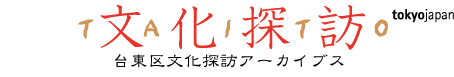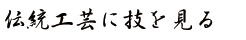Q: 現在の台東区伝統工芸振興会の活動について、お話し頂けますか。どの程度の業種の方が参加されていますか。
江戸下町伝統工芸館を拠点として集まって活動しています。自分たちで考えてこれを変えなければという事がなかなか出来ないのが職人の現状です。本館で作品を展示してると、陽は射さないのですが、変色したりします。簾(すだれ)や銀器や銅器なども、空気に触れると変色してしまいます。そのようなこともあって、時々展示を変えるのですが、その際に工夫をしたり、新しい製品を考えたりする機会にもなります。伝統工芸と言っても、私たちが製作しているものは日常使用するもので、いわゆる美術工芸ではなく生活工芸ですから、その時代に即したものとして創意工夫しなければなりません。
参加している会員の業種も時々に応じて変わりますから、一概に言えませんが、基本的には東京都が指定している40品目。その中の26品目は台東区にもあります。40品目の中でないのは、村山大島紬、本場黄八丈、多摩織などは地域にも関係していますので、台東区にはありません。染織にはやはり水を使いますから、例えば落合(新宿区)では石神井川の流れがありますから沿線には多くありました。台東区でも、谷中には昔は川があり、その周辺は藍染め町と言っていましたから、染織も少しはあったとは思いますが。(下段に続く)
Q: 台東区には、袋物を製造されている方がおいでになりますが、基になる染織がないのですか。
袋物製造は、比較的近年になってからです。26品目と言っても、代々引き継がれたものもあれば、近年若い方が加わったものもありますから。工芸などではよく後継者がいなくなると言われるのですが、その業種の需要があれば無くならないのです。需要があれば、仕事が成り立ち後継者も育っていきます。
シャッター街のようになった商店街などで後継者がいないという話がありますが、例えば夫婦で商いをしても売り上げはおおよそ決まってしまいます。その子供が大きくなって一緒に商いをしようと言っても、二世帯では出来ないのですよ。ですから、必然的に後継者はいなくなってしまいます。台東区でも、辞めてしまう方もいて、伝統が途絶えてしまう事も多くありますが、一方ではやりたいという方も結構います。代々の家系ではなくて、弟子入りされる方もいますが、実際に生活していくのは大変です。趣味でする分には良いのかもしれませんが、美術学校などを卒業しているのでしたら、また他に仕事があるのではと思います。どうしてもやりたかったら、やっても良いのですが、それなりの心構えが必要です。若い人も入ってはいますが、段々生活の事が分かってくると4、5年で辞めてしまう人も多いです。
根本的に物が作りたいという本能ではないけれども、泥棒心と大工心が必要でしょう。泥棒心というのは、10万円が落ちていれば、誰もいなくても拾うし誰がいても拾うでしょう。それはやれっていうんじゃなくて自主的にやる事です。大工心とは、自分で作って完成させてみたい、作り上げたいっていう心です。これは、人によってまちまちです。やりたいのは誰しも思っているんです。ですから、台東区伝統工芸振興会の事業として、上野の博物館や区内の小中学校、そして台東区の浅草文化観光センターなどの様々な場所で製作実演をして、また製作体験もしてもらっています。台東区以外でも、台東区の姉妹都市の宮城県大崎市でも、すでに20年程も催しています。他にも友好都市の福島県会津美里町、南会津町、山形県村山市などでも行っています。子供たちが、ものすごく喜んでいます。(右段に続く)
Q: いわゆる工芸復興運動みたいなものですね。組織を大きくしようというような事はないのですか。以前、九州の八代市(熊本県)の竹工業を取材した事がありました。昔から工芸が盛んな地域でしたが、戦後に国の指導などで素材をプラスチックに換えて、生産性を高めるようにしたそうです。そうする中に、中国の製品が多く輸入されるようになり、再び伝統的な竹工芸の技術を回復しようとしても、すでに失われてしまっていて、結局多くの職人さんは仕事を辞められてしまったというお話でした。保養地の別府周辺には竹工芸はまだ幾分残っているんですが、本来竹が豊富にあっても技術が無ければ、再び作る事は出来ないというお話でしたが。
工芸復興運動ではありませんが、地方に行っても製品や販売店はどこにでもあるでしょう。食物も何でもあります。けれども、無いのは伝統工芸です。伝統工芸は生活工芸であり、また職人にとっては生業なのですよ。需要が無くなれば、辞めてしまう商売です。ですから、組織や会社として大きくする必要はありません。自分が作った分だけで生活していければ良い。確かに、竹工芸はプラスチックなどの新素材の影響を受けていますね。台東区でも残っているのは、需要が途切れずにあったからだと思います。今では、単に観光地だからという事でもなくて、ずいぶん遠い所からも来て下さる方がいますし、展示している刃物であれば錆びたりしますからお安く譲っています。販売会ではありませんが、10年近くオークションなども行っており、年に2回開催しています。最初は思いつきでしたが、今は事業として年に2回催しています。本来は入手が難しいものが手頃な価格で入手出来ますから評判は良いですね。高価であるというよりも、良いものを安く買う事が出来るという事ですね。
私たちが製造しているもの、つまりは日本で作られている工芸品は、世界のものと比較してどのように違うかと言いますと、使い捨ての製品ではないのです。永く使う事が出来るのです。それに業種や種類が多いという事は、日本の工芸というのは一目的一品種で作るからです。例えば、出刃包丁から刺身包丁、アサリをむく包丁というように包丁の種類が多い事からも分かります。鍋にしても、数多くあります。昔ながらの鍋の他に、ミルクパンからフライパン、片手鍋というように様々なものがあります。これは、やはり日本特有だと思います。一目的に一品を作る事が出来る国は、それほど多くはありません。海外から日本を訪ねられた方や興味がある方が度々来られて、やっぱり日本の製品はすごいな、こんな物にまでこんなに丁寧に作るんだからと言われます。(下段に続く)
Q: そのように関心を持たれて居着いた方はおられますか、また、どこかと連携して指導された事もありますか。
新しく居着いた人というのは多くはありませんが、興味があってやってみたいという人はかなり多くなりました。また、こちらもこれまでの経験を積んでいますから、体験して頂く際の指導も上手になっています。東京藝術大学とも、3年間程連携した事がありますね。東京藝術大学学長の宮田さんが、一生懸命音頭を取られました。面白かったですよ、簾(すだれ)のドレスを作る人もいたし、若い人の発想はすごいですよ。鼈甲(べっこう)の指輪や、提灯にしても大根型提灯、人参型提灯などと、私たちが技術を話してこのような技術や手順で製作するというように説明すると、じゃあこんな発想で出来ないかというように提案を受け、共同で作りました。(次ページに続く)