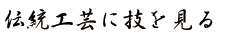Q: この江戸下町伝統工芸館は、浅草でも浅草寺の裏手で少し離れていますが、観光の観点からはいかがですか。
観光というと、どうでしょうか。台東区は他の区と密度が違って観光名所も多いのですが、まずパリだとか、ロンドンだとか、他の都市と比べて外国人の方が日本に来る機会が少ないですよね。パリが1位だそうで、日本は19位程度かな。東京に来て頂きたいというセールスのツアーに参加した事がありました。東京ってのはこういう街ですよと、色々な所に行って宣伝しました。ロンドンやパリ、ロサンゼルス、オーストラリアと、行ってみるとすごく面白かったですよ。日本にはコンピュータや電気製品などの最先端の物も数多くありますが、他の国にないのは、やはり日本の伝統工芸だけです。世界に誇れて日本にしかないと言えるのは伝統工芸ではないかと思います。
Q: スウェーデンやフィンランドなどでは、昔からの古い伝統木工芸を伝えて、また新しい物も作っていますね。そしてこれらを資産としてデザイン大国として売っていこうとしていますが、日本も工芸で売っていくような方法は難しいでしょうか。職人さんも減っているのでしょうか。
日本は宣伝が下手ですね。刃物と言えば、やはり日本が最高でしょう。例えば、ヘンケルという会社の中でも一番良い製品を販売しているのが、ジャパンヘンケルです。ヘンケルが、日本に依頼して製造しているヘンケル製品が、最も良い製品として選出されています。けれども、業種は減ってきましたね。生活様式が欧米化してきたため、需要が無くなっています。そのため、伝統工芸も少しずつ変わっています。そうでなければ、生きていけないですから。
Q: 都の伝統工芸士制度について、お話し頂けますか。
この制度は、私が発案者なんです。私が伝統工芸士の第一号ですから。伝統工芸の職人さんでずいぶん高齢の方が文化勲章などを受勲されているのを見て、若い時だったらもっと良い仕事が出来たかもしれないと思い、東京都に働き盛りの45歳から60歳程度の人を伝統工芸士に推薦する制度を創って下さいと提案したんです。
時折、修理の依頼に古い製品がきますが、それを見ると大変な技術の物があります。どの程度の年を経ているのか分からないのですが、昔の人はこんな仕事をしたのか。すごい人がいたんだなって思いますね。こちらも職人だからといい気になっていてはいけない。その研鑽の一助として伝統工芸士が役立てばと思います。昔はそういう事を教えてくれるような人が多くいましたね。いわゆる目利きの人が一般の方にもいました。今では、ちょっと仕事していると先生だとか言われて駄目になってしまいます。昔は、もっと色んな事ができるのではと教えてくれるような人がいて励みになっていました。(右段に続く)
Q: 技を伝えるために、どのような活動をされていますか。
修学旅行などで訪ねてくる生徒さんも多くいます。自分で実際に作ると、思いが強く残るのです。私の工房では竹の紐などもありますから、それを編んでランチョンマットみたいなものを作る事が出来ます。
また昔の定時制学校のように、体験学習を行っている所もあります。定時制というのは夜間ではないのです。いわゆる三部制です。朝に学ぶ人、昼に学ぶ人、そして夜に学ぶ人がいます。社会人の方も多くいますね。日を決めて、昼から夜9時まで教えています。現在4名いますが、作業の合間に少し休もうかと言っても休まないんですよ。少し休んでも、またすぐ始めます。何で休まないのって聞くと、面白いからと答えます。面白いから休めない、勉強もこういう風に面白かったらなあという子が多いです。やっぱり興味を持つ事が一番です。学校の先生なんかも調べにきて、興味を持つと虜になってしまう人もいます。先生を辞めて職人になりたいと言う人もいます。でも、止めるんですけれどね。
東京藝術大学でも結構行いました。私たちでは到底発想出来ない若い人の思いがあり、素晴らしかったです。若い学生達の作品を区の生涯学習センターで展示したところ、作品を欲しいというお客さんもいました。若い人が、これらの伝統を継いでくれると良いのですが、職人を生業として生活していく事はなかなか大変です。東京藝術大学がある谷中や近くの下谷には、金や銀の職人さんが多くいます。台東区になぜ多いかというと、錺(やすり)道具などを製造している職人が多くいるからです。道具が無くなれば、その技も無くなってしまいます。
Q: 台東区には、どのような工房や職人さんがおられたのでしょうか。今は、どのようにされているのでしょうか。
田河水泡さんという画家がいましたが、高見沢という版元の生まれでした。お父さんが版元で、絵描きに絵を描かせて、彫り師に彫らせ、そして摺り師に摺らせて、ご自身が版元として販売していました。そのせいか、田河水泡さんは、幼い時から漫画が好きで描いていました。谷中には、いせ辰さんのお店もありますが、ここも昔は版元でした。千代紙も版画のひとつで摺ったものですから、海外では大変人気があります。海外の人も見る目を持っています。裏返して見ては、また触っています。日本人の観察力よりも断然ありますね。