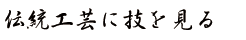台東区伝統工芸振興会会長の田中義弘さん

背中の「傳(伝)」の紋から伝統への心意気がうかがえます。
Q: この江戸下町伝統工芸館は、どのような経緯で設立に至ったのでしょうか。
今は私たちは台東区伝統工芸振興会という団体に所属しています。伝統工芸というのは本来は個人や家内での仕事なので、伝統工芸を紹介し交流する場が必要だと思い、昭和50年(1975)頃に仲間5、6人程度で始めました。その後に、徐々に広がっていき、現在は80名程になりました。
昭和55年(1980)頃に浅草の松屋百貨店で『現代版職人づくし』を開催しました。その当時の店長は、東武鉄道の浅草駅駅長さんの息子の森民雄さんでしたが、子供の時期から浅草界隈が遊び場で、遊び仲間にも職人となった人が多くいました。森さんが松屋に勤められていて、その縁で昔の仲間とも交流を深められるようになりましたが、時が経つにつれて職人もずいぶんと減ってしまいました。森さんが店長になった後に集大成として『現代版職人づくし』が松屋で開催される事となりました。私たちの仲間の5、6人も森さんと交友があったため、参加しました。墨田区では、当時の区長さんが職人さんや町をもう一度日の当たるようにと呼び掛けて区役所で職人を集め始めていました。一方、台東区では私たち区内の職人が自発的に活動を始めていました。それが、昭和55年頃の第一回目の展示会開催につながりました。また結束を固めるために「台東区伝統工芸振興会」の前身である「台東区伝統工芸保存会」を、昭和56年(1981)に結成して台東区役所にも支援を要請しました。支援を受けているだけでは駄目なので自分たちで頑張らないとと言っている頃に、浅草ひさご通り商店街にあった乾物屋さんが移転するとの事だったので、その跡地を台東区が譲り受けて、当時の区議会議長の石渡さんの応援もあって、この江戸下町伝統工芸館が出来ました。 (下段に続く)
Q: 現在、台東区伝統工芸振興会に参加されている方はどの程度ですか。また伝統工芸品とはどのように都に指定されるのですか。
多い時には、100人程です。今は亡くなった方もいますが、新しく若い方も入っています。また台東区内だけでなくて近隣の区の方も良いという事で参加頂いています。
伝統工芸の品は、東京では40品目が指定されています。伝統的な技術、または技法である事、手により製作されているもの、そして伝統的に使用されてきた原材料を用いている事などで、以上の要件を備えていなければ伝統工芸品とは言えません。また、国の指定する伝統的工芸品も同じような要件があります。
例えば原材料では、木材では松、檜(ひのき)は古くから工芸に用いられた材料ですが、ベニヤ板は新しい素材なので使えません。また金属や非金属では、金、銀、銅、錫などは良いのですが、アルミやニッケル、そしてプラスチックや樹脂などの新しい素材は違いますね。それから繊維では、綿や絹は良いのですが、化学繊維は違いますね。このように古くから続いている伝統技術や歴史を維持する事を重んじています。
Q: 新素材を用いるという事は、まったくないのですか。
それは、順じてありますよ。例えば、外見として見えないところ、指物でいうと見えない作りや箇所では、ベニヤ板などを使う事もあります。私の工房で手掛けている簾(すだれ)では、そのような表現はあまりないのです。現代風の表現として新素材を用いる試みもしていますが、やはり伝統的な素材は竹や葦(よし)などの国産の素材ですね。 (右段に続く)
Q: 江戸風、江戸モノとよく聞きますが、どのようなものなのでしょうか。
江戸時代からの伝統や表現は流行のようにしてありましたから、例えば、江戸前寿司などのように江戸で作られるモノという事で用いたのだと思います。元々は京都が日本での工芸や染め物の中心で、後に江戸に伝わってきたのですが、やはり少し表現が変わっています。簾(すだれ)を例としますと、京都の地形は盆地で夏は大変暑いので、部屋を暗くする事が一種の涼しさの表現となります。そのため、簾は上から下までびっしりと掛けて、下は床に垂れて膨らんでしまう程に重く長くしています。一方江戸では、辰巳の方向に東京湾や隅田川があり、涼しい風が吹き込んでくるので少し短めに華奢に作ります。そうすると風にそよいで揺れるので、風が見えます。本来風は見えないのですが、風があるのがわかる。江戸は外をきれいにするのですが、京都は中をきれいにすると言わています。だから表現もまるで逆です。建物全部の造りもそうなんです。
Q: 江戸風は、京風とはずいぶん雰囲気が違っているという事ですか。
そうですね。それはだいぶ変わっていると思います。日本の伝統的な表現や造りは、元は京都から伝わったものが確かに多いのですが、地域や風土の違いに合わせて表現も変わります。例えば、京塗りの漆器では、京都ではきれいに塗る事ができるのですが、関東では空っ風が吹きますから、乾燥しているため、本当の意味の漆塗りはできないんです。他のものは普通は風や日光で乾きますが、漆だけは湿度で乾くと言われています。そのため、漆工芸はやはり京都が中心になっています。他の漆系統の工芸では石川県の山中や福島県の会津などの、いわゆる盆地の風土が適しています。
また寸法なども変わってきます。例えば京都の一間は、柱の内から内で一間、東京の一間は柱割りと言って柱の芯から芯までを測ります。畳で言えば、京間(本間、一間6尺3寸(1910mm))、中京間(一間6尺(1820mm)の畳割り(畳の寸法を基準にして住宅を設計する))、江戸間(一間6尺、柱割りのため、畳は5尺8寸(1760mm))と違っています。そのため、東京で製造したものを京都に持って行くと、合いませんでした。今日では、これらを前提に製造していますから、そのような問題はないのですが。
Q: 以前工芸や家具製造の職人さんに伺った際、未だにセンチメートルではなく尺寸を使われているとの事でしたが、伝統工芸ではいかがでしょうか。尺貫法の廃止により、問題が多くあったとの事ですが、現在ではどうでしょうか。
注)尺貫法は、東アジアでは広く用いられていた長さ、面積を表す単位系だが、日本では計量法により昭和33年(1958)から昭和41年(1966)に掛けて廃止された。ただし、伝統的分野での使用は認められている。日本での1尺(市尺)は約303.030mmとされ、中国では約333.333mm(公尺)とされている。
私なんかは尺寸の方が頭に入っていますが、両方使いますね。けれども、戦後は一番困りましたね。戦後は進駐によりインチが用いられたため、ずいぶん寸法が狂ってしまいました。インチを尺やセンチメートルに直して製造していましたが、どうしても端数が出てしまいます。今でも尺の物差しは便利なので使っていますが、例えば三つに分けるなどの計算は簡単にできるんです。でもセンチだと計算しなければいけません。
Q: 今でも京風とか江戸風では、それぞれが指す雰囲気は違いますか。江戸で発展し成長した工芸はありますか。
例えば、茶道や茶道具などは、やはり京都を中心に生み出されたものですから、京間を前提としていますね。江戸では、夏の涼しさを得るために浴衣などが生まれていますね。小紋などでも江戸小紋と京小紋は少し違いますね。デザインや染織が地域の特性に合った独自の発展をしています。その他の工芸でも、このような違いがありますね。(次ページに続く)

台東区伝統工芸振興会会長の田中義弘さん

背中の「傳(伝)」の紋から伝統への心意気がうかがえます。