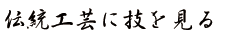江戸和竿(吉田 嘉弘)
江戸和竿(吉田 嘉弘)
昔は、台東区に限らず、竿屋さんは多かったですよ。今では、新素材を使用したり、洋式の新進の企業も増えました。台東区内では、昔ながらの手作りの有名な竿屋さんがありますが、船竿が得意な人、ウマヅラハギ釣り用が得意な人、タナゴ釣りやアユ釣り用が得意な人と、それぞれに違いがありますね。本当は、自分の得意な物で、互いに競争した方が良いのですが、世の流れで、仕方がありませんね。
江戸漆器(大塚 泰)
これは漆器です。東京は蕎麦屋さんが多かったので、東京の塗り物というと、蕎麦の蒸籠(せいろ)と寿司の飯台などは江戸の漆器を指しますね。
東京打刃物
こちらは、革細工のための太刀包丁です。このようにそれぞれの用途に合わせた刃物や包丁が製造されていました。こういう物を製造する人は、専門家、専業家になる人もいます。最初は包丁全般を手掛けていても、例えば畳製造のための包丁の依頼が数多くくるようになると、畳包丁が得意になります。
様々な和室金具
和室金具・釘隠し(堀口 宏)
家屋や室内の錺(かざり)金具ですが、襖や家具、家屋の錺や釘隠し金具として用いられてきました。それほど多くの需要が無いのですが、このようなものほど、残さないといけませんね。今では、襖を入れている家屋も少なくなってしまいました。
江戸袋物(藤井 直行)
これは牛革の袋物ですね。他にも革を重ねて作る合切袋があります。合切袋は、元々は煙草入れなどとして作られていました。
鋏(はさみ)(川澄 巌)
鋏(はさみ)(川澄 巌)
昔は、洋裁学校などでも、ずいぶんラシャ鋏などが使われていたのですが、最近では需要も無くなりました。これらは植木や花の剪定鋏ですね。 (右段に続く)
鑢(やすり)(深沢 敏夫)
この長い鑢(やすり)は、刀の鞘を作る時に用いられる道具です。手術の時に骨を削ったり、特殊な鑢が多くあります。この人は、職人の中でもいわゆる絶滅危惧種の朱鷺(とき)だと言われています。それほど、貴重な業種です。
おろし金(大矢 茂樹)
江戸刷毛(小林 誠)
これは調理用や化粧用の刷毛ですね。刷毛にも様々あります。お好み焼きのソースを塗る刷毛もありますね。このような物は最近ではずいぶん増えましたが、障子や襖を貼るための刷毛などは、需要が無くなりました。版画の刷毛や絵筆などもありますね。漆塗りの刷毛は人毛ですが、金泥で文字を描く時の筆は根朱筆(ねじふで)と言って鼠の毛だそうです。
江戸簾(すだれ)(田中 義弘・耕太朗)
江戸簾(すだれ)(田中 義弘・耕太朗)、東京仏壇(下段の右側 遠藤 利之)
簾は一般家庭でも、このように用いると分かるように展示しています。また、掛け軸として特殊な物も作っています。本来は、天麩羅だとか鰻(うなぎ)だとか、文字を透かして抜く仕事が多かったのです。というのは、江戸時代の筆記具は墨だけでしたから、ペンキはありません。墨は濡れると落ちてしまいますから、それでこのように簾に透かして文字を描いていたのです。木彫看板や簾がそのような用途から用いられていました。簾の場合は、湿度があっても、乾燥しても長さが伸びたり縮んだりしないために、竹、それから葦(よし)材などが用いられました。
竹は、国内でも材料が多く入手出来ますし、ずいぶん重宝されてきたのですが、近年プラスチックなどの新素材が増えてきました。提灯の籖(ひご)などは、竹籖を使っている所はもう少なくて、ほとんどがプラスチックや針金になりました。プラスチックや針金は機械で加工すれば簡単に紙を貼る事が出来ますから。簾は、材質としては合いません。木や新素材は細かく刻むと反ってしまいます。大正の終わり頃の一時期には、板簾と言ってベネチアン・ブラインドを真似たような製品が登場してきました。椹(さわら)の柾(まさ)目材だと反らないので用いられていましたが、次第に材料が品薄になり、他の木材を使うようになって反ってしまい、次第に減ってしまいました。簾は、茶室や寺社などでも多く用いられます。寄進する人も多くいます。簾だけでなくて葦簀(よしず)の障子なども、近年の和風好みへの回帰かもしれませんね。このような製品は、使っていくうちに風合いが出ますし、壊れたら直して永く使う事が出来ます。