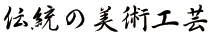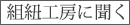桐生堂
江戸組紐桐生堂(株式会社桐生堂)は、明治9年(1876)創業の組紐工房です。台東区浅草に構える組紐、和雑貨の店舗には、国内外の観光客が引きも切らず立ち寄り、日本の工芸品の紹介の場ともなっています。(台東区浅草1丁目32番12号)

角台による組紐製作、大型の羽織紐が組まれています。
今日の組紐には、多様な製造方法と共に様々な用途があります。和装のための帯締め、羽織紐、袋物、日本刀の拵(こしらえ)の他、アクセサリー等にも用いられています。組紐製作の多くは手組み、手作業のため、組紐は手間を掛けて、丹念に、また精緻に組み上げられます。糸、色、組み方により組紐は様々な表情を見せます。紐を組む方法は国内外を問わず多様にありますが、多くは組台(くみだい)を用いて組まれます。以下のような代表的な組台と組み方が用いられています。
角台(かくだい)
角台は、角形の鏡(上板)、台板、組み上げた紐を吊る滑車等が付けられた構造の組台です。玉数が少ない紐組みに用いられますが、四つ組(4玉で組まれる基本的な組み方)、八つ組(8玉で組まれる丸紐)、丸唐組(組目を交差させた丸紐)、平唐組(丸唐組と同じ組み方による平組)、鴨川組(日本独特の組み方で強い撚り(より)を生む組み方)等と多様に組む事が出来ます。
丸台(まるだい)
円形の鏡(上板)、足、台板からなる組台です。鏡中央の穴から組んだ紐を吊り下げる構造になっています。玉数が限られるため、複雑な組紐には適していませんが、簡単な組みから複雑な唐組まで使用し得る組み台です。冠組(冠の緒に用いられた組紐)、 丸源氏組(色の異なった糸で矢羽根柄を表現した組紐)、平源氏組(丸源氏組を平たくした組紐)、洋角組(八つ組紐を芯に杉葉様に組まれた組紐)、御岳組(角八つ組や洋角組を束ねて連結した組み方)、唐組(矢羽根柄を表す笹浪組の変形)等の組紐製作に用いられます。
綾竹台(あやたけだい)
木枠に矢羽根型の棒を掛けた構造の組台で、経糸(横糸)を掛け、上下の経糸の間に緯糸(縦糸)を入れて、ヘラで打ち込みながら組み上げます。平組で多様な柄作りに適した組み台です。
高台(たかだい)
大型の木枠に左右2段に付けられたコマに玉を掛け、綾書きと呼ばれる組み方で、竹製のヘラで打ち込みながら組み上げます。上下2段の糸の色を変えて柄出し(柄を描く事)が出来ます。複雑な柄出しに適しています。高麗組(緻密な目が詰まった柄を作る組み方)、大和組(表裏の色や柄を変えた組み方)、笹浪組(笹や浪の波状の柄を作る組み方)、貝の口組(貝が口を開けた様の、亀甲とも類似した柄出しの組み方)、安田組(あんだぐみ、格子状に組む組み方)、内記組(安田組を表裏に組み合わせた組み方)、畝打組(高麗組を連結した組紐)等の多様な組み方が出来ます。丸台と共に多用される組台です。
内記台(ないきだい)
歯車により糸を掛けた木の葉状の板を回転させながら組み上げます。江戸後期に開発されたと言われる半自動的な組み作業が可能な組台ですが、複雑な構造のため、今日ではほとんど用いられる事が少なくなりました。

平組の羽織紐

羽織紐の結び方

桐生堂
江戸組紐桐生堂(株式会社桐生堂)は、明治9年(1876)創業の組紐工房です。台東区浅草に構える組紐、和雑貨の店舗には、国内外の観光客が引きも切らず立ち寄り、日本の工芸品の紹介の場ともなっています。(台東区浅草1丁目32番12号)