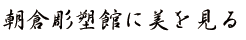公益財団法人 文化財建造物保存技術協会の樋口崇さん
公益財団法人 文化財建造物保存技術協会の樋口崇さんにお話を伺いました。
Q: 朝倉彫塑館の特徴とは、どのような点でしょうか。
樋口 : 朝倉彫塑館は、昭和3年から10年までの、実に7年間の期間を有して建築されています。7年間は建築期間としては大変長い期間だと思いますが、朝倉先生ご自身が設計と工事管理に携わられているため、一般の建築家では行わないような事が随所に見受けられます。つまりは、本建築は、朝倉文夫の作品だと言えます。特長としては、竹と丸太の使用が基調となっています。竹は腰板や格子に用いられていて、丸太については、手摺り等に用いられています。コンクリート造りのアトリエ棟の手摺りでは、丸太を模したコンクリート造りの、いわゆる擬木が用いられています。(下段に続く)
また、藝術の「藝」には修練された技能の意がありますが、文字の作りには、木・土・丸(圓)が含まれていて、木と土を丸く盛って植えるという意味があります。これらの意味が、本建築の随所に散りばめられています。また、朝倉先生は、芸術家とは園芸をすべきという考えがあり、お弟子さんにも彫塑教育の一環として施していました。このような方法は、芸術の持つ藝の意味からも正鵠を得たものと思われます。本建築には、このような哲学が反映したものと言えます。(下段に続く)
今回の修復工事では、樹木、そして魚については一旦小千谷(おじや)市に引っ越してもらいましたので、半世紀余りを経た帰省という事になりました。また巨石については、一般には建物を建てた後に石を運び込むのですが、彫塑館では建物がぐるりと中庭を囲んでいるため、築後に石を運び込む事はできません。そのため、建物を建てるために巨石を運び込んでいる事が分かります。つまりは、彫塑館は建物を建てた後に作庭するのではなくて、建物と庭を同時に創られた価値が高いデザインと言えます。(下段に続く)
中庭の植栽については、1本程の樹木は白色の花を付けるのですが、百日紅(さるすべり)だけが紅い花を付けます。このような一箇所だけを外すという、いわば破調のひとつの表現であると思われます。このような表現は、建具にも見受けられます。螺旋締まり(ねじしまり)にも一箇所だけ形状が異なっているような箇所が見受けられます。朝陽の間でも赤と白という対比が用いられていて、池の樹木でも一年を通じて、何かしらの白色の花が咲くようになっていますが、この中で紅い花が一瞬咲くというような表現が用いられています。
また、アトリエ棟の外壁は黒く塗られていますが、中庭に至ると白色が見えます。ここにも、黒と白というような対比が講じられています。住居棟については、修復前には壁にもすでに新しい建材で塗られていましたので、塗られる以前の朝倉先生が意図された当初の壁の痕跡を調べました。その結果、赤砂壁、黒砂壁、繊維壁、白漆喰壁、鼠漆喰壁が用いられていました。(下段に続く)

中庭
彫塑館の中心ともなっている中庭は、作庭の常識を逸脱し、2mを超える水深の池にそれぞれの趣向が凝らされた手水石が置かれています。
Q: 芸術家としての創意は、どのような点にあるのでしょうか。
アトリエ棟の3階にある朝陽の間は、西側を壁面として東側に窓を開いています。つまりは、この部屋に入る光は朝日です。そのため、朝陽の間と言います。通常は、砂壁になりますが、この壁には瑪瑙(めのう)を砂粒の大きさにまで砕いて用いられています。これらの瑪瑙に朝日が差して赤く輝くように設えてあります。朝倉先生は、随所に色の対比を施していて、朱(赤)に比して白が無ければならないという事で、中庭に面した窓の壁は貝を用いた白色となっています。螺鈿(らでん)細工に用いられる青貝を砕いて塗り上げられています。このような表現は、他の文化財でも例が無いものです。芸術家朝倉文夫の審美眼により、過去に無かったような表現を創っているとも言えます。
Q: 造作の妙とは、どのような所にあるのでしょうか。
丸太は、随所に使われていますが、いわゆる磨き丸太と言われるものです。磨いた丸太に拭き漆(うるし)を塗り、拭き上げています。このような工程により、丸太はほのかな鈍い光を放つようになります。このようにして、最も格の高い部屋に用いるに相応しい素材となります。最も手が付けられなかった朝陽の間の天井には、水中に没していた樹齢も永きを経た屋久杉が用いられています。水中に没した木材は、やがて幹が腐り、樹洞(じゅどう、うろ)が空きますが、これらを薄くスライスし、これを杉皮で裏打ちして用いられています。これらの材料は、すでに入手できない素材です。
Q: 中庭や建物の特長は、どのような所に見受けられますか。
中庭の特長は、作庭の常識を破った深さを有した池と巨石が中心となっています。作庭の基本となっている平安時代に記された作庭記には、庭の池は淺かるべしとされているのですが、深くなると魚が肥り過ぎると言われています。元々谷中では湧き水があり、朝倉先生はこれを活かして設計されたのだと思います。最も深い所で2mを超えていますが、池に配されている飛び石の下はコンクリートでアーチ状になっています。この下を魚は回遊するようになっています。現在では鯉(こい)が20数匹、鮒(ふな)が180匹程おりましたが、朝倉先生の文集には、元々鯉は新潟から取り寄せられたと書かれています。(右上段に続く)
これらを調べると、憶測でもあるのですが、より公的な場には赤砂壁、プライベートな場には黒砂壁が用いられていたのではないかと思われますが、ここでも一箇所外すという試みがあり、朝倉先生の娘さんが住まわれていた令嬢室と呼ばれる部屋だけは赤砂壁となっていました。このように、木造家屋については、いわゆる数寄屋造りとなっていますが、その裏には遊び心や教養に裏打ちされた物語性等が含まれています。ここにも朝倉先生の遊び心が表れています。庇(ひさし)の出桁にも隠された試みが見えます。(下段に続く)
Q: 今回の保存修復工事で最も注意された点は何でしょうか。
最も心を砕いた所は、中庭の樹木でした。建物の修復工事の場合にては、建物の外側に足場を組まなければならないのですが、朝倉彫塑館は、庭園として名勝に指定されていますので、言わば庭園が重要です。そのため、名勝としての庭園の樹木を移植するという事は大変な冒険でした。そのため、移植前に、千枚を超えるデジタルデータを記録しました。復原する際には、樹木の枝振りまでも再現する事に気遣いました。保存修復では、建物では経年劣化して行くというのが通常ですが、庭園の場合は年を経て完成して行くというものです。そのため、文化財としての庭園とは育てながら維持して行くものではないかと考えています。(次ページに続く)

公益財団法人 文化財建造物保存技術協会の樋口崇さん