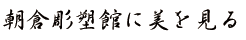松井建設の山田晴二郎さん

ピアノの間から中庭を望む。窓枠はアルミサッシからスチールサッシに復原されています。
松井建設の山田晴二郎さんにお話を伺いました。
Q: 今回の修復工事では、どのような修復が行われたのでしょうか。
山田 : 保存修復工事なので、現在用いられている材料を補完したり、不足している物については材料を調達したり、入手できないものについては、類似した材料を用います。今回は、現存する材料を再利用するという方法を用いました。そのため、一般の解体工事ではなくて、それぞれの材料を解体しながら番号を振るという作業を行っています。

Q: 保存修復の意義とは、どこにあるのでしょうか。
保存修復工事では、当時の姿に戻すという事が重要です。今回は30年代の姿に戻すという事ですので、アルミサッシとなっている箇所については、30年代当初に用いられていたスチールサッシに戻しています。使い勝手から言えば、アルミサッシを使いたいところですが、当時の材料や姿に戻すという事でスチールサッシを採用しています。朝陽の間の瑪瑙(めのう)壁については、大変高価な材料のため、壁を取り壊すという事ではなくて表面を薄く剥ぎ取る方法を用いています。鑢(やすり)状の道具を用いて、瑪瑙の部分だけを取り除いて洗浄しています。剥落して失われている箇所については、新たに瑪瑙を調達し補足していますが、類似の材料を探す事に苦労しました。(上段に続く)
Q: 今回の保存修復工事の大きな目的とは、何でしょうか。
今回の大きな目的は木造家屋の耐震工事と、やはり昭和30年代後半の姿に復原する事が重要な課題でした。耐震工事については、今回の工事の結果がまったく見えないという事が、最も重要な課題でした。耐震壁を用いていますので、耐震用木材を壁の内部に入れていますが、厚みが出来てしまいます。木造家屋は、数寄屋造りで元の壁が大変薄く造られていましたので、これらの厚みを感じさせないような工法が重要でした。壁を薄くして耐震補強をする場合は、使用する釘の本数を増やさざるを得ません。壁一面であれば、周囲に多数の釘を打たざるを得ませんが、今回の修復工事では壁面を六分割程に分けて、それぞれの部分を釘で留める作業をしており、出来るだけ釘の本数を少なくして仕上げています。このような方法で、薄い壁でも耐震性を持っています。
Q: 文化財としての耐震補強工事の難しさとは、どのような所にあったのでしょうか。
耐震補強工事の場合は、一般に基礎を掘って鉄骨を入れて補強しますが、家屋は文化財ですので、これらの工法を用いる事が出来ませんでした。そのため、今回は基礎と家屋部分の境に薄く鉄骨を組み込む方法を用いています。天井については耐震ブレースという鋼材を入れ、屋根裏には木材の筋交いを入れています。
担当した職人さんからも、こんな材料を見た事がない、こんな材料を使った事がないという声もあり、大変勉強になったとの事でした。今回の解体工事期間中に東日本大震災がありましたので、このような災害にも耐え得るような工法を取らなければという戒めにもなりました。


松井建設の山田晴二郎さん