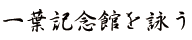三階展示室では、一葉の小説の情景を模型により再現しています 。

「玉菊燈籠模型」(三浦宏作、右)。新吉原角町(すみちょう)にあった妓楼「中万字屋」の遊女「玉菊」の霊をまつる仲之町の行事で、通りの両側の茶屋がこの燈籠を出しました。玉菊は、才色兼備の太夫で茶の湯、生花、俳諧、琴曲等の諸芸に通じていたと言われています。享保11年、享年25歳で没しました。


「玉菊燈籠模型」(三浦宏作、右)。新吉原角町(すみちょう)にあった妓楼「中万字屋」の遊女「玉菊」の霊をまつる仲之町の行事で、通りの両側の茶屋がこの燈籠を出しました。玉菊は、才色兼備の太夫で茶の湯、生花、俳諧、琴曲等の諸芸に通じていたと言われています。享保11年、享年25歳で没しました。



一葉記念館の近在には、吉原神社(上)、新吉原花園池(弁天池)跡(右)などがあります。

鷲(おおとり)神社
社伝によれば、天之日鷲命(あめのひわしのみこと)の祠(ほこら)に日本武尊(やまとたけるのみこと)が東国征伐の帰途、熊手をかけて戦勝を祝ったとのこと。この日が11月酉(とり)の日で、以後、この日をお祭と定めたと言われています。酉の市は、江戸中期より冬の到来を告げる風物詩として発展し、浅草は特に浅草観音・新吉原・猿若町芝居小屋を控え、賑わいをみせました。
社伝によれば、天之日鷲命(あめのひわしのみこと)の祠(ほこら)に日本武尊(やまとたけるのみこと)が東国征伐の帰途、熊手をかけて戦勝を祝ったとのこと。この日が11月酉(とり)の日で、以後、この日をお祭と定めたと言われています。酉の市は、江戸中期より冬の到来を告げる風物詩として発展し、浅草は特に浅草観音・新吉原・猿若町芝居小屋を控え、賑わいをみせました。

鷲神社の境内には、正岡子規の「雑閙や熊手押あふ酉の市」の句碑、俳人其角の「春をまつことのはじめや酉の市」の句碑とともに、樋口一葉文学碑(上)、師半井桃水への書簡文の碑が建っています。

師半井桃水に宛てた未発表の書簡文「玉梓乃碑」


「見返り柳」の碑
遊び帰りの客が後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この柳あたりで遊郭を振り返ったことから、そう呼ばれています。一葉記念館周辺は、「たけくらべ」の舞台ともなった神社仏閣や新吉原跡などがあり、往時がしのばれます。(台東区千束)

「見返り柳」の碑
遊び帰りの客が後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この柳あたりで遊郭を振り返ったことから、そう呼ばれています。一葉記念館周辺は、「たけくらべ」の舞台ともなった神社仏閣や新吉原跡などがあり、往時がしのばれます。(台東区千束)