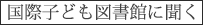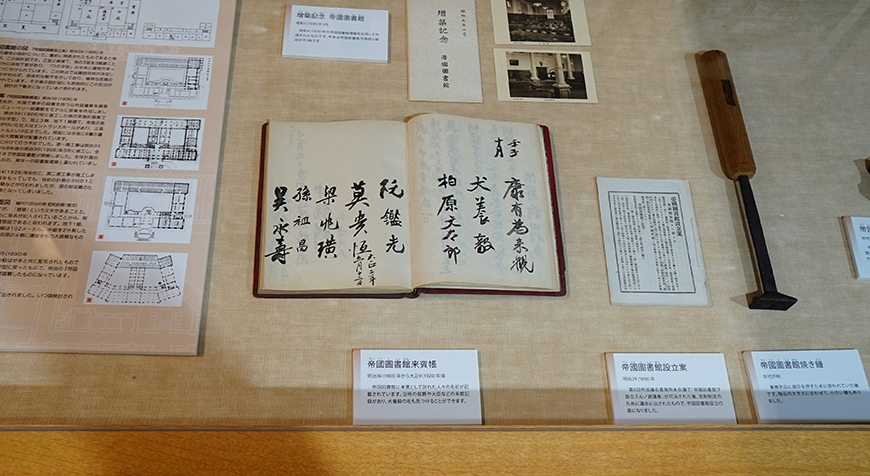旧帝国図書館について多くの文学者や小説家も、その光景を記しています。特に地方から東京を訪れた宮沢賢治は、帝国図書館の壮大さに驚き、憧れたであろう事が偲ばれます。
田山花袋、随筆集『東京の三十年』の「上野の圖書館」の項
「五銭出して、後には私は二階の特別閲覧室に行つた。大きな硝子窓、白いカアテン、外にざわざわ動いて見える新緑、キラキラする日影、その窓際で、私は終日長く本を讀んだり空想に耽つたりした。」
谷崎潤一郎『ハッサンカンの妖術』
「或る日の朝、予はあの物語を書く爲に、アレキサンダア・カニンハム氏のインド古代地理とヸンセント・スミス氏の「玄奘三蔵の旅行日誌」(The itinerary of Yuanchwang)を調べたくなつて、上野の圖書館の特別閲覧室へ出かけて行つた。・・・」
和辻哲郎『自叙伝の試み』
「初めて東京で出て来たころのことでもう一つ鮮やかな印象の残っているのは、上野の図書館である。(中略)そこで、ゆっくり落ち着いて、書物などをながめながら一日を過ごす、という仕方で経験した、すなわち世俗的な最初の大きい西洋建築は、あの上野の図書館だったのである。」
宮沢賢治『圖書館幻想』
「そこの天井は途方もなく高かった。全體その天井や壁が灰色の陰影だけで出來てゐるのか、つめたい漆喰で固めあげられてゐるのかわからなかった。・・・」
国立国会図書館デジタルコレクションより引用
(下段に続く)

小学生までを対象とした児童書が読める「子どものへや」

世界の国・地域の地理・歴史・民族を紹介する資料を通じて国際理解を深めてもらう事を目的とした「世界を知るへや」


世界の国・地域の地理・歴史・民族を紹介する資料を通じて国際理解を深めてもらう事を目的とした「世界を知るへや」

「世界を知るへや」は、旧帝国図書館の時代には貴賓室として用いられ、もっとも格式が高く、一般の利用には永らく供されることはありませんでしたが、国際子ども図書館の開館と共に開放されました。天井や壁の修復は、明治時代に用いられた貝灰、石灰、角又(つのまた、紅藻のこと)、すさ(繊維質のつなぎ材)等を混合した工法を用いて復元されました。またシャンデリアは、東京電力に保管されていた現物の部品を採寸して、真鍮に金メッキを施して復元されました。そして寄木細工の床には、明るい木目の欅(けやき)、暗めの茶色の花梨(かりん)、そして黒色の黒檀(こくたん)が美しい文様を成しています。