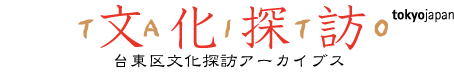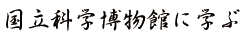国立科学博物館広報課の池本誠也さん
国立科学博物館広報課の池本誠也副課長に、お話を伺いました。
池本 : こちらは、天体観望用のドームです。この銘版や古い落書きなどが時代を感じさせてくれます。このドームがある日本館(旧本館)は昭和5年に完成しましたが、それに遅れること1年の昭和6年の10月にドームが完成して、その年の末から天体観望のために多くの人を迎え入れています。
完成時には20センチの屈折赤道儀があり、それを用いて観望をしていました。当初は手動でドームを回転させていましたので、なかなか多くの星を見るということができませんでしたが、昭和16年に電動式に改良されて一回の天文観測のイベント毎に数個の星等を観測できるようになりました。
日本館の改修に伴って、しばらく稼働していませんでしたが、平成19年の4月から再開しました。それに伴い、望遠鏡も更新して、現在では60センチの反射望遠鏡が設置されています。これらの利用で、ますます充実した観望ができるようになりました。(下段に続く)


こちらが日本館の屋上です。関東大震災当時、湯島にあった当館は全壊しましたが、その後に震災復興事業の一環として現在の地に再建されました。昭和5年に完成し、翌6年に竣工しました。震災復興事業により建てられたので、非常にがっちりとした造りで多くの鉄骨や太い柱を用いた当時の耐震技術を存分に用いて建てられています。この建物は上から見ると、当時の最先端の科学技術のシンボルである飛行機型の形をしています。ちょうど今立っているあたりが、飛行機の操縦席に相当するところです。(次ページに続く)

国立科学博物館広報課の池本誠也さん