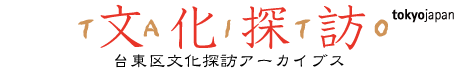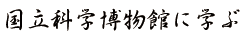携帯用日時計
こちらは「時を知る」のコーナーです。「時を知る」というのはまさに時計のことですが、日本人は昔から非常に面白い時制の決め方をして、「不定時法」というものがありました。不定時法は日本人が自然と調和しながら共に暮らしてきたことを象徴するような時制で、昼と夜、それぞれ日の出から日没までを、また日没から日の出までの時間を六分割して、それを一刻(いっとき)という単位で数えていくのですから、当然その季節によって、また昼と夜によって、その一刻の長さが違うわけです。でもまさに自然の動きに沿って時制を決めて、それによって暮らしていく日本人の昔からの自然調和型の暮らしを象徴しているシステムだろうと思います。
こちらは和時計の展示です。先ほどの不定時法は、昼と夜、または季節によって一刻の長さは違う訳ですから、特別な機構の時計が必要です。その不定時法をきちんと表示できる時計、そのような機構を持った時計が和時計です。ですから、日本人は非常に高度な技術を昔から持っていて、このように生活に応用していたのです。日本の当時の技術水準の高さをこれらの和時計は表しているんですね。そして、明治時代になりますと、不定時法は廃止されて定時法が採用されましたので、和時計は使われなくなりましたが、機械式の新たな時計製造が始まり、今日においては日本の時計産業も大きく発展して、世界をリードするような産業になっているということですね。


こちらは「微小を知る」のコーナーです。顕微鏡の技術に関する展示です。日本人が、昔から顕微鏡を使ってどのようなものを見てきたか。顕微鏡は、当初は外国から入ってきた物で外国の技術でしたが、ここでは特に日本人の自然に対する興味、関心の対象について展示をしています。例えば、日本人というのは非常に小さな物、例えば小さな蚊を見て、それを顕微鏡で見ると怪獣のようだというように驚いたりだとか、様々な物に関心を持って見ていました。ここに雪花図絵がありますが、雪の結晶を顕微鏡で見て、いろいろな結晶があることを図に表して残しています。このような興味や関心、好奇心の対象や観察技術が、時代を経るにつれて、博物学などに応用されてきました。さらに国産の顕微鏡が製造されて、今日では日本の顕微鏡製造技術も非常に高い水準にあります。
こちらには、このような興味や関心が生活にも取り込まれていた例として、雪の結晶の模様を取り入れてデザインされた刀の鍔を展示しています。このように顕微鏡で見たものをいろんな装飾に取り入れて、それがまた流行になっていくような面白い影響や効果があったことが分かります。

雪の結晶の模様が配された刀の鍔

携帯用日時計