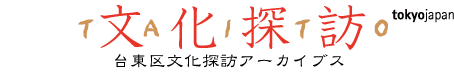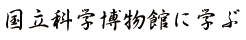トロートン望遠鏡
池本 : ここは「自然をみる技」のフロアです。日本人がどのような技を使って、日本の多様な自然の現象を捉えてきたかを説明しています。天・地・時・微小の4つのコーナーに分けて、天文、地震、時の流れ、微小と4つの分野で様々な技術を駆使して捉えてきたその歴史と、現代の科学技術立国に繋がっていった技術の進歩について展示しています。
それではまず天のコーナーからご案内します。こちらは、天のコーナーの最初のシンボルの展示です。トロートン望遠鏡と言って、明治13年にイギリスから輸入された物です。当時、明治維新政府になって、西洋の進んだ技術を使って天文観測をするということで導入された20センチの屈折赤道儀です。現在は重要文化財として指定されています。(右段に続く)
天文学の歴史の展示を見て行きましょう。こちらは「天文成象図」と言って、江戸幕府初代の天文方である渋川春海によって制作されたものです。江戸初期の日本の天文学は、中国から輸入された天文学をそのまま利用していましたが、江戸幕府の初代天文方の渋川春海が日本独自の天文学を確立するために、中国の星図に自身で観測した星を付け加えていったものです。この赤い点で書いてあるところが、渋川春海が新たに付け加えていったものですが、それがこの天文成象図です。まさに日本独自の天文学の発祥の図といえるものですね。(下左段に続く)


江戸時代の遠眼鏡(望遠鏡)を体験することができます。また、その構造も解説されています。
こちらは「日本の暦」に関する展示です。日本の天文学というのは観測天文学ではなくて暦を作る為の実学的な天文学として発展してきました。このように、江戸時代には暦を作ることは幕府の重要な仕事でした。日本の天文学は暦を作るということに科学の勢力を傾けてきて、結果としてこのように世界的にも非常に精巧な暦が作られてきた訳です。何故、幕府が暦を懸命に制作したかは、当時は権力者の権威と言いますか、「庶民に分からないものを幕府はきちんと作れるんだ」と、それがやはり幕府の威厳というものに繋がっていく訳ですね。そのような意味で、暦を幕府が一手に引き受けて制作していました。このようにして、次々と改暦を重ねて精密な暦が作られていったのです。(右段に続く)
当時の暦は、日数を計測するためには月の満ち欠けを利用して、季節の変化については太陽の動きを基にして作られています。これらは太陰太陽暦と言いますが、明治時代に入って太陽暦が採用されて、このような暦を制作する任務は終わった訳です。
当時、江戸時代は天の動きや暦を理解することは教養人にとっては非常に重要なことでした。重要な教養として考えられていて、いろいろな私塾や藩の学校などで勉強していた訳です。それでこのような天球儀などを学習教材として使っていました。これは先ほどお話ししました江戸幕府の初代の天文方である渋川春海が作った地球儀と天球儀です。重要文化財でここに常時展示することはできませんので、これらはレプリカです。(左下段に続く)

紙張子製地球儀(上、渋川春海作、元禄8年(1695))
紙張子製天球儀(下、渋川春海作、元禄10年(1697))

黒漆塗天球儀(18世紀頃)
こちらは「地の動きを知る」のコーナーです。明治に入り、お雇い外国人が多く日本を訪れて、その中には地学系の研究者も多くいた訳ですが、彼らにとっては日本の地震は大変に驚く自然現象でした。当然のことながら、科学者として彼らの西洋の科学技術を使って地の揺れを記録しようとする発想が出てくる訳で、地震学は日本から始まったようなものです。
これは「ユーイングの地震計」の復元模型ですが、このような地震計を基に日本人が新たに考え出した「大森式地震計」などがあります。(次ページに続く)

ユーイング-グレイの円盤式地震計(1880年代初め、復元模型)

トロートン望遠鏡