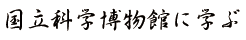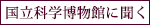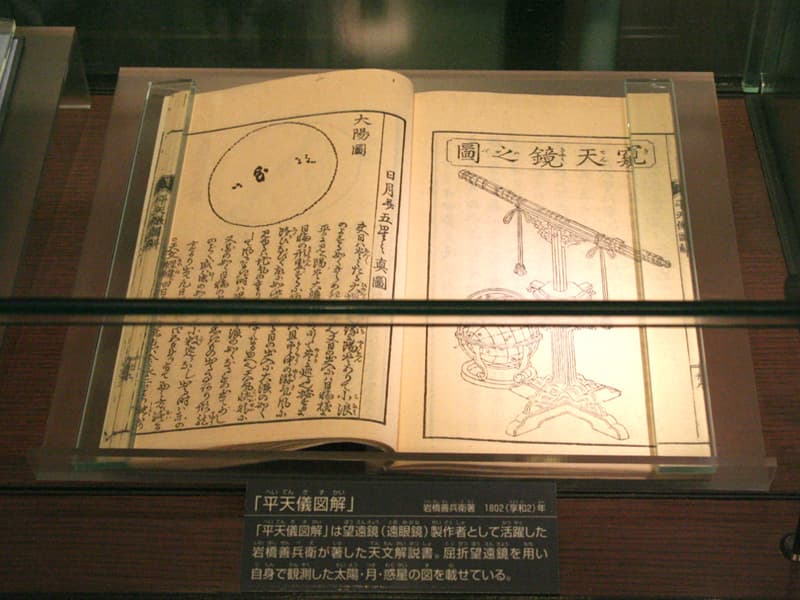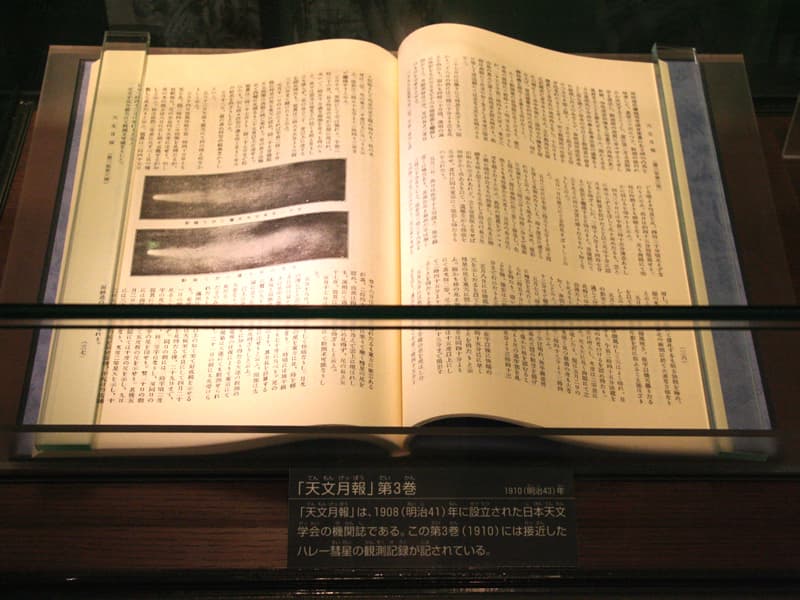遠眼鏡(望遠鏡)
江戸時代後期には、現在の浅草橋三丁目界隈に幕府の天文・暦術・測量・地誌編纂・洋書翻訳などを行う施設として、天文台が置かれていました。司天台、浅草天文台などと呼ばれた「頒暦所御用屋敷」は、本来は暦を編纂する天文方であり、正確な暦を造るには観測を行う天文台が必要でした。幕末に活躍した浮世絵師葛飾北斎の「富獄百景」の内、「鳥越の不二」には、背景に富士山を、手前に天体の位置を測定する器具「渾天儀(こんてんぎ)」を据えた浅草天文台が描かれています。浅草天文台では、天文方高橋至時(よしとき)らが寛政の改暦に際して観測しました。至時の弟子には、伊能忠敬らがいます。(参考:たいとう名所図会)

トロートン天体望遠鏡(重要文化財)
明治13年(1880)、明治政府によって当時の内務省地理局に、新たな観測用望遠鏡として輸入・導入されたトロートン社製20センチ屈折赤道儀。後に天体観測、および暦の編纂が文部省所管に移った際に、東京天文台(後の国立天文台)に移されました。

葛飾北斎「富獄百景・鳥越の不二」
鳥越神社の東に頒暦所御用屋敷がありました。北斎は、鳥越から見た富士を背景に天文台を描いています。

トロートン天体望遠鏡(重要文化財)
明治13年(1880)、明治政府によって当時の内務省地理局に、新たな観測用望遠鏡として輸入・導入されたトロートン社製20センチ屈折赤道儀。後に天体観測、および暦の編纂が文部省所管に移った際に、東京天文台(後の国立天文台)に移されました。

葛飾北斎「富獄百景・鳥越の不二」
鳥越神社の東に頒暦所御用屋敷がありました。北斎は、鳥越から見た富士を背景に天文台を描いています。