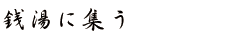銭湯は、地域保全の大事な役割も担っています。

弁天湯の北島鉱一さん(左)、北島健一さん(右)
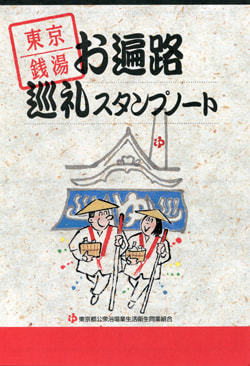
東京都公衆浴場組合では、都内の銭湯を巡る「銭湯お遍路」を催しています。26浴場を達成すると、「銭とお遍路達成」認定証と記念品の銭湯バッジを授与しています。いわゆる銭湯の達人養成の企画です。
台東区浴場組合連合会会長を務められている弁天湯(浅草橋1丁目)の北島鉱一さん、先代の北島健一さんにお話を伺いました。
Q:弁天湯の歴史について、お話し頂けますか。また入口の弁財天は、どのような由来で祀られているのですか。
健一が三代目、鉱一は四代目となります。明治時代に、現在の場所で富山出身の初代の常次郎が開業しましたが、戦後の混乱で詳しい資料が残っていないため、はっきりとした記録は分からないのです。
入り口の弁財天は、元々近所に祀っていたところ、戦後に行き場が無くなり、町内で苦心して祀っていましたが、道交法でいよいよ行くところが無くなって、弁天湯が引き取り世話をすることになりました。今はここもビルになってしまいましたが、昔は社がありました。弁天湯の由来も、弁財天にあやかって付けたと思われます。(下段に続く)

Q:台東区の銭湯事情について、お話し頂けますか。また弁天湯さんでは、一日にどのくらいの利用客がおられますか。
根岸、松が谷、千束等古い家が残っている地域は銭湯の需要がまだありますが、谷中地域は需要は少なく、柳橋や台東などのマンションが増えている地域ではどんどん廃業していきますね。
弁天湯のお客様は、入浴券(高齢者、生活保護世帯に配布)での利用者を含めて1日100人程度といったところです。台東区内でも少ない部類に入ると思われます。お風呂がない世帯が多い地域や高齢者が多く住まわれている地域では、お客様が300人から400人もおられるところもあります。
Q:最近では、このあたりにも外国人の住民の方は増えたかと思いますが、いかがですか。
パンツを履いたまま入浴しようとした話は有名ですが、今ではほとんど来られませんね。外国の風呂とは入浴方法が違うため、最初のうちはトラブルもありましたが、馴れれば問題はありません。バックパッカーとして来日された方は日本を勉強しようとされる方が多いので、身振り手振りで交流しながら素直に聞いてくれますね。ポスター等で銭湯の入り方を貼りだしていますが、むしろ日本人で守られない方もいますね。昔は湯船から桶で掛け湯をしていましたが、最近はカラン(蛇口)から取ることになっていますが、高齢者の方は新しいお湯はもったいないという意識を持たれていて、やはり湯船から取ろうとされますね。(下段に続く)

Q:弁天湯を利用される方は、どのような方々ですか。また災害時には、銭湯の利用が重要ではと言われていますが、いかがですか。
浅草橋はアクセサリー屋さんが多いのですが、通いの人が大半なのでほとんど来られません。やはり土地の方が多いですね。区境なので銭湯が無くなりつつある千代田区や中央区からも来て頂いています。小学生や中学生は、年に数える程しか来なくなりました。
最近の銭湯では、水道水を使用している所もありますが、台東区の銭湯のほとんどが井戸水を使用しています。弁天湯でも、湯船やシャワー等は井戸水、トイレや手洗い等は上水道と分けています。台東区と災害時の井戸の利用について協定を締結し、隔年毎に水質検査を行っています。井戸は最近は使わなくなったせいか、涸れるということはありませんね。掘れば、昔よりも水が出るのではないかと思います。深く掘って水質を調べ、もっとも良い水質のところを使います。地域や深さによって水質は異なっていて、近隣の蛇骨湯(浅草1丁目)は黒い色の水質です。この辺は硬水なので、湯を沸かすと「がり」と呼ばれる石灰分が付着してしまって、落とすのが一仕事です。
Q:一日にどの程度の水量を使われるのですか。また先の震災等を考慮すると、今後井戸が重要となってくるのではありませんか。
正確には量ったことはありません。井戸水だと汲み上げには料金は掛からないのですが、使用した後に下水に流すので下水料金が掛かります。パイプの広さと平米あたりを計りメーターを付けて、モーターの稼働時間によって計算しています。
昔、水道が止まった時には、水の供給場として弁天湯が機能しました。井戸水を汲み上げて、屋上のタンクに送ってから水圧で落とすのですが、上がる前の蛇口を開けて水を配給しました。先の東日本大震災の際は特に営業に支障はありませんでしたが、弁天湯は汲み上げに電気を使用しているので、停電になると営業や水の提供は難しいですね。災害や震災への対処は特に決まっている訳ではありませんが、対応している地区もあります。
Q:最近の銭湯では、番台も外についているところが多いようですね。また懐かしいペンキ絵については、どのようになっていますか。
色々ありますね。昔の番台の形式はどんどん減っていますが、ゼロではありませんね。番台風にしながら中の普請を変えている所や、帝国湯(浅草橋5丁目)のように外観はビルになっていますが、中は昔ながらの番台のところ、弁天湯や鶴の湯(浅草5丁目)のように、番台を完全になくしてカウンター式にしているところもあります。昔のように、番台があって富士山の絵がある銭湯は、まだ何軒か残っています。
ペンキ絵については、都内に有名なペンキ屋さんが居られて、お願いしていますが、数ヶ月待ちだと言っています。背景画を止めてタイル貼りにしている銭湯もあります。ペンキ絵の直しをお願いする頻度は、2年に1回程だったと記憶しています。昔は、絵の下に看板があり、地域の方が広告を出せるようになっていて、ペンキ屋さんが広告料金を代金として回収していました。ペンキ絵の直しは、定休日の1日でやってしまわなければならないので、作業は大変早いですね。絵を消すのではなくて、古い絵の上から新しい絵を描いています。描く絵については、こちらから指定したこともありますが、基本的にお任せです。富士山が多いのは、富士山が落ち着くとか、極楽を意味する富士と言われているからではないでしょうか。山岳信仰の名残りがあるのかもしれませんが、必ずしも富士山が見える方向に富士を描くという訳ではありませんね。
Q:営業時間や定休日、そして現在の料金は、どのようになっていますか。
昔ほど時間が厳しくないのでばらばらですが、営業開始が15時から、営業終了は0時前後が多いです。弁天湯は15時半から23時半までです。公衆浴場組合本部からの通達により、正月には朝風呂を行っています。燕湯(上野3丁目)は、普段から朝早く営業していますが、20時には閉めています。夜間人口があまり多くなくて、またマンション住まいが多いためでしょう。(右上段に続く)
定休日は設けているところもあれば、無休のところもあり、決まりはありません。月曜日を定休日とする銭湯が多いのは、土日曜日に客が多く入っていた昔のなごりです。弁天湯は、月2回の月曜日を定休日にしています。近所の他の銭湯と休業日が重ならないように調整しています。
入浴料は昔に比べて値上がりしているでしょうね。東京都や知識人等で構成される委員会で毎年値段を決めています。自治体から配布されている入浴券は、区によって枚数やシステムが異なっています。台東区では一部の高齢者に月に20枚の補助券を配布し、利用者が50円を足して入る仕組みになっています。利用される方も銭湯側も大変助かっています。
Q:浴槽は、どのような構造になっているのでしょうか。懐かしい菖蒲湯、ゆず湯は、今でもありますか。
弁天湯では、湯船は43度に設定していますが、実際は41-45度程度でしょう。男湯女湯とも温度は同じです。保健所の指導により、浴槽に人が入った際にお湯がこぼれないといけない事になっています。昔、濾過機がなかった時代のなごりで、熱めにしておいて水を足すと湯船表面の垢が流れ出る仕組みになっています。
今では、菖蒲湯やゆず湯は、一種のお客様へのサービスの意味合いになってしまいましたが、都の公衆浴場組合本部からも推奨されていますから、行っています。地域によっては、地方と手を組んで、出荷が難しい農作物を利用するなど、様々な湯を提供しているところもありますね。
Q:現在行っておられる取り組みや今後については、いかがですか。学校対象に銭湯体験などを行って、いわゆる裸のコミュニケーション体験は良い機会だと思われますが。
余力がなければ、銭湯は駄目になってしまうと思います。現在、組合で話しているのは、健康増進型銭湯にして、区や都から援助を受ける取り組みです。また弁天湯では、介護施設への貸し出しも行っています。名古屋の中小企業から始まった試みですが、最近では大手会社も参入し始めています。台東区内では、弁天湯が第一号です。現在も行っているところは多くはありませんが、健康ランド、フィットネスクラブでも取り組みたいとの事で、これからはライバルも増えるでしょう。
その他に、蛇骨湯(浅草1丁目)では、銭湯で定期的に落語を開催して援助を受けているとの事です。弁天湯でも、お湯に入りながらではありませんが、女湯に舞台を作って落語を行ったこともあります。銭湯にとっては、月幾ら、一回幾らの値段と収入の勝負ですが、使い放題のフィットネスクラブ等は大変なライバルですね。若年層の客は取られてしまいますし、外国人のように風呂に浸かる習慣がないと安い方が良いと考える方もいます。
昔は、学校を対象として銭湯の1日仕事体験等も行っていましたが、学外活動の責任問題等もあったり、最近では裸に抵抗があるため、無くなってしまいましたね。台東区内では小学校と提携している所はありませんが、他の区では小学生を招いたイベントや親子で入浴するようなスタンプラリー等も行っています。地域と先生方の声が上がらないと、銭湯側から働きかけても、なかなか実現しませんね。台東区は子供さんが多い地区と少ない地区の格差が激しい地域なので、イベントを開催するにしても一斉に行うことが難しいですね。(下段に続く)

Q:東京都の銭湯維持について、方針は何かありますか。大型の健康ランドと競合するために、営業形態を変えるのは難しい事ですか。
サービスを良くするよう、手ぶらで入れるようにシャンプー・リンスを置くように言われています。弁天湯では、手ぶらでも入れるように有料での販売を行っていますが、無料で行っている所もあります。タオル、石鹸、シャンプーは持ってきてもらえると有り難いですね。「先にお金払うんですか。」とか、中に入ると「タオルはないんですか。シャンプーはありますか。」と、健康ランドやスーパー銭湯感覚で来られるお客さんも最近は居られますね。
台東区は少ないですが、旭湯(現・アクアプレイス旭、浅草5丁目)のようにスーパー銭湯みたいに変えてしまった所もあります。
Q:閉業のペースはどれくらいなのかですか。また新しく始める人は居られますか。
台東区では、ここ幾年かは1年に1軒ずつ閉業していますね。お金も人手も掛かり、大変な仕事ですが儲からないため、銭湯を新しく始める人はいないでしょう。弁天湯が、それでも営業しているのは地元に根付いたもので、地域貢献という意識があるからです。後継者問題と言われていますが、儲かっていれば後継者はできるはずです。
Q:銭湯の今後については、いかがお考えですか。
多角経営をされている方もいますが、どうでしょうね。魚屋さんや八百屋さん等のどこの商売でも単独での商売が難しく、地域に根づいた商売がしにくい。近所の魚屋さんは、地元の方への販売よりも飲食店に提供することで成り立っています。弁天湯も同様で、銭湯だけでは厳しいので、三代目の時に建物をビルにして、地下駐車場からも収入を得ています。現在は家族経営で賄っていますが、必要経費を出すと給料は出せない程で、五代目に受け継ぐ時にはやっていけないでしょうね。
昔のような住み込みは今はありませんが、戦前、三代目が小学生の頃は、書生や番頭さんがいました。昔は石炭を使っていましたが、石炭が高くなって使えなくなってからは、大八車を引いて、深川の製材所あたりで薪やおがくず、みじんこ(鉋くずの細かいもの)を拾ってきて燃やしていました。今はガスを使用しているところが50%、他に重油を使用しているところや、昔ながら薪や廃材を燃やしているところもあります。弁天湯のように電気を使用しているのは数軒です。近年のエコロジーの考えで太陽光を使用している銭湯もありますが、太陽光だけでは賄いきれませんからガスを併用しています。もっとも安上がりなのは、何でも燃やす雑燃ですね。家の解体時に出る廃材を引き取って燃していました。最近は、木材の入手も難しくなりました。フォークリフト用の木製パレットが古くなったので燃やしてくれというような業者さんがいなくなりました。近在の銭湯でも、木製パレットを細かく切って雑燃として燃していたこともありましたが、今のパレットは樹脂を使っているので、燃やせませんね。
Q:銭湯の意義については、いかがお考えですか。
現在、都内の銭湯761軒程との事ですが、「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例」(東京都)で、銭湯の設置は、特別区域では200m、市町村区域では300mに一軒と距離制限があります。高齢者の方は自宅に風呂があっても、昔から銭湯を知っているので、大きなお風呂に浸かりたいと来られる方が多い。ひとつのコミュニケーションの場になるので、同じ時間に同じ方が集まります。生活のリズムに合わせて来られるので、自然と顔馴染みとなるようです。高齢者の方にとっては、銭湯は重要なコミュニケーションの場です。近在の銭湯が閉業して困ったという電話が区役所にあったそうです。(次ページに続く)

弁天湯の北島鉱一さん(左)、北島健一さん(右)
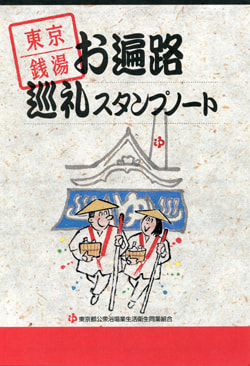
東京都公衆浴場組合では、都内の銭湯を巡る「銭湯お遍路」を催しています。26浴場を達成すると、「銭とお遍路達成」認定証と記念品の銭湯バッジを授与しています。いわゆる銭湯の達人養成の企画です。