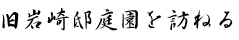和服姿のジョサイア・コンドル(1852-1920)
明治10年(1877)、工部大学校(現東京大学建築学科)造形学教師、および工部省営繕局顧問として来日。以降、大正9年(1920)まで在日し、鹿鳴館を初めとして日本国内の多くの建築物を手掛けました。また辰野金吾、桜井小太郎等の著名な建築家を育成し、大正9年(1920) 67歳で東京において逝去しました。(「ジョサイア・コンドルと鹿鳴館時代」展より)
Q.戦後(第二次大戦後)は、GHQがこの建物を接収したとの事ですが、建物は焼け残っていたのですか。
松井: 焼け残ったというより、あえて爆弾を落とさなかったと言った方がよいでしょう。当時アメリカはピンポイントで、残すべき所をはっきり区別していたらしいのです。戦後に都内では900ヶ所ほどが接収されたのですが、これらもやはり爆弾を落とさなかった場所なのですね。それは初めから戦略的に考えての事で、アメリカには情報が疎通だったのですね。当然ここも接収する目的がありましたから爆弾は落とさなかったのだと思います。日本文化や、精神的な支柱までを壊滅する事での反感を畏れた事もあるのでしょう、ベネディクトの「菊と刀」ではありませんが、やはりそういうものは残しておくべきと。
Q.接収されていた後も、岩崎家はしばらくはここに住まわれていたという事ですが。
昭和20年(1945)にGHQのキャノン機関がここを接収するのですが、今はもう無いのですが、洋館の奥には和式住宅があり、岩崎家の人々はそこに追いやられて昭和24年(1949)までは住まわれ、その年の暮に千葉県の富里町に所有されていた末広牧場に移られました。相当に広大な土地でしたが、戦後はほとんど接収されました。そこで岩崎家の手から離れてしまいました。(下段に続く)

サンルームでの岩崎久彌氏と家族

現在のサンルーム
Q.富里町にはどのような縁で土地を所有されていたのですか。
久彌氏は、特に動物や農業に大変関心を持たれていたのですね。たとえば明治24年(1891)に小岩井農場を三菱財閥二代目の彌之助氏が造りますが、小岩井農場は共同創始者であった小野義真(日本鉄道会社副社長)、岩崎彌之助(三菱社社長)、井上勝(鉄道庁長官)の三名の頭文字を取り命名されましたが、その後明治32年(1899)からは三代目の岩崎久彌氏が継承し場主となり、その後に井上氏、小野氏が亡くなり、結局岩崎家が三菱とは関係なく、個人事業として名前だけを残して農場を経営していくのですが、それにずっと久彌氏も関わっていた事もあり、近場の富里町に土地を購入して、農場を拓いて行った経緯があるようです。その当時、宮内省に生ハムを納めていたという話もあります。ある意味、久彌氏は農学者でもあったのではないかと思います。
Q.旧岩崎邸庭園は、現在は国の重要文化財との事で歴史的な文化遺産でもありますが、建物としての価値としても評価されているのですか。
歴史的な文化遺産としての趣きが最も重要な事なのでしょうが、当時鹿鳴館も設計したコンドルの作品の中でも、最高傑作と言われているのがこの岩崎邸なのです。元々コンドルは大きな公(おおやけ)の施設よりも邸宅の設計が得意でした。(右段に続く)
イギリスでも邸宅設計でソーン賞を受賞していて、これが日本に来るひとつの契機になっています。そのコンドルが一番に脂(あぶら)がのっていた時期、そして洋館、和館が併置建造された時代背景にあった岩崎邸がこれらの様式を代表する建築であった事から文化的な価値も高いと文化庁が判断したと思います。またコンドルのいわゆるジャコビアン様式を取り入れた設計やインテリアなども文化的な価値が高いとの評価があったようです。明治期の建築物で重要文化財に指定されているのは都内で9ヶ所ほどで、東京国立博物館の表慶館や旧東京音楽学校奏楽堂などの公の施設がありますが、邸宅はこの建物だけです。
Q.旧古河庭園(東京都北区)もコンドルの設計ですか。
はい、コンドルですね。重要文化財ではありませんが、国指定の名勝となっています。石造りで、大正期のアールデコ様式の時代に建った家ですから、趣きもデザインも違います。建築家はそういう意味では大変で、時代の流れの中でデザインも変えて行かなければならない、建築家だけの意思では建物は建ちませんからね。施主とのコミュニケーションの中で造って行くもので、また時代と共に変わっていくものでしょう。(次ページに続く)



別棟の撞球室(ビリヤード場)
スイスの山小屋風で、校倉造り風の外壁、軒が深く張り出した大屋根のゴシック調の木造建築。



イオニア式列柱の立ち並ぶ二階ベランダ

イオニア式列柱の立ち並ぶ二階ベランダ

和服姿のジョサイア・コンドル(1852-1920)
明治10年(1877)、工部大学校(現東京大学建築学科)造形学教師、および工部省営繕局顧問として来日。以降、大正9年(1920)まで在日し、鹿鳴館を初めとして日本国内の多くの建築物を手掛けました。また辰野金吾、桜井小太郎等の著名な建築家を育成し、大正9年(1920) 67歳で東京において逝去しました。(「ジョサイア・コンドルと鹿鳴館時代」展より)