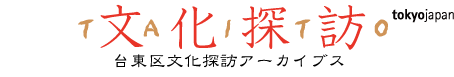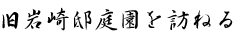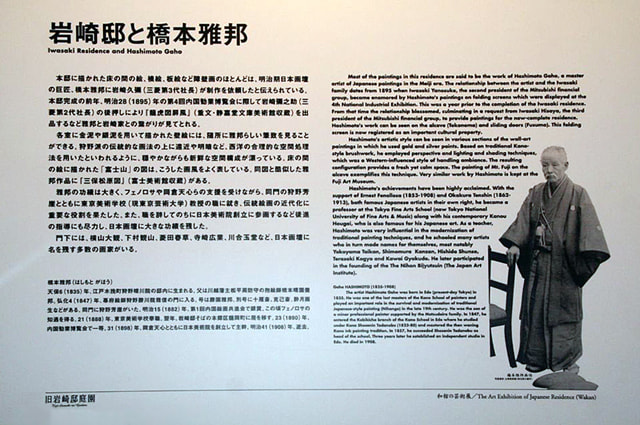Q.現在、本邸はどの様に使用されているのでしょうか。開園されたのは平成13年(2001)ですが、それまでは公開されていなかったのですか。
松井: 国の重要文化財として、文化庁から東京都に管理委託されましたので、この時代に建った和洋併置式の建物、しかも日本近代建築の父と言われたジョサイア・コンドルの手による最高傑作として、多くの方に見学して頂いて当時の建築文化を認識して頂いています。そして文化財の保護と継承、そして伝承を第一として取り組んでいます。ずっと法務省の司法研修所となっていて、私も都立庭園として開園するとは夢にも思っていませんでした。ですから、まだ知らない方も結構多いですよね。
Q.正門や植木などの植生はあまり変わっていないのでしょうか。
正門は、平成6年(1994)に敷地が売却された後に現在の場所に置かれて、法務省の職員はここから出入りしていました。もともとの正門は春日通りに面したところにあり、樫の木の大きな門があったらしいですよ。そこに馬車を留め置いていました。いわゆる馬車道ですね。神社でいえば参道みたいなものです。植生はあまり変わっていません。委託された際には非常に荒れていて、私たちが開園準備で訪ねた際は自生の樹木で鬱蒼としていましたよ。芝庭は雑草がこんな背丈までありましたね。芝刈りから始まって、自生した樹木の伐採、そして土方仕事で約半年を費やしました。どれだけ東京都の職員も導入したか、分かりませんね。それでようやく見せられる程度にまでなりましたが、いまだ暫定整備ですね。(下段に続く)

庭園には、ウィリアム・モリスのデザインにも表われるアカンサス(葉薊(ハアザミ))が見事な大葉を広げていました。

庭園は、大名庭園の名残りも残していました。

庭園のシンボルでもあるヒマラヤスギの大樹
Q.私共は、3,4年ほど前に一度伺って写真撮影をしているのですが、まだ庭園の整備中のようでした。国分寺の殿ヶ谷戸庭園には池が残っていますよね、こちらもそのような体裁に近かったのでしょうか。
そうでしょうね。これからご案内する和館にちょっとした庭があるのですが、こちらもほんの一部が残っている程度で、庭園と言いながらもお粗末と言わざるを得ませんね。池があったかは確証のない話で、基本的には芝庭の庭園、和風庭園、回遊式の庭園とそれぞれ概念が違うので、植栽についても自ずと変わってくると思います。
Q.当時の敷地や建物の図面は残っていますか。
図面として信頼できるのは、大正6年(1917)に当時の陸軍が調査した実測図です。これ自体が重要文化財になっていて、館内にはこれを実寸大で複写した物を展示しています。この実測図から灯篭の位置や園路なども明らかなので、これが元通り1万5000坪の庭園となったら、夢のような話ですが、建物は無理としても庭園の部分だけでも復元したいですね。これは私たちの夢ですね。(右段に続く)
Q.庭園の周辺には、すでに民間の方々が住まわれているのですか。
裏手は財務省の管轄で、こちら側には法務省の住宅が建っています。関東財務局です。一方は民間です。この関東財務局の建物が移転するという話もあります。この裏に建っている建物ですね。この周辺のご隠居さんたちが中心となって、岩崎家が物納したものとはいえ、良い加減で岩崎家に返して、昔のお庭に戻したらどうかと住民運動が起こされてているのも事実です。大変有難いお話です。まだ文京区としても(旧岩崎邸庭園は、台東区と文京区の境界にあります。)公園地にした方が良いのではという話も聞いております。我々としてはどうにも出来ない事ですから。
Q.もし民間に払い下げになると間違いなくマンションが建ってしまうのでしょうね。しかし東京都では歴史的建造物の周辺数百メートルには景観の問題等で高い建物が建てられないと措置されているので、民間も買いようが無くなってしまう課題もありますね。
文京区の方も景観条例等を考えているみたいですが、これからどうなることやら。
Q.旧敷地は元々の大名屋敷の敷地だったのですか。
もうちょっとあったのですね。6万平米ほどもあったと言われています。もうちょっと長かったのですね。東大の龍岡門くらいまであったのでは。この辺の土地も岩崎家はお持ちでしたから、文京区の体育館も岩崎家の土地ですよ。この周辺に持っていた土地を財閥解体と共に手放されました。この屋敷内に従業員は50名ほどいましたので、そういう人達の住宅も岩崎家が建てて、そこから通っていました。従業員も本当に大事にされたようです。
Q.本邸庭園を見学される方は、どのような方が多いのですか。この方々は、歴史的な背景をご存じで訪ねられるのですか。また海外の方は、いかがですか。
圧倒的に多いのは40歳から60歳前の女性ですね。洋館の憧れやノスタルジックなものを感じられるのではないでしょうか。また、歴史についてはご存知ない方が圧倒的だと思います。洋館に一度は住んでみたいみたいな憧れを持たれているのだと思います。海外からの方は5パーセントにも満たないでしょう。ただ最近は、台湾や韓国のお客様が来られます。一度、日本アジア航空が「日本の名所」と題して機内で岩崎邸庭園の宣伝をやっていた時期がありまして、そのお陰で台湾のお客さんがずいぶんお出でになりましたね。