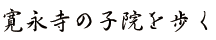寒松院住職の宮部亮侑さん
寒松院の宮部亮侑住職にお話しを伺いました。本インタビューは平成27年(2015)10月に取材したものです。
Q: 寒松院は、いつ頃に創建されたのでしょうか。
宮部 : 寛永4年(1627)に徳川家康公を祀る上野東照宮の別当寺として開基されました。
Q: どのような経緯で、現在の地に移られたのですか。
創建当時は、上野東照宮に隣り合った、現在の上野動物園のあたりにありましたが、慶応4年(明治元年)(1868)の上野戦争(戊辰戦争)の際に、寛永寺の多くの堂宇は焼失してしまいました。明治21年(1888)に現在の寛永寺の裏手に再建されましたが、第二次大戦時の戦火により再び焼失してしまいました。現在の地に移りましたのは、その後です。二度の焼失のため、歴史的な資料等の多くが失われてしまいました。(下段に続く)

上野東照宮(上野公園内)
Q: 現在は、上野東照宮の別当寺としての関係はあるのでしょうか。
明治新政府は、王政復古のため神道の国教化を図り、永らく行われてきた神仏習合を禁止し、神仏分離令(神仏判然令)を発布しました。これにより、その関係が断ち切られてしまいました。上野公園内に残る五條天神や浅草寺内の浅草神社等も神仏習合でした。
Q: 藤堂高虎は、どのような経緯で寒松院を上野東照宮の別当寺として創建したのでしょうか。
徳川家康公を祀る上野東照宮の造営の際に、東照宮の法要を行うために藤堂家自らの下屋敷の地所を明け渡して寒松院を別当寺として建てました。高虎公は、家康公の側近の中でも重用されました。高虎公は勇猛、剛健の武将として伝わっていますが、高虎公に関する研究は近年ようやく始まったばかりで、未だ全容は分かっていません。藤堂家の墓所は現在の動物園内にありましたが、明治維新以降の方は豊島区駒込にあります染井霊園に埋葬されています。
Q: 藤堂高虎とは、どのような人物だったのでしょうか。
近江国(現在の滋賀県)の出身と言われています。体躯は6尺余(約190cm)もあったとの言い伝えもあり、羽柴秀長(羽柴秀吉の弟)の家臣でもありましたが、築城技術等に優れ、聚楽第の家康公の屋敷の造営にも関わりましたが、その配置を見て守りに弱い事を指摘して造営を改めたとの事で、家康公にも褒められたとの事です。秀長の家臣として戦功を挙げ頭角を表しました。
Q: 関ヶ原の戦いでは、どのような戦功を挙げたのでしょうか。
秀吉公の死後、豊臣家の家臣が軍務を担った武断派と、政務を司った文治派に分裂した際に、武断派の一人として徳川方に付きました。またその戦功から、今治藩を賜っています。その後、江戸城の築城にも功績を残したため、今治に加えて伊勢津藩主となりました。高虎公は、外様大名でしたが、津は江戸と京都を結ぶ中の要衝として高虎公に任されたとの言い伝えもあります。
Q: 家康公との関係や江戸での務めとはどのようなものだったのでしょうか。
高虎公は朝鮮出兵でも戦功を挙げていますが、兵の引き上げについても家康公に進言したとも謂われ、家康公の信頼も大変篤かったのだと思います。高虎公も家康公を大変尊敬され、高虎公は元は日蓮宗でしたが、家康公が逝去された際には家康公が帰依されていた天海大僧正の宗派の天台宗に改宗し、さらに家康公を祀る東照宮の造営、そして東照宮の法要を取り扱う寺、いわゆる別当寺として寒松院を創建しました。
高虎公は和泉守を授けられ、藤堂家は代々和泉守を襲名していましたので、神田にありました津藩邸(上屋敷)の地域は、千代田区神田和泉町の町名の由来となっています。現在でも、和泉小学校等の名称として残っています。
Q: 古くから浅草寺がありましたが、寛永寺はどのような経緯で創建されたのでしょうか。
寛永寺は、天海僧正が京都の鬼門に置かれた比叡山延暦寺に見立てて江戸城の鬼門封じとして創建されました。当初は寛永寺と浅草寺の両方が国の安全を祈っていたのですが、徐々に寛永寺のウェイトが増していきました。(右上段に続く)
Q: 明治新政府設立後の寛永寺はどのような状況にあったのでしょうか。
戊辰戦争の後は、上野の山内には永らく立ち入る事が出来ませんでした。彰義隊の遺体もそのまま置かれていたとの事です。そのため、寒松院と護国院の住職が、寒松院の松、そして護国院の国を取って「松国」と称して遺体を弔ったと伝えられています。彰義隊は、本来一橋家の警護隊ですが、一橋家を相続していた徳川慶喜公が水戸に戻られてからは寛永寺を警護する大義を失っていました。慶喜公も彰義隊の解散を命じていますので、寛永寺に留まった部隊と官軍の戦であったかと思います。一方、官軍は彰義隊を幕府の正規軍と位置付けて滅ぼす事により、戦の大義を偽ったとも言えるのではないでしょうか。(下段に続く)

彰義隊墓所(上野公園内)
ところで、寛永寺では代々皇子あるいは天皇家の猶子の方が住職を務められたので、慶応3年(1867)に北白川宮能久親王は江戸に下向され寛永寺に入られて15世公現入道親王として寛永寺住職、輪王寺門跡を継がれました。この公現入道親王が明治新政府樹立後に僧侶を辞められて以降、寛永寺住職を皇族の方が務められる事はなくなりました。(下段に続く)

旧寛永寺五重塔(上野動物園内)
寛永寺は、戊辰戦争後に寺領を明治政府に没収されましたが、明治8年(1975)に元は寛永寺の子院の大慈院が建っていた地に、川越市にある天海僧正の住まいでもあった喜多院の本地堂を移築して根本中堂が再建されましたが、ちなみに徳川慶喜公が慶応4年(1868)2月から2ヶ月余り蟄居されていました葵の間は、この大慈院にありました。
Q: 後に上野公園として整備された際の寛永寺とはどのような位置付けだったのでしょうか。
当時、寛永寺はそのほとんどの寺領を失いましたし、その存続は大きくは顧みられなかったかと思います。
Q: 寛永寺の子院の役割についてお話し頂けますか。
子院の住職は、寛永寺管轄の諸堂の輪番や役職を務めるようになっています。このような役割は、今も変わっていません。

寛永寺根本中堂

寒松院住職の宮部亮侑さん