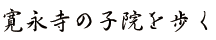寛永寺の子院のひとつの護国院(護國院)の大黒天は、護国院がある上野、谷中、西日暮里、田端の寺に祀られた七福神を巡る、いわゆる谷中七福神の一寺となっています。谷中七福神巡りは、毎年正月から10日の間、催されています。(上野公園10-18)

寛永寺の子院のひとつ護国院は、大黒天を祀る事から、上野大黒天とも呼ばれています。江戸時代から、正月には七福神詣でとして不忍池の辯財天、上野護国院の大黒天、谷中天王寺の毘沙門天、谷中長安寺の寿老人、日暮里修性院の布袋、日暮里青雲寺の恵比寿、田端東覚寺の福禄寿の谷中七福神に詣でる事が、山の手七福神、向島七福神と共に盛んでした。天海僧正は徳川家康の徳を讃えて長寿、富財、人望、正直、愛敬、威光、御徳の七福を挙げました。徳川家康は、絵師狩野探幽に七福神を描かせました。これが七福神の起源と言われています。探幽が描いた七福神は、市井にも評判となり、 正月には七福神が乗った宝船の縁起札を頂く事が全国で盛んとなりました。
護国院は東叡山寛永寺三十六坊のひとつで釈迦堂とも呼ばれています。釈迦堂は三代将軍家光により寛永7年(1630)に建立されましたが、享保2年(1717)に焼失しました。その後の享保7年(1722)に再建され、現在に至っています。寛永16年(1639)の大念佛法要の際に三代将軍家光は、国の護りと人々の福運を祈願して藤原信実筆とされる大黒天の画像を護国院開祖生順大僧正に贈りました。以来、護国院ではこの尊像を祀ったため、護国院大黒天として信仰されました。

護国院には、数多くの往時の著名な寄進者の銘が刻まれています。


護国院には、重層した歴史が建物や壁画にも残されています。

寛永寺の子院のひとつの護国院(護國院)の大黒天は、護国院がある上野、谷中、西日暮里、田端の寺に祀られた七福神を巡る、いわゆる谷中七福神の一寺となっています。谷中七福神巡りは、毎年正月から10日の間、催されています。(上野公園10-18)