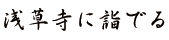江戸の賑わいが偲ばれる伝法院通り

大正12年(1923)の浅草三社祭の写真が、浅草の街角に掛けられていました。

戦後から昭和33年(1958)頃の浅草寺
Q:浅草寺さんとその周辺はどのように信仰されてきたのでしょうか。
浅草寺の歴史は大変古く、遥か飛鳥時代にまで遡ります。以来今日に至るまで、様々な人々からの信仰を受けてまいりました。浅草寺草創の歴史を振り返ってみましても、その初めは2人の漁師が観音さまをお掬い申し上げたところから始まる訳で、庶民である漁師たちがその草創の主人公というその起りからみても、浅草寺がいかに民衆の寺として信仰されてきたのかがわかります。さらには、源頼朝公、足利尊氏公、小田原北条氏や徳川歴代将軍等々名だたる武将の庇護を受けるなど、時の権力者の信仰をも受け入れているのです。特に江戸時代には元々庶民信仰の土壌があった所に徳川将軍さまのご信仰も加わり、民衆と将軍さまが一体になれる寺という事で、さらに大いなる繁栄をみたといえます。
Q:浅草寺と将軍家に纏わるエピソードがあれば、教えて下さい。
浅草寺には将軍家に纏わるエピソードは数多くありますが、一つ申しますと御成りのお話がございます。江戸時代も天下泰平の世の中になりますと、将軍さまも幾度も御成りまたはお忍びで浅草寺に参られて観音さまをご参拝なさいました。参拝の後に、伝法院でお休みになられて庭園を楽しまれたり、浅草の奥山から大道芸人などを呼んで、それをご覧になられたりして楽しまれていたとの事です。奥山は、当時は一流の大道芸や見世物などが行われていた賑わいのある地域でしたので、日本一の手品師や独楽回し師などを呼ばれて伝法院で楽しまれていたのでしょう。(右段に続く)
Q:奥山とは、日本最古の遊園地と言われる「花やしき」がある辺りですか。
そうですね、浅草寺の本堂の裏側、西北の辺りですから今の花やしきの辺り一帯ですね。将軍さまは、代々浅草寺を好まれて幾度もお参りに来られていました。また、上野の寛永寺の住職として代々いらっしゃいました法親王様も、兼帯ではありますが浅草寺の住職でもありましたので、浅草寺に御成りになられまして、将軍さまと同じように楽しまれたという事です。
Q:浅草寺周辺では、これまでにずいぶん焼失が度重なったかと思いますが、現在の本堂(観音堂)は過去にどの程度再建や改修が行われたのでしょうか。
浅草寺では、過去に幾度も地震による倒壊や、火災や戦火による焼失を繰り返しております。正確な数は分からないのですが、20回くらいはあったとされています。最も近いものでは、第二次世界大戦時におけるいわゆる東京大空襲があった昭和20年(1945)3月10日に焼失しています。大正12年(1923)の関東大震災の際には、当時の浅草区の大半の家屋が焼失しましたが、浅草寺は避難された方々の協力もあり、境内の一部の建物が被害を受けながらも、観音堂は奇跡的に焼失を免れました。それ以前には、江戸時代初期に2度ほど焼失しています。それよりも前の話になりますと、室町時代や平安時代にも焼失しておりますが、その度に時の様々な人たちによって復興されており、人々の観音さまへの信仰の篤さが偲ばれます。

大正9年(1920)頃の仲見世、出店には電飾が並んでいます。

大正12年(1923)の浅草三社祭の写真が、浅草の街角に掛けられていました。

戦後から昭和33年(1958)頃の浅草寺