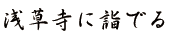Q:平成21年(2009)から22年(2010)に行われた平成本堂大営繕では、どのような営繕や改修が行われたのでしょうか。
昭和20年(1945)の第二次世界大戦の東京大空襲で焼失した本堂(観音堂)が、昭和33年(1958)に落慶しまして、それから約50年が経ち、あちらこちらが傷んできておりました。昭和33年の再建時には、防火等の様々な問題に対処するために鉄筋コンクリート造りとし、屋根は本瓦が使用されました。平成の本堂大営繕には1年9ヶ月程を要し、屋根瓦の葺き替え、壁面の塗り替え、そして耐震補強等が施されました。瓦も50年を経て傷んでおり、また大地震への備えということもあって、全ての瓦をチタン瓦に替えました。チタン瓦に替えることによって、全体の重量が本瓦の時の5分の1程度と大変軽くなりました。この工事の結果、この度の東日本大震災にも耐える構造となりました。震災当日、境内にも多くの方々が参拝におられましたが、皆さん無事でありましたので、この工事が完成しておったということは大変ありがたいことだったと思っております。
Q:境内にある建造物の中でも、六角堂はとても古い建物だと伺ったのですが。
浅草寺では六角堂が最も古い建物のひとつで、東京都指定文化財になっています。しかし建立された年代は定かになっていません。室町時代末から江戸時代初期の建物であるという事は間違いないようです。ただ六角堂だけではなくて、二天門も古く、今の門は慶安2年(1649)に建立されたと言われています。二天門は昭和21年(1946)に国の重要文化財に指定されました。建立以来幾度か改修や補強をしていますが、先年、国と東京都そして台東区と共同で1年以上掛けて全面的な改修工事を行いました。その際に様々な事が分かりまして、実際には門の形もずいぶん変えられていましたので、先生方との協議の結果江戸初期の創建当時の姿になるべく復元しようということになりました。(右段に続く)
Q:二天門は元々朱塗りの建物だったのですか。
朱塗りだったようです。朱の色は魔除けの色とも言われております。その朱色も剥落してしまっていくらか失われておりましたが、この度建立当初の煌びやかな朱の門に甦りました。
Q:浅草寺さんに関係する寺社はどのようになっているのでしょうか。
浅草寺は、昭和25年(1950)に天台宗より聖観音宗として独立し、現在は本寺である浅草寺と一山である24の支院で合計25ヶ寺、他には末寺が人形町に1ヶ寺あります。聖観音宗とは申しますが、浅草寺は昔から「あさくさのかんのんさま」として宗派を問わず様々な方がお参りされる寺でありました。さらに、今ではとても多くの外国の方々をもお迎えしております。
Q:六角堂、二天門の他に、歴史的な建物や史跡はありますか。
他には、主なものに伝法院があります。徳川家康公によって徳川家の祈願寺になった頃から伝法院の庭園と建物が大きく造られていくのですが、安永元年(1772)に目黒の行人坂から起こった江戸大火により伝法院も焼失したと『浅草寺日記』には書かれています。伝法院の中でも今に残る古い所は大火後の安永6年(1777)頃に再建された大玄関や客殿です。
伝法院は、平成23年(2011)9月に国の名勝に指定されています。江戸時代の庭の特徴や形態を残している事等が評価されました。都内でも名園はいくつかありますが、寺院庭園の中で今にしっかりと残っているものはあまりなく、大変貴重な庭といわれております。(下左段に続く)

江戸時代の浅草寺全景
Q:現在、浅草寺の恒例行事には、どのようなものがあるのでしょうか。
色々とありますが、最も賑わうのは初詣、そして四万六千日などがあります。ご縁日は、仏様によって異なっていて、観音さまは毎月18日、お地蔵さまは毎月24日、お不動さまは毎月28日がご縁日とされています。浅草寺の観音さまが御示現(ごじげん)されたのが3月18日ですので、その日には示現会(じげんえ)を催して金龍の舞が舞われ、その徳を讃えます。6月18日には、観音さまによって浄められたお水を無病息災等の祈願を込めご信徒の頭上に灌ぐ(そそぐ)儀式の楊枝浄水加持会(ようじじょうすいかじえ)、観音さまへ日頃の感謝の意を込めて百の山海の珍味を模した百味(お菓子)を供える百味供養会(ひゃくみくようえ)が行われます。また10月18日には、菊花を観音さまに献花し、また観音さまに供えられていた菊花を頂く菊供養会があるなど、観音さまのご縁日である毎月18日には様々な行事が行われます。
Q:四万六千日の功徳日の由来を教えて下さい。
ご縁日とは別に毎月その日にお参りすると特別に多くの功徳が得られるという功徳日というものが室町時代以降に設けられるようになりました。中でも7月10日は、一度のお参りで四万六千日のお参りをしたのと同じ功徳があるとされています。功徳日というのは、簡単に言えば、信仰推奨デーという事でしょうか。昔は、今のように電車に乗って、すぐに浅草寺の観音さまへお参りに来られるというという訳にはいきませんでしたので、遠方の人々は年に一度、中には一生に一度のお参りはいつが良いのかという事で、7月10日を最も功徳がある日としてお参りを勧められたようです。
四万六千日を1年である365日で割ると約126年になります。昔の人は人間の寿命の限界が126年ぐらいかなと思っていたのではないでしょうか。一生分のお参りが1日で叶う日を設けたのですね。それが7月10日でした。ところが地方や遠方から江戸の浅草寺に向かって7月10日の朝に出立しても間に合いませんので、7月7日、8日に出立して9日に浅草寺の近くに寝泊まって10日の朝の開門時に、大勢の方が一斉に参拝されるようになりました。(右中段に続く)
そのため、7月9日も多くの参拝者で賑わったことから、いつしか、7月9日も10日と同じ功徳日として、7月9日、10日の2日間が四万六千日とされ、それが今に続いているのです。
またこの四万六千日には、境内にほおずき市も立ちます。7月15日は盂蘭盆会(うらぼんえ)ですので、ほおずきは仏さまに供える灯明に似ている事から、お明かりとして仏壇にお供えする風習があり、この時期に求めるのにちょうどよかったのでしょう。また、ほおずきは薬用としても用いられていましたので、当時の市はほおずきを求める人で大変賑わい、その賑わいは今に続いています。
Q:その他に賑わう催しがありますか。
年末に賑わう市として、12月17日、18日、19日に羽子板市が行われます。12月18日はその年の最後の観音さまのご縁日という事で、多くの人が浅草寺にお参りされます。昔の歳の市を描いた浮世絵等を見ましても南は浅草橋、東は上野の方まで正月飾りなどを売る市が立ち並んでいたようですが、歳の瀬のこの時期、浅草寺のお参りの帰りに正月飾りなどを求めて帰られていたのでしょう。今では、正月用品は、デパートやコンビニエンスストアでも買えますので、そのような大きな市は無くなってしまいましたが、歳の市の中でも羽子板市だけは今に残りました。正月に、その先年に女子に恵まれた家にお祝いと厄除けのために羽子板を送る習わしがありますが、これは羽子板の羽が蜻蛉(とんぼ)に見えるため害虫を食べてくれるということで、悪い虫が付かないようにというような意味もございます。そういった縁起もあり、羽子板の市は今に続いています。また、最近の羽子板市と言いますとお相撲さんとか野球選手とか、芸能人とか、その時々の話題の人の羽子板も作られるなど、新たな楽しみでもあります。
この他にも、浅草寺には大変多くの行事があり、このこともまた多くの方々が浅草寺に参拝される理由となっているのではないでしょうか。

江戸時代に描かれた浅草寺境内での興行風景(香蝶楼国貞(歌川国貞)画)


浅草寺守護鬼瓦
東京メトロ銀座線浅草駅に展示されている浅草寺宝蔵門の鬼瓦。平成19年(2007)の宝蔵門の屋根瓦の改修時に下ろされたもの。

浅草寺六角堂(東京都指定有形文化財)
六角堂は、室町末期から江戸初期の建築と考えられています。木造、単層の六角造りの瓦葺きで、元は浅草寺境内の東方の地に建っていましたが、平成6年(1994)の境内整備により、影向堂境域の現在の場所に移されました。

浅草寺守護鬼瓦
東京メトロ銀座線浅草駅に展示されている浅草寺宝蔵門の鬼瓦。平成19年(2007)の宝蔵門の屋根瓦の改修時に下ろされたもの。

浅草寺六角堂(東京都指定有形文化財)
六角堂は、室町末期から江戸初期の建築と考えられています。木造、単層の六角造りの瓦葺きで、元は浅草寺境内の東方の地に建っていましたが、平成6年(1994)の境内整備により、影向堂境域の現在の場所に移されました。