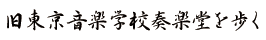奏楽堂の部材


山口半六が手掛けた旧兵庫県庁は、明治35年(1902)に竣工した近世フランスルネッサンス様式に則った建物です。現在は、建設当時の姿に復元され、兵庫県公館として公開されています。
Q : 奏楽堂の上野保存については、台東区が大きく関わり、貢献したとのことですが、保存に至る経緯をお聞かせください。
近藤 : 奏楽堂も建立以来100年近く経ちますと、古くなってがたがきていますから、このままでは危ないというので明治村へ移築するという協定が作られました。しかし建築学会が強く反対しました。由緒ある建物ですから、ぜひ現地で保存してくれと。そういう要望書を文部大臣文化庁長官、東京藝術大学長へ出しました。藝大(東京藝術大学)OBの芥川也寸志、黛敏郎ら7人も、反対のために集まりました。そして強力に反対していこうということで昭和55年(1980)の2月に音楽家を中心にして「奏楽堂を救う会」という団体をつくりました。約1700名が署名したとあります。

旧奏楽堂のシャンデリア

様々な蝶番(ちょうつがい)類と部材
一方で台東区長の内山さんは、文化行政を充実したいと思っていたんです。しかし藝大とのコネが何もないんです。そんなとき藝大が奏楽堂の問題で困っているという話があった。なんとか台東区が入ってくれないかという話でした。そこで隅田公園に、奏楽堂を移築しようという案を出し、その案をもって藝大に行くとすごく喜ばれて、学長も美術学部長も賛成でした。9月になってその台東区案を救う会に説明したんです。そうしたら黛さんが「隅田公園じゃ、明治村にいくのと大差ないんじゃないか。100歩譲って上野公園だ」というんです(笑)頑として譲らなかった。それで上野公園で都知事のところへ行ってみようということになりました。都知事は「奏楽堂っていうのは国の問題じゃないか」と。東京都は国連大学を青山に引き受けたばかりという事情もあり、やんわり断られました。しかし「皆さんの気持ちはわかったから、これからも協力しましょう」ということでした。しかし文部省、藝大は隅田公園案の方が早く片付くと考え、文部省の管理局長から内山区長へ移築費用は文部省が全部出し、管理は台東区へ任せたいので、早く奏楽堂を救う会をまとめてくれという要請がありました。その後、文部省、東京都、台東区、救う会、国会議員で五者会談が参議院の議員会館で開かれることになりました。しかしやはり黛さんは隅田公園案については頑として反対でした。芥川さんはこれでいいんじゃないかという顔だったけれど(笑)、結局だめでした。
そこで一切白紙にして、いらっしゃっていた東京都副知事に、上野公園にということでお願いしようということで別れたのが、昭和56年12月上旬です。1月になったら、都知事が政治決断で上野公園に置けるという情報が入ったので都知事のところに行きました。都知事は受け入れをしますと表明しました。そして、もう一度会議を開くことになり、衆議院第二会館で五者会談を行いました。その五者会談で一番大切な協定書を詰めたんです。
協定書の第一条に奏楽堂は重要文化財に指定されること。第二に移築の主体は文部省が行うということ。維持管理は藝大が行い、防災に十分配慮すること。第三条は都市公園法上の教養施設として設置の許可をする。第四条は音楽ホールの使用と、音楽資料の展示は一般に公開すべきこと。
しかしそこから場所がなかなか決まらないんです。地元町会に反対されてしまって。上野公園は公域避難場所になっているのですが、木造ですし、防災上悪いという問題になりました。東京都内部もだいぶもめて、昭和58年(1983)の1月になってもまだ決まらない。そして2月になってやっと、東京都美術館の跡地に決まりました。それで、4月になったら一般の教養施設に文部省は金を出せないと言いだした。そこで、なんとか台東区でもってもらえないかという話が東京藝大学長からありました。話を受けた内山台東区長は驚いたのですが、隅田公園に引き受けると言ったときに元々台東区が金を出そうと思っていたのだから、また元に戻ったと考えればいいと思い、なんとかしましょうと言ってくれたんです。そうして都知事に許可を得て、協定書の移築の主体を文部省から台東区にし、事業主体も台東区に移ったということです。

移転工事風景

舞台の天井ドームの骨組み
文化財というのは、保存するということです。しかも生きた文化財として。文化財の評価とは、これは使われているということです。保存するだけでも立派なのですが。補修や塗り替えもしなくてはいけませんが、文化庁の許可が必要になったりします。壁の塗り替えをするだけでも、昔のままできるだけ残そうとすると何千万とかかりますから。文化財になるということは相当覚悟がないと生きたまま使うというのはできないのです。(次ページに続く)

奏楽堂の部材


山口半六が手掛けた旧兵庫県庁は、明治35年(1902)に竣工した近世フランスルネッサンス様式に則った建物です。現在は、建設当時の姿に復元され、兵庫県公館として公開されています。