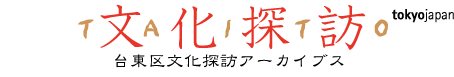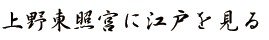上野東照宮の造りについて
Q : 社殿は慶安4年(1651)に造営替えされたとのことですが、その他に現存しているものがございますか。
社殿、そして唐門、透塀(すきべい)と、すべて当時のまま現存しております。
Q : 江戸初期の彫刻師の左甚五郎(ひだり じんごろう)が手掛けた作品があるとのことですが、どれでしょうか。
左甚五郎が手がけたと言われますのは、唐門の龍の彫刻4体のみと言われています。
Q : 透塀は、どのような方が手掛けられたのでしょうか。
透塀は、狩野派の絵師が下絵を描いて、それを彫師が彫ったと伝えられています。透塀の彫刻は257枚ありまして、塀の上段には野山の植物や動物が彫られていて、下段には海川の水の生き物が彫られています。上段には小鳥が多いのですが、昆虫や猪、鹿などの動物もあり、下段には海鳥や魚貝類、鯰や蛙などが彫られています。数多くの種類の動植物が彫られていますが、身近によく見掛ける雀(すずめ)や燕(つばめ)、蝶々や紅葉などもあり、楽しむことができます。

透塀の吐綬鶏(とじゅけい)の彫刻
Q : 透塀は、先年の保存修復工事の際に修復されたとのことですが、どのように復元されたのでしょうか。
修復前は、透塀の彫刻はすべて弁柄漆(べんがらうるし)で塗られていました。日光や久能山の東照宮はすべて色が施されておりますので、江戸初期には彩色が施されていたと考えられています。創建当時の姿を復元するために、弁柄漆を取り去れば下の色が出てくるのではと思われたのですが、昭和40年(1965)の修理の際に前の色を除去して弁柄漆を塗ったようで、色が出てきませんでした。今回、彩色を施すということになり、257枚の彫刻の動植物をすべて特定しまして、実物に近い彩色が施されました。
Q : 復元にあたっては日光東照宮なども参考にされたのですか。
日光東照宮の彫刻が豊富ですので、参考にさせて頂きました。
Q : 社殿は、どのような造りになっているのでしょうか。
社殿は権現造ですが、正面手前が拝殿(はいでん)で、奥に本殿があります。その間に石の間と呼ばれる幣殿(へいでん)があり、一段低くなったところで繋いだ三室の造りになっています。
外壁は、復元して塗り直したのですが、内壁には狩野探幽の障壁画がそのまま残っています。加筆してしまうと文化財としての価値が無くなってしまいますから、今回は剥離した部分の金箔や漆を塗り直し、絵具の剥落止めを施す程度に留めていますので、創建当時の姿がご覧になれるかと思います。
Q : 国指定重要文化財として指定されているのはどちらですか。
社殿、透塀、唐門と48基の銅灯籠、そして大石鳥居が重要文化財に指定されています。

大石鳥居
Q : 参道に配置されている灯籠は、どの程度あるのでしょうか。
銅灯籠が48基と、石灯籠が200基程ございますが、ほとんどすべてが慶安4年(1651)の社殿建て替えの造営の年に寄進されたものです。その中でも最も古いものは、藤堂高虎からの寄進の銅灯籠で、家康公十三回忌の寛永5年(1628)のものです。銅灯籠の台座は八角形になっていますが、この灯籠だけ少し小さく台座が円形になっています。

藤堂高虎寄進の銅灯籠
Q : 参道は当時のままですか。
参道は大石鳥居までは変わっておりませんが、以前の資料を見ますと、その先は不忍池(しのばずのいけ)の方まで延びていたようです。公園整備などで少しずつ縮小されてきました。
Q : 不忍口(しのばずぐち)の鳥居へと降る階段がありますが、そちらからも参詣される方は来られていたのでしょうか。
そうですね。
Q : 参詣される方の多くは、広小路から入って来られるのですか。
はい。そちらが主な参道です。不忍口に面した鳥居の参道は、不忍参道と言いますが、石段は幕府が造営したのではなくて、こちらの参拝者の方が私財で造られた階段なんです。当時にしても珍しい短い段と長い段が交互になっている階段です。

不忍口の鳥居
連携について
Q : 現在、日光や久能山の東照宮との連携はあるのですか。
東照宮連合会がありまして、日光がまとめて下さっています。それぞれが独立した宗教法人ですから、それほど強い繋がりではないのですが、会報が届いたり、時々宮司様にお目に掛かったりすることはございます。
重要文化財として
Q : 社殿内は、一般の方は見学ができるのでしょうか。
以前はお入り頂いていたのですが、外気による劣化や、修復工事中に起きた東日本大震災の影響もあり、耐震構造にできない社殿は、現在非公開とさせて頂いております。
Q : 参詣されるのは、どのような方々がおられますか。
海外からの方が大変多くおられます。平日でも半数の方が海外の方ですし、多い時には7割程が海外の方です。年間20万人程の海外からの方がお出でになりますので、パンフレット、ホームページを初めとして境内の説明板なども日本語の他に英語も加えております。境内の絵馬にも、様々な言語が見られます。

Q : 海外の方はどのような情報を得られて、こちらに来られるのでしょうか。
ガイドブックやホームページでも紹介されているようですし、こちらに来られるのは、秋葉原をまわって浅草に行く間、ちょうどここの立地が真ん中に位置しますし、美術館に行かれたり、そのついでにこちらにお寄りになるという方も多いようです。
Q : 海外の方はどちらの国の方が多いのですか。
頂いたお賽銭に外国硬貨がたくさん入っており、毎月どこの国のものか並べてみていますが、一番多いのは台湾の方ですね。次がアメリカ、韓国、中国が上位5ヶ国にいつも入りまして、その他ではタイも多いですね。ベトナム、その次がヨーロッパでしょうか。時折、北欧やロシアの硬貨が入っていたりすることもあります。
Q : 今後、更に参詣客を誘致する企画など計画されていますか。
重要文化財として、こういうものもあるということを日本国内の方々はもちろん、海外の方々にも知って頂ければと思っていますので、日本語の他に外国語のホームページなども作成しております。
ぼたん苑の開苑のシーズンには多くの方がお出でになりますが、昨年(2018)は台東区から依頼があり、社殿のライトアップを行いました。日本の方も外国の方にも夕闇に浮き上がる金色の社殿をとても楽しんで頂きました。今年もまた行えればと考えております。
ぼたん苑について
Q : ぼたん苑はいつ頃開苑したのでしょうか。
昔の絵などを見てみますと、現在のぼたん苑の場所は木々が生い茂ったところでしたが、そこを整備してお参りにいらっしゃる方々がお楽しみ頂ける場所にしたいと、昭和55年(1980)に開苑致しました。社殿の彫刻に数多くの牡丹(ぼたん)があり、また牡丹は百花の王とも言われていることから、上野東照宮に相応しい花ということで選定致しました。(次ページに続く)