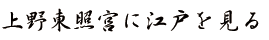上野東照宮禰宜の嵯峨まきさん
上野東照宮禰宜(ねぎ)の嵯峨まき(さが まき)さんにお話しを伺いました。(2019年2月に取材しました。)
上野東照宮の歴史について
Q : この辺り一帯は藤堂家の地所内で、そこに上野東照宮が造営されたということですか。
嵯峨 : 上野東照宮と上野動物園一帯はすべて津藩主であった藤堂高虎の下屋敷だったと聞いております。
Q : 家康公をお祀りするために創建されたとのことですが、由来についてお話し頂けませんか。
家康公がお亡くなりになる2ヶ月前に、藤堂高虎と天海僧正を枕元にお呼びになって、三人一つ処に魂鎮まるところを造って欲しいと遺言をお残しになりましたので、その後寛永寺として現在の上野公園を整えた時に、当時の津藩主の藤堂高虎家の下屋敷地の跡に東照宮を勧請して造ったというのが始まりです。
Q : 創建当初から、一般の方も参詣(さんけい)が許されていたのでしょうか。
当初はそうではなかったようです。浅草寺の隣に浅草東照宮というのがありまして、そちらに日光東照宮まで行くことができない方々がお参りしていたとのことですが、浅草東照宮が火災に遭い、家康公をお祀りするところで火災があってはならないということで、再建を許さず、代わりに江戸の庶民の参詣所として整えるため、こちらを日光に準ずる建物として慶安4年(1651)に造営替えしました。
Q : 東照宮が、浅草寺の境内にあったのですか。
浅草寺の五重塔寄りに丸太橋のようなものが掛かっていますが、その先にあったとのことです。こちらが江戸庶民が参詣するところで、他には江戸城内の紅葉山にも東照宮がありましたが、そちらは将軍しかお参りできないところでした。
Q : 東叡山を開いた天海僧正は天台宗でしたが、こちらの宗派はどちらになるのでしょうか。
こちらは、日光東照宮を大本とした東照大権現の神社ですが、昔の記録を見ますと、東叡山東照宮という記述も見られますので、天台宗の中のひとつの子院のような扱いだったようです。
Q : 正式名称は何と言われるのでしょうか。
現在は日光や久能山と同じく、東照宮が正式な名称です。(右段に続く)
Q : 戊辰戦争時にも、戦火に遭われなかったとのことですが。
上野の山での戊辰戦争のひとつの、いわゆる上野戦争(旧暦 : 慶応4年5月15日(1868年7月4日))時には、彰義隊の本部が上野東照宮の近くに置かれたということですが、寛永寺の根本中堂などは大火に包まれたものの、東照宮や五重塔、そして護国院、清水観音堂などは火の手が及ばずに残りました。他の東照宮も火を着けられたところはひとつもありませんでした。新政府軍は幕府が憎しと言えども、神様の居られる場所ですから、畏敬の念により避けたのではないでしょうか。
Q : 創建当時は、東照宮の管理はどのようにされていたのでしょうか。五重塔も東照宮が管理されていたのでしょうか。
五重塔は、現在は上野動物園内の遊歩道に面してありますが、本来は、上野東照宮の参道を向いている面が正面になります。東照宮は幕府が建立し、日光と兼務で宮司を務めていた時代が長いようですが、現在はそれぞれ別に宮司が勤めております。
Q : 管理のための組織は、どのような形になっているのでしょう。寛永寺との関係はあるのでしょうか。
現在は一宗教法人となっていますが、神社本庁に属しておりますので、神社本庁傘下のひとつの神社ということになります。寛永寺とは明治時代の神仏分離令により分離させられましたが、歴史を辿りますと、いわゆる神仏習合としてのひとつの組織でしたので、寛永寺には今でも色々とお伺いすることがあります。
Q : こちらには、一般の方は祀られていないのですか。
はい。家康公と吉宗公、そして慶喜公の三柱をお祀りしております。
Q : 天海僧正は、京都に倣って上野の山を東叡山として造られたとのことですが、東照宮はどのような位置付けだったのでしょうか。
比叡山を模した東叡山や清水寺に見立てた清水観音堂、琵琶湖を模した不忍池などがある一方で、特に京都に有名な東照宮があるわけではないのに、どうして東照宮があるのかと、よく尋ねられます。やはり家康公の遺言もありましたし、幕府が造った一大寺院、参詣所という位置付けで東照宮も不可欠だったのではないかと思います。(次ページに続く)


上野東照宮禰宜の嵯峨まきさん