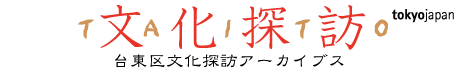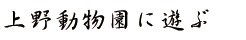「ゴリラの住む森」全景

Q:もっとも手が掛かる動物は何ですか。
小宮: 冷房施設が必要なジャイアントパンダなどですね。動物は体調を壊されると困るので、夏場は人間が冷房を我慢しています。
Q:動物病院、調理室について
専従の獣医が、4名います。獣医は人間相手と違って、目から歯まで全部見なければいけません。調理室は、各自の担当の動物の餌を調理しています。外来種のためには、入手できない食物もあります。マダガスカル島から来ているアイアイは、主食のラミー(クルミのような木の実)が手に入らないので、マカデミアンナッツで代用しています。ジャイアントパンダの主食の竹は日本にもありますので、パンダの方がコアラよりも経費は掛かりません。コアラの主食のユーカリは日本にないので、農場を作り栽培から行っています。
Q:国立科学博物館などに死亡した動物の遺体を寄贈する事は多いのですか。
近在の国立科学博物館などで、亡くなった動物を良い状態で剥製として保存して頂けるので助かっています。名前が付いていない最初のメスの象の全身骨格などもあります。
Q:東日本大震災の影響はありましたでしょうか。
アクアマリン福島という水族館から震災のためカワウソを預かっていました。セイウチやトドは、鴨川シーワールドで預かるなど、みんなで分担していました。また、震災当初は仙台に餌が届かなくなってしまったので、すぐ手配をして餌を運びました。阪神淡路大震災の時にも、王子動物園の閉鎖期間が長かったため、近畿地区の動物園が協力して、動物を預かったり餌を運んだりしていました。(右段に続く)

平成11年(1999)、第11回 種保存会議が、日本動物園水族館協会と上野動物園の主催で開催されました。同会議は、加盟園館の持ち回りで開催されています。
Q:上野動物園のサル山について、紹介下さい。
上野動物園のサル山を作る際は、左官さんが房総の高宕山まで猿を見に行きました。アメリカでは、グランドキャニオンなどの岩場の型を取り、パテントを取得しています。これが世界のひとつのモデルとなっているため、日本の動物なのにグランドキャニオンにサルがいるような、おかしな状況になっています。上野動物園のサル山は、日本の風景と言えるでしょう。
「ゴリラ・トラの住む森」の展示スペースの周囲を擬岩で囲っていますが、本来はジャングルなので、壁面緑化を進めています。これには、温度を下げる効果も期待できます。
Q:寒冷地と熱帯地の動物の棲み分けはできているのでしょうか。
上野動物園では、スペースや環境の問題から、なかなかできない部分もあります。多摩動物公園では、敷地に地域別に分けて動物を飼っていますが、広大なため動物のいる景色は描けるけれど、遠過ぎてヤマアラシのとげまでは描けないという東京藝術大学の学生の意見もありました。上野の狭さと近さが、動物の鼻の先からしっぽまで見たい人にとっては魅力かもしれません。(次ページに続く)

平成11年(1999)、コビトカバの35年ぶりの出産