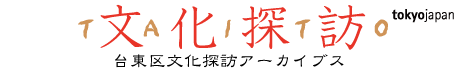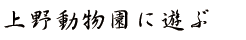Q.なぜ上野公園に動物園が置かれたのでしょうか。
小宮: きっかけは、明治10年(1877)に開催された第一回内国勧業博覧会でしょう。町田久成、田中芳男を中心として、自然史博物館の付属に植物園があり、その中に動物飼育場があったパリのメナジュリーをモデルにし、現在の東京国立博物館の付属として、上野の山のあまり環境の良くない谷間を動物飼育場にしました。現在では、面積は設立当時よりも10倍程度に拡がりました。東園と西園を繋ぐモノレールは、昭和32年(1957)に日本で初めて設置されましたが、都市交通として使用できるかの試験運用だったと聞いています。
Q:上野動物園では、マダガスカルに生息しているアイアイやキツネザルの繁殖に力を入れられているとの事ですが。
アイアイは、世界でも今はアメリカのデューク大学と上野動物園しか繁殖に成功していません。現在、上野動物園にはアイアイが8頭いますが、6頭はここで生まれました。国際会議に、アイアイの紹介パンフレットを持って行くと、「アイアイを飼っているのですか。」と感心して、先方の態度が変わります。奄美群島に生息するルリカケスも、現地ではやや増えて保護種としてのランクは下がりましたが、沢山いる時にこそ研究すべきです。ひとつの巣で4、5羽が成長しても、ヒナはカラスに食べられたりして、ほとんど育たないため、もっとも弱いヒナを飼育しようとしています。(下段に続く)
Q:外来の動物は、日本の気候に合うのでしょうか。
世界中に哺乳類は4000種程いますが、飼育されているものは、その一割もおらず、また飼育が難しいものも多くいます。冷暖房などを駆使して、何とか飼育しています。上野動物園では、スマトラトラを飼育していますが、冬は暖房を入れています。中国のトラなどの日本と気候の近い地域の動物を飼育した方が、余分の冷暖房などのエネルギーを使わずに済みます。千年、万年単位で考えれば、種の保存のためには、世界各地で飼育すべきですが、シベリアの寒冷地に棲むアムールトラを北海道で飼うなら良いですが、温暖な九州で飼っていると種が変わってしまうかもしれません。そのために、冷暖房などの設備は欠かせません。(右段に続く)

Q:日本全国の動物園や水族館では、特長のある展示ばかりが話題になりますが、将来の動物園像とはどのようなものでしょうか。
将来の上野動物園は、環境動物園であり、文化動物園だと考えています。「上野動物園の一番の自慢は何ですか。」と聞かれたら、ジャイアントパンダという答えを期待されていると思いますが、実は不忍池です。東京湾で絶滅しそうだった鵜を上野動物園に移して1000羽程に増えた時に、鵜の糞で木々が枯れて、不忍池は鵜と蓮だけになってしまいました。島は鵜の糞で真っ白になりましたが、ひとつの島に飛べない鷲を放したら緑に戻りました。さらに池に白鳥を放したら、蓮のレンコンを食べていました。蓮のために今は維持費を掛けていますが、生物多様性の環境に戻れば、人工的な経費を掛けずに済みます。このように生態系について小学生にも分かりやすい説明ができるようにしたいですね。
動物を自慢すれば、他の園でも真似る事はできるかもしれませんが、不忍池という自然環境や五重塔、藤堂家の墓、家光が休んだ囲炉裏があるという閑々亭、そして開園から130年の歴史は、他の動物園では真似はできません。


生物多様性が回復しつつある不忍池


生物多様性が回復しつつある不忍池