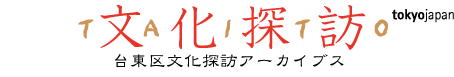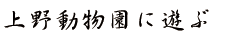平成23年(2011)10月28日にオープンした「ホッキョクグマとアザラシの海」

小宮輝之 上野動物園 前園長(現公益財団法人東京動物園協会常務理事)
上野動物園の前園長の小宮輝之さん(現公益財団法人東京動物園協会常務理事)に、お話しを伺いました。
Q:近年、自然保護や希少動物の繁殖に力を入れられているようですが。
小宮: 昨年(2010年)の生物多様性年でも使われた言葉ですが、生息域外で動物を保護し繁殖させる域外保全を動物園では行っています。動物園は生息域内保全とも連携しなければなりません。昭和33年(1958)に上野動物園でクロトキを飼い始めた当初はうまく行かなく、繁殖の成功には11年が掛かりました。生アジだけを与えて飼っていたのでは増えなかったため、人工飼料を作りました。この人工飼料を、今では200羽以上に増えた生息域の佐渡や中国のトキにも食べさせていました。現在、上野動物園ではトキを飼ってはいませんが、域内保全に貢献した例です。
それぞれ世界中の動物園が一種類ずつ、域内保全に貢献する域外保全をやれば、例えば160ある日本の水族館と動物園では160種のデータが集まり、これからの保存の指標になります。上野動物園や多摩動物公園に30羽程いるアカガシラカラスバトは、本来は東京の小笠原諸島にしかいないハトですが、日本の国内動物のアカガシラカラスバトの域外保全を外国の動物園が行ったら、私たちにとっては恥ずかしい事でしょう。トキやコウノトリは、アジア大陸に残っていたから良かったのですが、アカガシラカラスバトは小笠原にしかいない鳥なので滅べば終わりです。

Q:現在の上野動物園における在来種と外来種の割合はどの程度ですか。
鳥は200種程いて、半分は日本の鳥です。世間では動物園とは、ジャイアントパンダ、ゴリラ、ゾウなどのイメージが先行していますが、哺乳類も130種類程いる内、在来種は意外と多くいます。園内の家畜もすべて在来種にしました。外国からのお客様が来られた時に、「明治維新までの1500年間の日本の生活を支えて、武士が乗っていたのは、この木曽馬なんですよ。」と紹介ができます。西洋のサラブレッドやポニーがいるとがっかりされます。ニワトリの場合は、一般に積み出し港の名前が付くため、日本のオナガドリの英名はyokohamaと言います。外国からのお客様に日本の文化である実物を見せたい。ふれ合いと文化が大事ですね。
もう一点、遺伝子を残す事も大事です。ブタはアグー、ヤギはトカラヤギがいますが、両方とも小さい。日本では、仏教の影響で肉食は忌避されてきましたが、沖縄では食されていて、ウシやブタは小さい事が大事でした。冷蔵庫がないから、一度処理してしまうと食べ切ってしまわないといけませんから。今回の原発事故のように、もしも電気が使えなくなった時には、このような小さい遺伝子が大事になってきますね。(右上段に続く)

アグー豚

在来牛(左: 口之島牛、右: 見島牛)
Q:種の保存のために、それぞれの動物園の間で交換されているのですか。
例えば、「ジャイアントパンダの子供の所有権は、どこにあるのですか。」とよく聞かれますが、所有権はありません。動物は、世界共通の財産です。オランダで生まれたゴリラが、一旦オーストラリアに行って、配偶者が見つからなかったので、今上野動物園に来ています。オーストラリアやオランダにも兄弟が沢山いますので、係累のいない日本で増やした方が世界中のゴリラのためになります。
これまでのジャイアントパンダは、国際親善のために贈ってもらいましたが、今回は贈ってもらうのではなく保全費用を払ったのは、パンダが絶滅して欲しくないからです。希少動物を絶滅させないために、中国にではなく、パンダに代価を払っていると考えています。パンダの展示をずっと続けて行くのなら、一緒に保護もする必要があります。金銭的な援助をし、見返りに日本でパンダを展示して、中国には野生のパンダは1600頭程度しかいないという事も知ってもらいたいのです。日本では、5年前に5000頭、昨年は4000頭のツキノワグマを危険という事で殺しています。もし中国でパンダが人を襲った場合、あっと言う間にいなくなってしまいます。
Q:北海道では、熊と共生していると聞いていますが。
通常は人里に出て来た熊は、二度捕まると駆除をしますが、知床では通学路や学校を電気柵で囲っています。イギリスでは、何世紀も前に絶滅させてしまっている事を考えると、小さな北海道で熊と共存しているという事は、大変すごい事だと思います。
Q. 乱獲などによって絶滅した動物も多いのでしょうか。
日本で有名なのは、ニホンオオカミですね。明治時代以降、西洋の牧畜が入って来て絶滅しました。欧米式の農業を教えるために来日した欧米人がオオカミの効率的な殺し方を教えた結果です。アメリカでは、野生のバイソンも乱獲で絶えてしまいましたが、動物園や保護区に残っていたのを増やしました。ヨーロッパバイソンは野生が絶滅して、動物園に残っていた50数頭を血統登録して近親交配にならないように注意して、一世紀程度も掛けて増やして森に戻しました。
Q:お客さんは、動物園に珍しい動物見たさに来るのでしょうか。
アルブレヒト・デューラーは見た事もない犀(サイ)を描いていますが、伝聞だけで描いたか、実物を見て描いたかは明白です。例えば、トラは古い時代に日本に入って来ていますが、ライオンは慶応年間からですから、獅子の絵は想像で描いていたため、オスもメスにもたてがみがありますね。(次ページに続く)

アルブレヒト・デューラー「犀」(木版画、1515)

小宮輝之 上野動物園 前園長(現公益財団法人東京動物園協会常務理事)